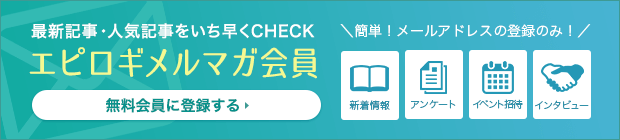被災地支援を振り返って
熊本の経験を明日へ生かすヒント
吉田 穂波(国立保健医療科学院 生涯健康研究部 主任研究官)
医師の皆さんの中には、現地での支援活動に参加された方もいるでしょう。状況を見守ることしかできずに歯がゆい思いをした方もいるでしょう。
緊急支援が必要な時期を過ぎ、被災地以外はほぼ日常を取り戻した今、皆さんの心に抱えるものはないでしょうか。
そんな皆さんに向けて、産婦人科医で国立保健医療科学院・生涯健康研究部・主任研究官である吉田穂波先生に、先の東日本大震災で支援活動を行った経験からメッセージをいただきました。

このたびの熊本地震では、全国各地からさまざまな応援の気持ちが寄せられました。
同じ国に住む仲間として、助け合う思いを感じ、人の持つ良さ、優しさに感動した人も多かったと思います。
そして、実際に被災地で支援活動をされた方も多いでしょう。
今の皆さんのお気持ちはどうでしょうか。疲れ、いらだち、不全感などを感じていらっしゃる方はいないでしょうか。
被災地支援活動を振り返り、日常に戻ってからの落ち着きを取り戻し、再び自分の役割に向かい合うため、今ここで「Transition Time(移行期)」をきちんと持つことも大切かもしれません。
以下、この支援活動を次に生かすためのヒントについて、これまで勉強してきたことを書かせていただこうと思います。
読者の皆様からのご意見、ご批判をいただければ幸いです。
自分の感情労働を認める
被災地支援をする側に求められることは、肉体的な動きというよりは、「感情労働」かもしれません。感情労働とは、仕事の場で自分の感情を抑制し、コントロールしなければならない職業や労働を指す言葉です。
以下の文章は、一橋大学教授の宮地尚子先生が、阪神大震災における支援者の心のケアについて、読売新聞の「論点」というコラムに書かれたものです。1995年4月1日の記事ですが、今読んでも非常に心を動かされる内容なので、ご紹介したいと思います。
「被災支援者に心のケアを」 阪神大震災から二か月半。表面上はようやく落ち着きが戻ってきた。しかし、人々の心の傷とその回復という点ではむしろこれからが正念場である。今回の震災では幸い、被災者の心のケアの重要性が早期から指摘され、援助活動も行われているが、その陰に隠れて見逃されやすいのが「被災者を援助する人たち」の心の問題だ。
被災者の生活の回復は、消防救急隊員、警察官、医療福祉関係者や学校教諭、地方自治体の職員、避難所の自治会のリーダー、ボランティア団体のスタッフ、ライフラインの復旧従事者など多くの人たちに支えられている。これら援助者の中には、最初は必死の思いで無理な仕事量をこなしてきたけれど、今、疲労の極致にあるという人が多いのではないだろうか。
意欲が落ち、仕事のミスが増える。たばこや酒の量が増える。胃痛や頭痛、生理不順など身体の不調。眠れない。集中できない。いらいらし、怒りっぽい。これらはみんな精神的ストレスの高まりを示す危険信号だ。ほうっておけばうつ病、燃え尽き症候群、休職や大きな労働事故、過労死、自殺といった事態になりかねない。
また、援助する側が心の余裕と笑顔を失えば被災者との関係にもひびがはいり、ひいては被災者の心の回復をも遅らせる結果になる。
援助者の多くは緊張を強いられる長時間の労働をしてきている。生死にかかわる迅速な決断を迫られ、無惨な死体を取り扱い、遺族の嘆き悲しみに直接ふれる第一線の仕事。きめ細かなアレンジが重要にもかかわらず、自分がどう役立っているか見えてこない後方支援の仕事。必死でやっても感謝の言葉より不満をぶつけられる方が多い行政窓口の仕事。いずれも精神的にかなり負担の多い状況だ。
でも、こうした援助者の精神的負担は本人も周りも認識しにくく対応が遅れがちだ。当然の業務ということで理解や同情が得られず、調子を崩しても「ひよわ」「怠けている」とみなされやすい。
実際には自分より他人のことを優先する責任感の強い人ほど、仕事を抱え込んでしまう。まじめな人ほど被災地を離れて休養をとり遊ぶことに罪悪感を抱く。被災者に感情移入すればするほど自分の家族の悩みがつまらなく見えるなど感覚にずれを生じ、本来の生活基盤をも崩しがちだ。
また、援助職にある人ほど援助されるのは嫌がる傾向もある。支える側の人間が世話になるなんてと助けを求めるのが遅れる。他者を支えることで使命感や充足感を得ている場合、自分の精神的不調を認めるだけで「必要とされる強い人間」という自己アイデンティティが壊れかねないからだ。
では、援助者を支えるための具体的な対策とは、どんなものだろう。まずは、われわれ皆がその人たちの努力を認識し、ねぎらうことである。ごくろうさまの一言がどれほど疲れを癒すことか。震災後の対応の批判も必要だが、自分がその場に立ってできそうにもないことを、離れた所から攻撃すべきではない。
被災地外部からの継続的な人的支援も必要だろう。内部の人間として働く専門職員の長期貸与などの制度を各職域別にもっと考えてもいいのではなかろうか。
つぎに、職場での取り組みである。業務量と時間の制限、計画的な休養、安全で快適な職場環境の確保など労働衛生の基本条件は非常時にこそ厳守すべきものだ。
また全体の様子が見えるよう情報をオープンにし、ゴールをはっきりさせ、個々人がやりがいや達成感を持てるようにすること、責任範囲を明確化し、矛盾する役割を一人に課さないことも重要だ。トップに立つ人間は実行できない美辞麗句を並べるべきではない。建前で約束したことと現実とのギャップを指摘されて非難を浴びるのは、常に現地のスタッフであり実務をつかさどる職員である。
メンタルケアに関しては、災害が及ぼす被災者や援助者への心理的影響について知識を広め、意志の強さでどうにかなるという根性論を捨てることが必要である。仕事上のつらい経験や感情を共有できるような、定期的な話し合いの場も非常に有効だ。その場合は、精神的に弱いと思われるのを恐れて参加しない人もでてくるので、全員を対象とする。必要な場合は勤務評定に影響しない状況でカウンセリングや専門的治療につなげていくことも重要だろう。
本人にはとにかく「がんばりすぎないで」と言いたい。自分がいなければという過度の思い込みを捨て周りに仕事を預けること。自分の貢献を積極的に評価すること。仕事場を離れ、ゆっくり休めば、視野が広がり仕事の能率も上がる。そして援助者も精神的にまいって当然であり、援助をうけるのは恥でないと考えてほしい。
支えられるばかりでも支えるばかりでも、人間は生きていけない。自分は強い人間だと虚勢を張るより、時には弱音をはき愚痴をいい、めげたり涙を流したりする人の方が、しなる竹のように息の長い支援を続けられるはずだ。
被災者の心のケアの必要性は知られていますし、今回もたくさんのチームが心のケアの支援を行いました。一方、支援者の心のケアの必要性は気づかれにくく、忘れられがちです。
支援者にも「支援」が必要ですし、自分を犠牲にしない方法で、どう支援していくかを考えて行動することが重要なのだと思います。
これから、被災地の中と外の人が本当に対等な協力関係を築くため
2011年、私が東日本大震災後の支援活動のためにさまざまな勉強をしている中で、「支援学」というものがあることを知りました。たとえば、支援をする側が状況を型にはめ、こちらの偏見や推測、期待を持って接してしまうと、支援を受ける相手は誘導されていると感じ、うまく信頼関係を築けないということが系統立てられています。
実際に、地元の人や被災者の方と、外部からのボランティアの方のトーンやスピード感が違うということは、阪神・淡路大震災の時も指摘がありました。
こちら側は、「遠くから来ました! 何かできることはありませんか?」と意気揚々と現地に入り、何か特別なことをしたがっています。しかし、現地の人々は普通の生活をしていて、そんなに大きな望みはありません。
「最高のものを提供することが最良ではない」とは、私が一緒に活動していた家庭医が話していた言葉です。最新の医療・物資、最高の技術を提供しても、それが一過性のものであれば、普通の生活に定着しなければ、喜ばれないでしょう。
あまり「支援者」「被災者」と線を引かず、対等な協力関係を結ぶ、関係性を築いてから相手がどんな支援を必要としているかを見つけていく、ということが、実はとても難しいのです。
支援学から学ぶ被災者支援のコツ
・支援者が被災者の問題に対し当事者意識を持つのは大切だが、問題の解決方法を編み出していくのはあくまでも被災者である
・支援する側の努力が受け入れられなくても腹を立てない。何があっても支援者が保身的になったり、恥や罪を感じたりしないようにする
・誤謬を起こさないほどに被災者の現実を十二分に知ることはできないし、むしろ誤謬を起こし、それに対処していくことで、被災者の現実をもっと良く学んでいける
・支援を求める人が気まずい思いをしているということを常に念頭に置きながら、その人が何を望んでいるかということを必ず問いかけるようにする必要がある
この東日本大震災の時に支援学を学問的に学び、それを実地で活かし、また教科書に戻って考える、反省する、というサイクルは、私にとって大きな糧となりました。
被災者のためだけではない支援活動
今回の熊本地震では、私が東日本大震災で学んだことが、当てはまる部分とそうではない部分があると思います。
私自身は、役に立ちたくて飛んで行ったのに、無力を感じながら戻ってくることの繰り返しでした。その情けなさの中で、何かにすがろうと手当たり次第にいろんな文献を読み、たくさんの講演会を聴いて勉強してきたような気がします。
医療の中から地域に出て、地域保健の政策研究という分野に取り組んだのも、この時の未完了感がもとになっています。
「何もできなかった」と無力感を抱く方々も、罪悪感を抱く方々も、今回の経験が、日常に戻られてから、そして診療に戻られてから、きっと何かに役立つはずです。
今回の支援活動が、読者の皆様にとってどのようなものだったのか、どのような意味があるのか。支援に行く前といった後で何か変化したことがあるのか。熊本に住む皆さんのために働いたという経験を通じて、何を得たのか。また、今後の仕事や生活に対してどのような姿勢で向き合いたいと思うのか、立ち止まって、少し考える時間を取られるといいかもしれません。
そして、ぜひ、たくさんの方に、ご自分で得られた気付きを話してあげてください。 その蓄積がきっと、次の進歩につながります。
今回支援活動を行った方も、今後支援活動に参加される方も、どうかご自身のケアを忘れないでいただきたいと願っています。
<参考>
「災害救援者メンタルヘルス・マニュアル」(監修:重村淳/防衛医科大学校精神科学講座、金吉晴/国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所成人保健研究部)
(http://saigai-kokoro.ncnp.go.jp/document/medical_personnel02.html)
「災害救援者のメンタルヘルス対策‐被災地に職員を派遣前・派遣中・帰署後のポイント」(大澤智子/兵庫県こころのケアセンター)
(http://150.60.7.6/wp/wp-content/uploads/2012/11/osawa0317.pdf)
【関連記事】
公益財団法人ときわ会 常磐病院院長・新村浩明氏寄稿「東日本大震災の大規模透析患者移送の経験を通して、熊本地震へのメッセージ」
国立保健医療科学院 生涯健康研究部主任研究・吉田穂波氏インタビュー「母で医師だからわかること~壁があったからこそ見えたもの」前編
産婦人科医・石田健太郎氏エッセイ「医師としての存在価値を肯定できる場所から
~「リアル」を求めた海外ボランティアで“医療に対する謙虚さ”を学ぶ~」

- 吉田穂波
- 最終学歴:ハーバード公衆衛生大学院(2010年卒)
職歴:1998年三重大学医学部卒後、聖路加国際病院産婦人科で研修。2004年名古屋大学大学院にて博士号取得。ドイツ、英国、日本での医療機関勤務等を経て、2008年ハーバード大学公衆衛生大学院入学。2010年に大学院修了後、同大学院のリサーチ・フェローとなり、2011年の帰国後に起こった東日本大震災では産婦人科医として妊産婦と乳幼児のケアを支援する活動に従事。2012年4月より国立保健医療科学院にて、公共政策研究を通して母子を守る仕事についている。著書に、『「時間がない」から、なんでもできる!』(サンマーク出版/2013年)、『安心マタニティダイアリー』(永岡書店/2012年)などがある。