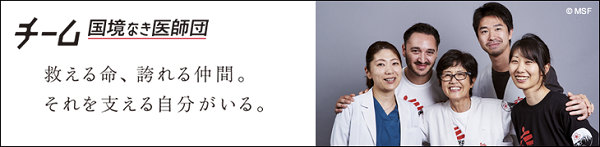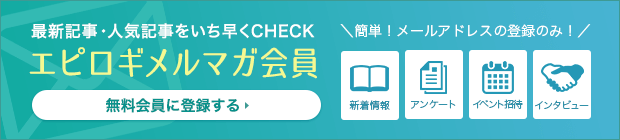医療がない場所で、医療を求める人のために全力を尽くす【前編】
医師としての自分を必要としてくれる人のために
加藤 寛幸 氏(小児科医/国境なき医師団日本 会長)

紛争地域や感染症の流行地、難民キャンプなどで緊急の医療活動に従事する「国境なき医師団(Médecins Sans Frontières=MSF)」。その名前は多くの人が耳にしたことがあるはずだし、活動内容についてのおぼろげなイメージもあるかもしれない。けれども、その活動の実態は、あまり知られていない。納得のいく医療を施すのが難しい現場で、医師たちはどのような活動に取り組んでいるのか。目の前で苦しむ人を救うためにすべてを捧げる……。医師の原点ともいえる活動に打ち込む、加藤寛幸会長にその活動内容や今後の展望などを伺った。
追い詰められたロヒンギャ難民
私が国境なき医師団に参加したのは2003年です。それ以降、スーダン、インドネシア、パキスタン、南スーダンなどで活動してきました。エボラ出血熱に対する緊急援助活動に赴いたり、国内では東日本大震災の被災地にも入りました。

そして2017年の9月からバングラデシュに行ってきました。日本ではあまり詳細には報道されていませんが、そこにはミャンマーから逃れてきた約70万人ものイスラム系の人々、ロヒンギャ難民がいます。私自身の約15年に及ぶ活動の中でも、これほどまでに劣悪な環境を見たのは初めてでした。
人口密度7万人と言えば、どれくらいの密集度か想像できるでしょうか。難民収容地10平方キロのわずかな土地に70万人が押し込まれ、まさに“ひしめき合って”暮らしています。しかも、その土地は湿地帯でぬかるんでいる。
そこにロヒンギャの人たちは、どこからか木や竹を調達してきて、テントのようにビニールシートを張って雨露をしのいでいます。一つのテントの中に数家族が一緒にいるケースも珍しくなく、プライバシーという概念など存在しません。
それどころか清潔な水さえ当初は満足にありませんでした。トイレも十分な数はない、病気がいつ蔓延してもおかしくない極めて非衛生的な環境です。
逃げ出してきたミャンマーでは、女性に対する暴力も相当ひどかったようで、一部の報道によれば、性暴力の被害者の多くがこれから出産を迎えるともいわれています。
キャンプでは、大人も子どもも、みんな揃ったように同じ表情をしていました。なんと表現したらいいのか……、眉間にシワをぎゅっと寄せて目を大きく見開いているのだけれど、瞳の視点は定まっていない。まるで魂を抜かれてしまったかのような虚ろな表情が、どこまで行っても溢れている。
首を切り落とされたり、目の前で隣人が生きたまま焼き殺されたという話も聞きます。よほどの恐怖と疲労と絶望を抱えてきたのでしょう。生気のない顔の人たちが、これほどまでに集まっている情景は、これまでの活動を通じて初めての経験でした。

土地の選定から始まる現地での活動
国境なき医師団の活動は、ヨーロッパに拠点を置く5つのオペレーションセンターによって統括されています。今回の危機以前からバングラデシュで活動を続けていたのはアムステルダムに拠点を置くチームです。ところがまったくの人手不足ということで、バルセロナのチームに続いて日本がもっとも強いつながりを持つパリチームが入り、その後、ブリュッセルのチームも参加しました。
パリのチームは現地で鉄骨を組み、約半年かけて100床の病院を建設しました。70万人に対して100床だから、焼け石に水だけれども、それでもないよりはあった方がいいし、この規模の病院を短期間に立ち上げられるのは国境なき医師団の底力だと思います。
ロジスティクス(物資の調達と管理)を自分たちで賄うのが我々MSFのやり方であり、強みでもあります。サプライセンターが世界に5カ所あり、24時間あれば仮の診療所を立ち上げられるだけの資材が用意されています。我々の活動はあくまでも緊急援助ですから、一刻も早く現地に入り、治療を始めるための体制が整えられているのです。
私たちは先発隊のアムステルダムチームとの役割や担当地域の分担を考え、まず支援活動を行う地域の見極めから始めました。医療に関するニーズ調査を行い、場所の目星をつけた上で現地の機関と調整を図って診療所を立ち上げるのです。こうした調査や準備はある程度経験を積んだメンバーが担当しており、初めて参加する医師は、設置された診療所での治療から現地入りすることになります。

バングラデシュのマイナーゴナ難民キャンプで(2017年10月撮影)
診療所に来る患者の多くは、逃げてくる途中で衰弱し病気にかかった人だったり、キャンプの劣悪な衛生環境のために感染症にかかったりした人たちです。ミャンマーとの国境に近いエリアでは大けがを負った人の外科的治療も行いますが、私たちのいたエリアでは、内科的治療や精神的なケアを中心に行い、外科的治療や帝王切開が必要な人は現地の医療機関に搬送していました。
終わりのない診療所での治療
診療所を立ち上げてからの医師の主業務は、バングラデシュ人の医師のサポートでした。現地にいても、バングラデシュの法律により、本格的な医療行為は基本的に同国の医師しか行えません。もちろん、診療を円滑に進めるために側にいて手助けはするし、人手が足りないので私自身も簡単な診察もしますが、できることは限られています。
診療所を運営していくためには、私のような海外から派遣されたスタッフだけでなく、現地の医師のほか、さまざまな職種のスタッフを現地で雇用し、チームを組む必要があります。そうした人的資源を確保しトレーニングするのも私の仕事でした。しかしニーズはあまりに大きく、一方で医師や看護師が元々そう多くない土地のため、必要なスタッフを探してくるだけで大変です。
診療所ができたと聞きつけると、患者さんが押し寄せてきます。朝からフル稼働して、いくらやっても終わりはない。とはいえ、夕方になるといったん治療を中止し、自分たちの安全を確保するため日が暮れる前に宿舎に戻らなければなりません。緊急性の高い患者さんの治療を先に行い、それ以外の診療待ちの人たちには、翌日の診察引換券を渡して引き取ってもらいます。それから30分ぐらいで片付けをして撤収です。翌朝はまた6時ぐらいに起きて、パンやバナナなどで軽食をとり、道が一本しかないため大渋滞する中を、途中でスタッフを拾いながら診療所に向かう。クルマを停めて、必要な薬などを運び込んで準備を整えたら、9時からまた診察を始める。現地ではそんな毎日を送っていました。

難民キャンプ内の国境なき医師団の診療所で現地の医師とともに子どもたちを診察する(2017年10月撮影)
助かるはずの命を助けられない現実
現地での医療活動は、日本でのそれとまったく異なります。診察や治療に必要な機材はもとより、薬剤なども十分に揃っているわけではありません。
私がバングラデシュを離れる頃よりジフテリアの流行が始まり、その患者数は難民キャンプ全体でおそらく8,000人に達したのではないでしょうか。感染性が強いため、我々の入院施設に患者を集めて治療し、予防接種も行いました。現地では、このようにチームごとに役割を分担してそれぞれの治療にあたるのが一般的です。
ジフテリアは既に日本では見ることのない病気です。仮にかかったとしても日本のような医療体制であれば命を落とすことは稀でしょう。けれど、キャンプには人工呼吸器を始め十分な治療設備がなく、また、たとえ呼吸器を持ち込んだとしても、扱いに不慣れな現地スタッフとともに適切な管理を行うことは難しいでしょう。現地スタッフのトレーニングや教育は重要な課題ですが、初期の段階ではそこまで手が回らない。なんとか当面を乗り切れるよう、今できる最善を尽くすのに精一杯で、十分な手当てをすることなく炎症から気道狭窄を来たし呼吸できずに亡くなる患者さんもありました。
このような、日本であれば当然助かるはずの命を、「助けられない」と判断することも私たち医師の仕事です。このようなジレンマは、初めて参加する方にとってはかなりストレスに感じるでしょうし、私自身、今も、そうした患者さんの最後を看取るたびにやりきれない気持ちになります。そのときに感じる無力感に慣れることは、この先も決してないでしょう。
不思議なことに、現地にいると疲れを感じません。体も心も臨戦態勢というか、非常事態に順応しているというか、ハイテンションになっている。とはいえ興奮状態は3ヵ月位しか持ちません。やがて疲弊し仕事の効率が落ちてくる。ですから、MSFでは最低3カ月に1度は1週間の休みを取らせる仕組みを取っています。また、より状況の厳しい地域に派遣された場合は、スタッフに対しても精神的なケアを行います。
「独立・公平・中立」で守られる、スタッフの安全
紛争地域や被災地での活動に従事するわけですから、安全確保は我々の活動の中で最重視されています。本格的な活動に入る前に、事前準備に特化したスタッフが現地入りし、さまざまな情報収集にあたるほか、あらかじめ対立するあらゆる勢力と対話を持ちます。
国境なき医師団の活動は、「独立・公平・中立」を原則としています。例えばタリバンとアフガニスタン政府が争っている地域では、両方に支援を届けるのだと事前に話をつける。相対立する勢力の考え方がどうであれ、一方に肩入れするのではなく、あくまでも中立的な立場で両方に対して援助活動を行うことを納得させるのです。
そのために原則として我々はあらゆる勢力との対話を図ります。それがタリバンであれイスラム国であれ。ともかく全関係者とコミュニケーションをとることが、安全確保のための大前提となります。
何かあったときにすぐに避難できるようにするため、車両はバックで駐車するというルールを聞かされた時に、日本との違いを実感したものです。また、宿舎には襲撃された際に逃げ込むための部屋が必ず用意されています。
セキュリティに関する責任者の判断は絶対です。彼がひと声「撤収」といえば、直ちに動く。四の五の言っている間に爆撃されかねない。だからこその安全確保なのです。
アフガニスタンに行ったときには、宿舎兼病院の近くで爆発音がよく聞こえてきたし、数百メートルほど離れたところで銃撃戦が起こっていました。正直、最初は恐ろしいと感じましたが、反面、現地の人たちはとても友好的で、敬意を持って私たちの活動を支えてくれていました。
命の危機に瀕する患者がいる限り
なぜ、そのような思いをしてまで、活動に参加するのか。
自分なりに出した答えは、結局患者さんを診るのが好きだからというシンプルなものでした。
自分を本当に必要としている命の危機に瀕した人が居る。そんな人たちに、微力ながらも手を差し伸べることができる。医師として、これ以上のやりがいはありません。もちろん診察中に、そんなことを感じている余裕などないのですが、振り返ってみると充実感に満たされた、この上なく濃密な時間を過ごしている実感はあります。

アフガニスタンのホーストで国境なき医師団が運営する産科および新生児のための病院で(2015年11月撮影)
※中編に続きます
(聞き手=竹林篤実 / インタビュー写真撮影=加藤梓)
国境なき医師団(Medicins Sans Frontieres:MSF)は、独立・公平・中立な立場で、医療・人道援助活動を行う国際NGO。アフリカ、アジア、南米などの途上国、中でも紛争や感染症の流行地などでのその献身的な活動は世界中から高く評価され、1999年にはノーベル平和賞を受賞した。
【関連記事】
・「厚生労働省医系技官・加藤琢真氏インタビュー|日本、そして世界で、医療をいかに届けるか~『人・薬・もの』のデリバリーイノベーションを目指して」加藤 琢真 氏(厚生労働省医系技官/佐久総合病院国際保健医療科・小児科医)
・「医師としての存在価値を肯定できる場所から~『リアル』を求めた海外ボランティアで“医療に対する謙虚さ”を学ぶ~」石田健太郎氏(産婦人科医)
・「海をわたる診療船『済生丸』取材企画|【後編】知ってほしい、より広い医療の世界を~へき地医療の先進地域で、日本医療の将来を見据える」若林 久男 氏(香川県済生会病院 院長)
- 加藤寛幸(かとう・ひろゆき)
- 1965年、東京生まれ。1992年、島根医科大学(現・島根大学医学部)卒業後、2001年、タイ・マヒドン大学熱帯医学校において熱帯医学ディプロマを取得。東京女子大病院小児科、国立小児病院手術集中治療部、Children's Hospital at Westmead(Sydney Children's Hospital Network)救急部、長野県立こども病院救急集中治療科、静岡県立こども病院小児救急センターなどに勤務。国境なき医師団参加後は、スーダン、インドネシア、パキスタン、南スーダンへ赴任し、主に医療崩壊地域の小児医療を担当。東日本大震災、エボラ出血熱に対する緊急援助活動にも従事した。