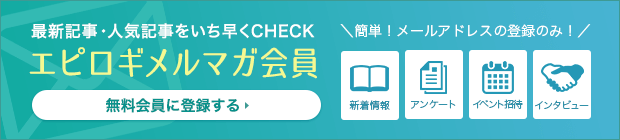大塚篤司氏に聞く「バーンアウトしない・させない」医師の働き方
かつてバーンアウトを経験した病棟医長の考える、医師を“楽しむ”ために必要なこと
大塚 篤司 氏(皮膚科医/京都大学医学部特定准教授・病棟医長)
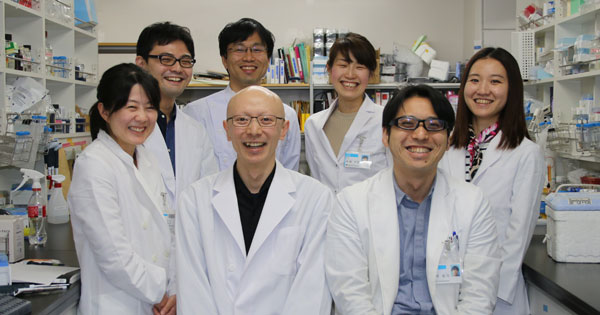
「医師の働き方改革」が叫ばれて久しい。長時間労働に当直・オンコールの負担、確保できない睡眠時間や休日――。従来のシステムが制度疲労を起こす中、社会に不可欠な医師という職業を、どうすれば持続可能な形で次世代に残していけるのか。
このような状況下で、患者のために「最善を尽くす」ことと、過重労働に陥らず「心身を健康に保つ」ことの両立に頭を悩ませる医師も多いだろう。著書『心にしみる皮膚の話』(朝日新聞出版)でその重要性を指摘した、京都大学大学院医学研究科・医学部特定准教授で皮膚科専門医の大塚篤司氏もその一人だ。
大塚氏は同書で過去のバーンアウトの経験を公表。現在は同大学医学部附属病院皮膚科学講座の病棟医長として、所属医師のマネジメントにも取り組む。「現場の中堅医師」視点でのベストエフォートな働き方について、大塚氏を取材。この難題と向き合うためのヒントを共に考えた。
医師には「自分を犠牲にする」素地があった
―― 医師がバーンアウトしてしまうとき、そこにはどんな理由があるのでしょうか。
僕は今年44歳で、2003年卒です。一般論として、僕くらいの世代の医師は「自分で自分を追い込むような働き方」をしていたのだと思います。そして、それを耐え抜いた医師だけが今も現場にいて、生存者バイアスのかかった状態にある。このことには自覚的でないといけません。
その働き方というのは、土日も担当患者さんを診る。年間で休みの日はほとんどなくて、毎日、病院に出勤するのは当たり前。患者さんのご家族への説明も、土日や平日夜の遅い時間であっても、望まれればそのご都合に沿う。生活のすべてを犠牲にして医師として働くことが普通であり、多くの医師の共通認識だったのではないでしょうか。
ちなみに、僕の一つ下の世代から、スーパーローテートが始まりました。逆に言うと、僕たちはほとんど全員が卒業と共に直接、医局に入った最後の世代ということになります。この世代までは、医師としてのキャリアを考える上で、そもそも選択肢が限られていたんです。
一つは入局して、そのまま大学のスタッフとしてアカデミアに残る道。臨床だけでなく、研究もしたり教育もしたり。もう一つ、入局後に関連病院に出て、そこでスタッフをしながらゆくゆくは部長に……といった道。最後の一つは開業です。自力で、あるいは親の病院を引き継いで。
当時はほとんどの医師が入局していましたし、選択肢が少ないということは、要するに逃げ道がないんですよね。だから、「みんなやってるから」「ずっとこうだったから」と、「自分を犠牲にすること」がある種、正当化されてしまう素地があったんだと思います。だから、ギリギリ限界まで働いて、バーンアウトしてしまう。
「中堅どころの先生が過労死で亡くなった」という話は、僕らの世代の医師であれば、どこの病院でも聞いたことがあると思います。だからといって「医者を辞めた」という人もほとんどいない。みんなそれでも限られた選択肢の中で働いていた。過去にはそうした状況があったんです。

取材はZoomで実施しました
―― では、スーパーローテート以降は変化が生じた?
あくまで僕の観測範囲でのことですが、世代間でのギャップが生じているように感じます。というのも、今の若手の医師は「まあ、合わなかったら、辞めればいいかな」と思うこともできるんです。
このことにより、僕らの世代が感じていた逃げ道のなさゆえのストレスは軽減されている。今は大学の医局に入らずに市中病院のスタッフになったり、フリーランスとして働いたりする道もある。または、大学の医局に入るけれども、ずっといる気は最初からない、とか。こういった選択肢が増えるのはとても健全なことです。
一方で、大学の医局という組織の後ろ盾がなくなれば、自己責任でキャリアを形成しなければならないことにもなります。僕たちや上の世代が感じていたのとはまた違ったストレスを感じていらっしゃる若手の医師も多いでしょう。
とはいえスーパーローテート前後できっぱりと分かれるわけでもなく、このような傾向は徐々に広がっていったものですし、若手の医師にも僕らと同じように考えるタイプはもちろんいるのですが。
「まだ下に任せるのは心配」のワナ
―― 大塚先生がバーンアウトされたことには、振り返ってどんな背景がありましたか?
世代も違いますし、僕がバーンアウトした経験を紹介しても、人によっては参考にならないかもしれないのですが……。僕と共通点がある場合は注意してほしいので、説明しますね。僕はもともと仕事においてスピードや合理性を重視するタイプで、成果主義。それゆえに、一人で仕事を抱え込みがちだったんです。
分かりやすいのが、いわゆる「自分でやった方が早い」という発想。これは僕らの世代、40代中盤の医師に多い印象です。「まだ下の医師に任せるのは心配だし、このくらいなら自分でやってしまおう」。これは時に危険な考え方です。
というのも、医師の仕事というのは年齢と共に増えていくものです。それは具体的にはマネジメントや会議、承認作業や意思決定などですが、こうした「増えたタスク」をこなしながら、医師としてのタスクも増やしてしまえば、どんどん仕事があふれ返って、いずれパンクするのは明らかです。
加えて、学会の準備や、患者さんの状態、それがどのくらい重なるかによって、仕事量が一気に手に負えないレベルまで増えてしまうこともある。そんなとき、ずっと頑張れてきたのに、ある瞬間にフッと「頑張れなく」なってしまうんですよ。
振り返ると、僕の場合は医学部の受験勉強くらいからストイックに自分を追い込んできました。ノルマを自分で決めて、それを必ず消化する。この傾向は医師になっても変わりませんでした。
でも、臨床でも研究でも、ゴールがなかなか見えないというか。こちらが努力したとしても患者さんが良くなるとは限らないし、新しい医学的発見なんて簡単にはできません。出口がないのに自分を追い込んで追い込んで、限界に達したとき、まさに疲労骨折みたいに心がポッキリと折れてしまった。
一番ひどい時期は、もちろん希死念慮もあったのですが、学会の抄録が送られてきたり、本屋の医学書のコーナーに行ったりしただけで、具合が悪くなってしまいました。仕事に関連するものが目に触れると、本当に体調がおかしくなるんです。

―― 現在は快復されていますが、ご自身の「タイプ」ゆえの働き方のリスクに対して、どのように対策していますか?
もともと僕、メールの返事がすごく早いんです。届いた瞬間に返すような性格で。でも実は今、あえて返信までのスパンをやや遅くしています。すぐに返すと「あれはどう」「これはどう」とかえって問い合わせが増えることもあるのですが、ワンテンポ置くことにより、それを防げるんですよ。
心って意外と柔軟じゃなくて、金属みたいなものだと僕は思っていて。折れてしまうと、くっつけてもしなりのある曲がり方はしないというか。なので、一度折れたあとは頑張り方を変えたり、違う工夫をしたりしないといけなくなる。ヘタをすると、今でも頑張りすぎてしまいますから。
例えば僕はよくビジネス書を読んでいたのですが、そこに書かれがちなこととして「人が休んでいる間に働け」というのがあるんですね。それを真に受けて自分に言い聞かせていると、土日にちゃんと休めなくなるんです。自分への呪いみたいなもので、何もしないことを罪だと感じてしまう。
でも医療って、手を抜くってことが許されない分野ですよね。すると、責任感の強い人ほど休めなくなってしまう。だからこそ、マインドの切り替えも重要です。例えば、後輩の医師に振れる仕事は振ったらいいんです。もちろん事故がないようにしっかりサポートしながら、ですが。
本来はそうやって権限やタスクを委譲して、自分の負担を軽くしながら、そのスペースに新しく自分がやるべき仕事を詰め込んでいくべきなんです。それを「サボっている」ように感じてしまうと苦しい。この場合は、後進の育成も立派な自分の仕事であるという意識を持つことが解決方法になるでしょう。
なぜ多くの医師が「休めない」のか?
―― 話を伺っていると、医師という職業の特殊性による問題も多く、「本当に働き方を改革できるのか」と思ってしまいます。
一つ言えるのは、若手の医師が自分だけの力で持続可能な働き方を実現するのは難しい、ということです。それを整備するのは僕らの世代以上の医師の仕事であって、実際には担当患者さんが誰になるかということ一つを取っても、最前線で働く若手の医師にはコントロールできないことが多すぎます。
しかし、何らかのアクションはすぐにでも取らなければいけません。このままでは若手の医師は働きすぎて潰れてしまうか、逆にすごく手を抜いて周りの人に迷惑をかけながら働くか、という究極の二択になりかねない。
一方で、中堅の医師が下の世代のことを考えようとしても、中堅は中堅で忙しくて余裕がないこともある。ジレンマですが、現場経験があり、運営システムに決定権のあるマネージャーとしては、やれることを一つひとつやるしかない、とも思っています。
小さいところで言うと、有給の取得ですね。僕のときは正直「医者が有給なんて」という雰囲気がありました。平日に休むとは何事か、休むのは親族の不幸か自分の結婚式かそれくらい、といった暗黙の了解です。
でも、本当に言うまでもないことですが、医師も休まないと働けないので。「医療の常識」ではなく、「今の社会の常識」に合わせて休むことも大事です。僕らの世代は休めなかったけれども、だからといって下の世代に対して休めない雰囲気を作るんじゃなくて、むしろ「休め」と言っていかなければいけない。
ただし、「休め」と言えない事情がある病院や診療科も多いんです。「じゃあ誰が代わりに外来やるの」「オペやるの」という話になってしまうので。そこはもう、システムで何とかしないと変えられないところになりますね。
医師の働き方の問題の根本には、医師の人手不足とタスク過多があります。対策としては医師の採用や、それが現実的でなければ医療事務の方々への権限移譲などがあり得るでしょう。でも、これはその体制を構築する余裕がない、本当にギリギリで回している病院には難しいことです。
他にも例えば、医療情報の取り扱いには細心の注意を払わないといけませんが、将来的には診療や患者さんのご家族とお話をするときにWeb会議システムを導入すれば、せめて移動時間を減らすことができるかもしれない。ただし、これもすぐにというわけにはいかないでしょう。
僕は皮膚科という比較的、急変が少ない科なので、他の科より休む機会は増えます。それでも、専門が悪性腫瘍ということもあり、状態がシビアな患者さんも多く、状態が悪いときは休めない。それが続くと大変で、やっぱりみんな「休んじゃいけない」という雰囲気ができてしまう。

欧州アジア臨床腫瘍学会で行った研究発表時の様子。医師の仕事は、診療に加え、学会発表や委員会などの会議、書類仕事まで多岐に渡る。
だからこそ、僕がちょっと気をつけているのは、休むときは(チームメンバーに対して)堂々と休むこと。自分のためでもあるんですけど、若い人たちのためにもなる。わざとそうしています。
一方で、じゃあ患者さんに対してはどうするべきかというと、これも頭の痛い問題です。仮に僕が重い病気を抱えて入院しているとして、自分の担当医が「来週は有給を使って旅行に行きます」と言い出したら、「えっ」と思うでしょう。
これはもう本当に状況次第なんです。担当患者さんと信頼関係を構築できていて、その患者さんの状態が落ち着いていて、そのうえ特に予定されているイベントもないのであれば、「〇〇さんの状態も落ち着いていますし、来週はちょっと休ませてもらいますね」と伝えることもできるかもしれません。
医師の持続可能な働き方を実現したいなら、たまには休みを取らないと潰れてしまう人も出る。そうすると他のスタッフがカバーに回り、結局みんな苦しくなる。医療の質の低下にもつながって、患者さんにも迷惑がかかる。だから医師は休まなければならない。そんな社会的な合意形成が徐々に進んでいけばいいと思います。
「黄色信号」で助けを求めてほしい
―― 医師が働きすぎてしまう理由がたくさんある現在の医療システムの中で、それでも肉体的・精神的に健やかでいるためには、どうすればいいのでしょうか。
明確な正解があれば、バーンアウトしていなかったと思うのですが(苦笑)、僕の場合は自分自身の「働きすぎ」に気づくため、二つのポイントを気にするようにしています。一つは「髪の毛を切っていない」ことで、もう一つが「靴が磨かれていない」ことです。
忙しくなると、美容室を予約する心の余裕がなくなるんですよね。実際に足を運ぶ時間も取れないし、日程を決める余裕も失う。あとは、講演や出張に行ったときにふと革靴を見ると、汚れて底が減ってしまっていることがある。身だしなみに気をつけられなくなったときに、働きすぎを自覚するんです。
できるだけこんなふうに、「やばい」と思えるシグナルを見つけておくといいかもしれません。人によっては「一年以上、服を買いに行けていない」ことかもしれませんし、映画が好きな人が映画を観ようと思わなくなることかもしれない。
ポイントは「自分でないと気づけない」ことだと思います。忙しいときほど、例えば家族に「働きすぎじゃない?」と言われても、反発してしまうことがあるんじゃないでしょうか。あるいは家族や周囲の人も医療関係者だと、医師の仕事環境を知っていて、激務であることに慣れてしまっているかもしれないので。
とはいえ、僕がこうやって自分のシグナルを自覚できるようになったのは30代後半で、仕事をする上である程度、権限を持たされて、余裕が出てきてからです。一度、潰れてしまった経験も生きている。逆に言うと、若手だった頃は毎日が必死で、自分自身で健康管理せよというのはなかなか酷な話でもあるのですが。
自分の経験も踏まえて思うのは、「赤信号」になってからではもう遅いということ。だからマネージャーとしては、危うい後輩医師がいれば、できるだけ黄色のうちに声を掛けるようにしています。
先にお話ししたように、周囲は気づきにくいのも事実。だからこそ、若手の医師には少なくとも赤信号になる前にSOSを出してほしい。「やばい」と思ったら「やばいです」と言うようにしてください。
―― では、助けを求めるべき「黄色信号」は具体的にどのような状態ですか?
一日の終わりに「やりきった」「頑張った」と感じたとしたら、それはすでにオーバーワークの可能性があります。なかなか疲れが取れない日が続いたり、仕事終わりに「もっと頑張れたのに」と思ったりするのは、働きすぎの兆候。
後から振り返って「いいテンポでこの一カ月走っているな」と思えるのが、持続可能な働き方なんですよ。
心地よくコンスタントに走り続けることがポイントになります。もしかしたら「走る」というのも良くない表現かもしれません。歩きでもいいから、前に進むことですね。
この例えで言うと「昨日走った、今日休んだ」は持続可能ではありません。「このペースで明日も、来月も走り続けるのは無理だ」と感じる状態も同様です。それがしばらく続いてしまうようなら、黄色信号でしょう。
もちろん、どれだけハードワークをしても体力も気力も尽きない超人のような人もいますし、特に若い頃はそのような人に憧れるものです。でも、医師として20年近く働いて思うのは、そんな超人はひと握りだということ。また、超人になることや超人の存在を前提としたシステムは、そもそも持続可能ではありませんから。

メラノーマユニット専門外来にて。治験患者に対して、チーム(腫瘍内科医、治験コーディネーター)で診察を行う。大塚氏がユニット長を務める同ユニットでは、皮膚科医、腫瘍内科医、病理診断医などが連携し、患者の治療方針を検討・提供している。
―― 大塚先生はハッシュタグ #SNS医療のカタチ を主宰し、SNSで医療と患者をつなぐような発信も積極的におこなっています。仕事量は増えてしまうと思うのですが、なぜこのような活動をされているのでしょうか。
先ほど、社会的な合意形成という話も出ましたが、医師と患者の接点を増やすことで相互理解が深まるのではないか、と期待しています。医師と患者の良好な関係は、必ず医療の質を高めてくれる。そのためには病院に来る前の情報提供、そして来た後のフォローアップも大事で、そこでSNSが活躍します。
近年はオフラインでのイベントも多数、開催しました。ネットにとどまらないこのような活動により仲間も得られて、サードプレイスというか、病院の外に自分の居場所を作ることにもなっているのかな、と。その意味で、個人としても救われています。
カバーしあってチームの「ストレスの総量」を下げる
―― 大塚先生の目から見て、この20年で医師の働き方はどのように変わってきていますか?
現実として、今の方が大変になっていると感じます。かつて、医師の患者さんへの接し方がパターナリスティックだった時代、医師は病院で白衣を着て座っていれば、患者さんたちは医師の言うことを聞くしかありませんでした。しかし当然、今はそんな態度は許されません。
医学の進歩は目覚ましく、最近では「医学知識は40日で2倍になる」なんて言われたりします。それだけ、新しく身につけるべきことは増えている。それだけでなく、医師患者関係の変化により、訴訟リスクを抑えて自分たちの身を守るための仕事、つまり書類作成や説明に必要な時間も増えています。
今の若手の医師は本当に苦労していると思いますよ。だからこそ僕らの世代が、後輩たちに「医師をしていて楽しいな」と思える環境を提供しなければならない。医師として働く上で、僕のモットーは「仕事は楽しく」です。これは自分だけではなく、一緒に働くみんながそう思えることが目標。
そこで、楽しく働くにはどうしたらいいかをいつも考えています。その一つが、「チームとしてストレスの総量を下げること」です。
医師の仕事とひと口に言っても、いろいろありますよね。手術をするのも、外来でたくさんの患者さんを診察することも、コミュニケーションが難しい患者さんと必要なコミュニケーションを図って治療につなげていくのも、医師の仕事じゃないですか。でも、それぞれ性質は全く異なるわけです。そうすると、医師によって得意不得意も発生します。
手術は得意だけれど、患者さんをたくさん診察するのは得意じゃないとか、外来は得意なんだけど、コミュニケーションが難しい患者さんとじっくり向き合うのは苦手とか。得手不得手はどうしてもあるので、そこはマネージャーが上手に得意なところに得意な人をつけてあげればいい。
苦手な人をわざわざ苦手なところにつけて、ストレスを感じさせるのって、ムダじゃないですか。例えば難しい患者さんとのコミュニケーションは、僕は他の医師よりストレスなくできる。その場合は僕が出ていったほうがチームとしてのストレスが少なくなって、みんなが楽しく働けますよね。
まあ、いつもそんなに思い通りにはいきませんし、苦手でも逃げてはいけないこともあるのですが、カバーできるところはカバーし合う、という発想は必要でしょう。人を相手にする仕事ですから、ストレスは少なからずあります。マネジメントはそのことを常に念頭に置いておこなわなければなりません。
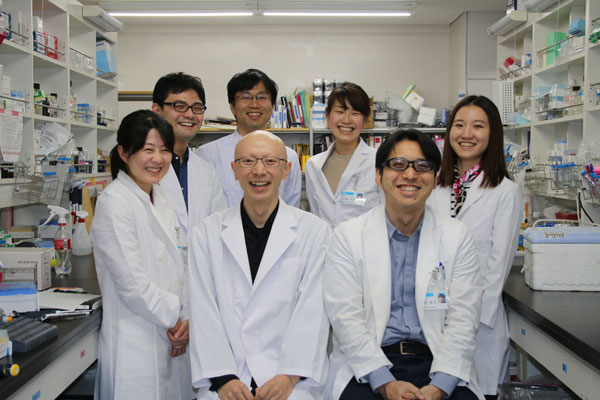
大塚氏の研究グループのメンバーと。グループには、現在、医員や研究員、院生など6人の医師が所属している。
逆に言えば、チームメンバーが何にストレスを感じているか分からないと、マネジメントできないとも言えます。こちらが中堅になると困るのが、若手の医師が本音を話してくれなくなること。未だに年功序列の傾向が強いので、僕から何かを頼むと、皆かしこまって「頑張ります」と返事してしまうんですよね。
だから、若手の「苦手」を観察するときは、自分じゃなくて他の人と話しているところをチェックしています。同期や少し上の先輩医師とのコミュニケーションを見ると、人となりが分かるので。こういうことを言うと、若手の医師からはすごく嫌がられるのですが(笑)。
医師を「楽しむ」ために必要なこと
―― 現場の医師からは「持続可能な働き方」を実現するためのキャリア形成に悩む声も多く聞かれます。
結局、オーソドックスな方法ではありますが、まずはそれぞれの道の先で頑張っている先輩医師たちの話を聞くのがいいのではないか、と思います。この時代にあえて大学の医局に入った人、流れに乗っていきなり市中病院のスタッフになった人、フリーランスに挑戦している人……というようにです。
できればその道の良かった点だけでなく、悪かった点も質問しましょう。働きやすさは、休みの取りやすさと、やりがいや責任とのバランスで決まります。後者も重要で、楽しいだけでも続きません。医師は、ただ生活費を稼ぐためにやるにはちょっと大変な仕事ですから。
やや矛盾するようですが、最近は自分のQOLが最優先になっている医師の姿を見かけるようになりました。もちろん、体やメンタルを壊してまで働く必要はありませんが、「いかに省エネで医師として働くか」ばかりを追究するようになってしまうと、それで本当にこの仕事を楽しめているのだろうか、と考え込んでしまいます。
若手の医師に覚えておいてほしいのは、年齢と共に気力は確実に落ちるということ。「20代はそこそこやって40代で頑張ろう」という人生設計は、こと医師においてはあり得ません。医師の仕事を楽しむには知識と技術が必要なので、若いうちに身につけるべきことは身につけておいてほしいですね。
だからこそ、僕らの世代には「若手が精一杯頑張りながらも、体調やメンタルを犠牲にしない」ような環境を整備する責任があります。
僕もそうですが、40代はいろいろと悩む時期なんですよ。バリバリやって突き抜ける人も、半分ドロップアウトしてしまった人も、その中間くらいの人もいますよね。そして、ある意味でそれら全部が「正解」なんです。僕らの背中を見て、後輩の医師たちは自分にあったロールモデルを探すのですから。

僕は「医師はこうあるべきだ」「仕事ができる人はこうだ」という刷り込みを自分にした結果、潰れてしまった経緯があるので、ロールモデルの選択肢は多いに越したことはないと思っています。絶対にしてはいけないのは、若手に自分のやり方を押し付けること。そして、やってほしいのが、楽しそうに働くことです。
僕らくらいの年齢まで医師をしてきてしまうと、「今さら変われない」というところも正直、あるでしょう。しかし、医療の発展のために必要なのは、下の世代が医師という仕事を楽しみ、続けて、さらに下の世代の医師を育てること。そのためには僕らがそれぞれのやり方で、楽しそうに働いているのが一番なんじゃないでしょうか。
(聞き手・文=朽木誠一郎+ノオト)
【関連記事】
・「米国・ハワイ大学での内科レジデンシーの現場から【後編】|アメリカの医師の働き方に触れて~全ての医師がハッピーに働ける現場を作る」浜畑菜摘氏
・「医師が医療に殺されないために【前編】|勤務医が“自分自身”のために行うべきメンタルケア」鈴木裕介氏(医師/ハイズ株式会社 事業戦略部長)
・「医師のためのタイムマネジメント術」岩田健太郎氏(神戸大学大学院医学研究科・微生物感染症学講座感染治療学分野教授)
・「時間外労働100時間の産婦人科で、残業時間の半減を実現!~明日から実践できる10の取り組み」柴田綾子氏(産婦人科医/淀川キリスト教病院 産婦人科 副医長)
・「上限規制1,860時間 ~「医師の働き方改革に関する検討会」報告書を読み解く」

- 大塚 篤司(おおつか・あつし)
- 1976年生まれ。京都大学医学部特定准教授(病棟医長)、日本アレルギー学会代議員。2003年信州大学医学部卒業後、京都大学大学院、チューリッヒ大学病院客員研究員を経て、2017年より現職。医学博士。皮膚科専門医。がん治療認定医 。アレルギー薬剤開発研究にも携わり、複数の特許を持ち、アトピー性皮膚炎に関連する講演は年間40以上こなす。著書に『本当に良い医者と病院の見抜き方、教えます。 “患者の気持ちがわからない”お医者さんに当たらないために』(大和出版)、『世界最高のエビデンスでやさしく伝える 最新医学で一番正しいアトピーの治し方』(ダイヤモンド社)、『「この中にお医者さんいますか?」に皮膚科医が…… 心にしみる皮膚の話』(朝日新聞出版)。