西洋医学も伝統医療も、「効くもの」は受け容れる
探検家として医師として、その目に映る人間の豊かさとは
関野 吉晴 氏(探検家/医師)

関野吉晴さんといえば、アフリカに誕生した人類が、ユーラシア大陸を通ってアメリカ大陸にまで拡散していった行程を、自らの力だけを頼りに遡行した旅「グレートジャーニー」で知られています。そんな関野さんは学生時代、南米への旅を重ねる中で、現地での医療の必要性を感じて医師免許を取得し、訪ねた土地の人々の治療に当たってきました。探検家として、医師として、旅を通じて感じた医療への思いについて、お話を伺いました。
探検家として一番印象的な出会いが、初めての旅であった
――まず、探検家としての原点からお聞かせください。一橋大学で探検部を創設し、探検家としての人生を始めたと伺っていますが、探検に出たいと思うようになったのはいつ頃のことですか。
高校生くらいの頃って、誰かの話や読んだ本に影響を受けて、自分の将来を決めることが多いですよね。でも、僕にはそういうものがなかったから、文化も自然も日本とはまったく違うところに自分を放り込めば、違う自分が見えたり、いろんな人と出会って化学反応が起こるんじゃないかと考えていたんです。
一橋大学の法学部に入ったのは、高校が進学校で、兄弟もみんな進学していたし、大学に行くのが当たり前だと思っていたから。入学してすぐ探検部をつくって、山登りや川下りのトレーニングを始めました。先輩がいないから社会人の山岳会に入ったり、ほかの大学の探検部に「どんなことやってるの?」と聞いたりしてね。
――初めてアマゾンへ渡ったのも在学中でしたよね。そもそもアマゾンを選んだ理由は?
本当はどこでもよかったんです。ただ、関東で一番活動が盛んだった早稲田大学の探検部が世界最長のナイル川を下っていたから、「じゃあ世界で一番デカい川をやろう」と、1971年、3年生の時に1年間休学してアマゾンに行きました。
探検部の3人で、ある川をボートで400kmほど下った時、「同じ川をみんなで下っても面白くないから、別々の川に分かれて河口で落ち合おう」という話になり、僕は河口から一番遠いところ、最長源流と言って、氷河の一滴から始まり6300km続く川を下ることにしました。そこで、今までの旅の中で一番印象的な出会いがあったんです。

ある日、テントを張ろうとしていたら、素っ裸で水浴びしている子どもたちを見つけたんですね。そこで、片言のスペイン語やボディランゲージで「君たちの村に泊めてくれない?」とお願いすると、しょうがないなって感じで連れて行ってくれた。村に着いたのは夕方の4時くらい。乾季だから川の近くに降りてきたんでしょう。4本の柱と屋根だけの簡易的な家の一軒を僕に与えてくれて、ゴザまで敷いてくれました。
ところが、誰も近寄ってこないんですよ。女の人に「お世話になるから」と、日本から持ってきた鏡や櫛をプレゼントしようとしても拒否される。そのうち、男たちも帰ってきたけれど、僕のところには誰も来ない。興味がないのかといったらみんな興味津々で僕を見ている。でも、目が合うと逸らすんです。
だんだんあたりも暗くなってきてね。それまで一人で山に入っても川を下っていても、寂しさを感じたことは一度もなかったのに、その時はどういうわけか寂しいと思いました。人がいっぱいいる中で孤立した時、人は寂しさを感じるんだなって……。それで、寂しさを紛らわすために歌を歌い始めたんです。
といっても僕は音痴だし、レパートリーが少ないから、「故郷」とか「赤とんぼ」とか知っている童謡を片っ端から歌いました。すると、子どもたちが僕の目の前で正座をして、一緒に歌い始めたんです。自分たちの歌を聴かせたいんだなと思ったけれど、よくよく聴くと、僕の歌を真似している。で、子どもたちの背後では、さっきまで険しい顔をしていた大人たちが、とてもゆるい表情で僕らの歌を聞いていたんです。夕方、プレゼントを断ったおばあちゃんが、彼らにとってはごちそうの、タニシを少し大きくしたような貝まで差し入れてくれて。
すごくうれしかったですね。モノをあげることで彼らとつながっても、それきりの関係でしかない。けれど、歌や音楽という普遍的なもので距離が近づいたことが、すごく心地よかった。
そういう旅を1年間続けていたら、時間さえかければ僕は誰とでも仲良くなれるという自信が生まれました。相手の気を引くために何かやるんじゃなくて、「祭りがあるからお前も踊れよ」とか「お前も酒飲むか?」とか、何かきっかけがあれば、近づいていくことができるんだなって。

1977年 ペルー、アマゾン川流域で焼き畑と狩猟採集の暮らしを営む先住民のマチゲンガ族の人々と。40年来の付き合いになる一家もいる。
医者になれば少しは役に立つかもしれない
――それほど探検に魅せられていた関野さんは、どうして医者になろうと思ったんですか。
大学に入って6年経った頃ですね。そろそろ大学を出たほうがいいかな、でも探検は続けたいなと思っていて、ジャーナリスト、研究者、写真家とか選択肢はいろいろあったけれど、アマゾンで知り合った人とは取材や調査の対象ではなく、友達として付き合っていきたかった。じゃあ何をすればいいだろうかと考えた時、医者になれば少しは役に立つかもしれないと思ったんです。
それまでは「何でもしますから泊めてください」とお願いしても、何もできなくて足手まといになることが多かった。でも、医者になれば診療や自分の健康管理もできるし、人間の心と身体にも興味がありました。そこで、当時は法学部から社会学部に編入していたんだけど、最後の1年を半年で辞めて、医学部の受験勉強を始めました。
――法学部、社会学部から医学部を目指すというのも、思い切った決断だと思います。
そういう発想ができたのは、先生にも恵まれていたからだと思います。大学2年の時、今でもお世話になっているゼミの教官から「法学部に入ったからといって法律をやることはないよ」と言われたことがあるんです。医学や工学は違うけれど、人文社会学系、特に社会学は社会に出てから始めたほうがいい。じゃあ学生時代に何をやるかといったら、本を読んで、自分のものの見方、考え方をしっかりさせろって。
その教官のゼミは、3年生になるとゼミ生が2人しかいなくて、僕はアマゾン、もう一人はインドのことをやりたいと言ってね(笑)。でも、「わかった。ただ、真剣にやれ。僕も一緒に勉強するから」と、教官は僕らに付き合ってくれたんです。
――一橋大学を卒業後、関野さんは横浜市立大学の医学部に入学されます。医学部生時代、探検を続けることはできたんですか。
友達には「医学部に入ったら探検に行けないよ」と言われていたけれど、春休みと夏休みがきちんと2カ月ずつあったから、行ってましたね。ただ、南米に行く前に試験があって、帰ってきてもすぐ試験でしょう。帰国の日が近づくと、みんなが寝たあと、テントの中でろうそくを灯して勉強していました。結局、再試ばかりだったけどね(笑)。
当時の医学部は60人しか学生がいなくて、そのうちの20人くらいが大卒か中退者。結束が固かったから、「これだけは覚えておけ」とか「ここがヤマだ」と、よく助けてもらいました。
医学部を出てから3、4年は、アマゾンと日本を行き来していたんですが、国家試験に受かっただけでは何も役に立たないですよね。子どもを診られる外科医か、小外科手術ができる小児科医になろうと思い立って、武蔵野赤十字病院で研修医として働き始めたんです。
医者が面白くて、「アマゾンはしばらくいいかな……」
――なぜ、武蔵野赤十字病院だったのでしょうか。
当時、あの病院はプログラムを好きに選べたんです。外科は半年、麻酔科、小児科は半年というふうに。産婦人科もやって、子どもも10人くらい取り上げたかな。探検先で診療する上で必要となることはすべて学びたかったから、とても魅力的な環境だったし、「アマゾンはしばらくいいかな……」と思えるほど、勤務医は勤務医で面白かったです。
3人チームで10人くらいの患者さんを担当していると、いろんな患者さんと出会うし、胃がんといっても合併症の有無、ステージの違いで対応が変わりますよね。どんな治療法が最適なのか、必死になって勉強していたら、メキメキと自分が成長していくのがわかるんです。
でも、やっぱりね、1年半くらい経った頃にNHKから「ギアナ高地に行かないか?」という話があって。初めは「行けない」と返したけれど、外科部長に相談したら「そりゃ行って来なさい」と、送り出してくれたんです。病院に入る時、ここにずっといるわけではない、僕は探検家になりたいんですと伝えていたから、理解してくれていたんでしょうね。

――武蔵野赤十字病院の後、多摩川総合病院にも勤務されますよね。
「グレートジャーニー」の旅を始める前ですね。武蔵野日赤を辞めて、再び南米通いをしていた頃、僕らとそっくりな顔をしたアンデスやアマゾンの人々の先祖は「いつ、どこから、どのようにしてやって来たのだろうか」という問いと、しっかり向き合う旅をしようと思ったんです。ゴーギャンの「我々はどこから来たのか。我々は何者なのか。我々はどこへ行くのか」じゃないけれど、人類にとって普遍的なテーマを、自分の足で這いずりまわり、自分の目で見て、自分の耳で聞き、自分の頭で考えようと。その旅の前に、医者としての修行をもう一度しておこうと決心して、多摩川総合病院に3年間勤務しました。
「西洋医学か、伝統医療か」の二択ではない
――「グレートジャーニー」の旅の模様を追ったTV番組では、訪ねた土地の人々を診療する関野さんの姿が映されています。日本で勤務医として患者さんに接していた時と、いわゆる現代文明と接触が少ない地域で生活する人を診療する時とでは、どんな違いがありましたか。
常に付きまとっていたのは、「文化を壊してしまうのではないか」という不安でした。例えば、ベネズエラのヤノマミ(アマゾン流域で1万年以上、独自の文化・風習を守り続けている部族)の村に行くと、シャーマン(呪術・宗教的職能者)が力を持っています。シャーマンに嫌われたら病気を治してもらえないから村人は彼らを立てるし、僕は僕で、自分の治療のほうが効果があったらどうしようかと心配でした。
その頃、村ではマラリアが流行っていて、彼らの世界観では、マラリアに罹った人は「悪霊が取り憑いた人」なんです。だから、シャーマンが祈祷するんだけど、医学的に考えれば、マラリアの典型例は潜伏期間の後、悪寒や震えとともに熱発作で発症して、四日熱なら72時間ごと、三日熱なら48時間ごとに熱発作が起きますよね。つまり、何時間も祈祷を続けていたら、一時的に症状が軽くなるタイミングがある。でも、村人はそれを見て「さすがはシャーマン」となるわけです。
――伝統的な医療が絶対視されているわけですか。
そんな単純な話ではなくて、彼らからすれば「西洋医学か、伝統医療か」の二択ではないということです。実際、その村で僕が診療を始めると、最初に来た患者がシャーマンでした。「頭が痛い……」って、明らかに幻覚剤の吸いすぎでね(笑)。
ボリビアのアマレテという村も印象的でした。『ナショナル・ジオグラフィック』で特集が組まれたこともある「薬草の谷」と言われる村で、カリャワヤと呼ばれる伝統医がいる。300もの薬草の知識があって、リャマの胎児を埋めるような呪術的なこともするんだけど、街で往診もするし、ペルーからも患者が来るくらい有名なんです。
そのアマレテにはフランスのNGOが建てた診療所があって、ここが優れた仕組みなんですよ。患者が来たらカリャワヤとフランス人の西洋医が「どっちで診ようか?」と相談して、「あなたは伝統医、あなたは西洋医」というふうに分けて、「一緒に診ましょう」というケースもある。つまり、「西洋医学か、伝統医療か」ではなく、どっちも診ればダブルで効くじゃないかという、とても現実的な考え方なんです。
これって日本人と似ていると思いませんか。「腰が痛い」といったら整形外科に行くけれど、慢性疾患には対症療法か手術しかない。じゃあどうするか。「鍼灸に行くか」となるわけです。それも効かなくなったら「整体に行くか」「カイロプラクティックに行くか」となって、最終的には「拝んでもらおう」となるでしょう(笑)。伝統的な医療が受け継がれている土地に西洋医学が入っていくことで、その土地の文化を壊してしまうと思っていたけれど、そんな例は少なかったですね。
医師がいなくてもできる医療を
――現地では、どのように診療しているのでしょう。例えば、常に医療機器を持ち運んでいたんですか。
移動型の旅では持っていかないけれど、その土地に生きている人たちと一緒に長く寝泊まりするような定住型の旅では持ち歩いていました。
青空診療所もよく開きますよ。ネパールの4000mの高地にあるチベット人の村では、村の一番高いところにテントを張って診療所にしました。その時は往診もして、「お腹が痛い」と言われてもなるべく薬は渡さずに、「生水はあまり飲まないでね」と話したり、どうしても下痢が止まらない場合は、整腸剤くらいはあげていたかな。

1998年 ロシア・インチョウンにて
やっぱり、そうした土地で診療していると感じるのが、僕がいなくてもできる医療の必要性なんですね。そういう意味で、最近はモルフォセラピーという医療法を実践しています。
これは、本来あるべき位置からズレている骨を手技によって正しい位置に戻すというもので、骨のズレが神経や血管を圧迫して頭痛や腰痛などの不快症状を起こしているという考え方に基づいている。もちろん技術は必要だけれど、医療器具や薬はいりません。どこに行っても腰痛や肩こりは多いから、例えば村の村長とか学校の先生にきちんと教えることができれば役に立つんじゃないかって。
「ありがとう」の存在しない究極の平等社会
もともと僕は採集狩猟民に興味があって旅を続けてきたけれど、彼らの何に自分が引きつけられているのかといったら、「平等社会」なんですね。男女の分業はあるけれど、「お前は弓矢だけ作っていればいい」「お前は畑だけやっていればいい」ということが起こらない。逆を言えば、肉や魚を採っても、焼き畑でイモやバナナをつくっても、腐ってしまうから蓄えることができない環境なんです。
蓄えないということは、人を囲い込むことができませんよね。余剰がなければ貯め込む人間がいないわけで、持つ者と持たざる者が生まれない平等な社会が成り立つ。モノは必要な人に渡っていくし、なおかつ「この土地はオレのもの」と言い出す人間もいません。
アフリカのエチオピア南西部から、ケニアのトゥルカナ湖に流れる全長760kmのオモ川の河原で生活する、ある部族の村に行ったことがあります。彼らは牛飼いをしている他の部族との争いに生き残れなかったような人たちで、彼らが暮らす河原にはツェツェバエという眠り病を媒介するハエがいる。牛にも病気を引き起こすから、牛飼いの部族の干渉を受けずに生活できているわけです。
河原に肥沃な土壌が生まれる乾季には稗の仲間の種を蒔いて農業をして、雨季の半年間は小動物や魚を採って、かろうじて暮らしているんだけど、彼らも蓄えられないから、完璧な平等社会なんですよ。
そこで面白かったのが、青空診療所を始めたらたくさんの村人が来たんだけど、誰一人としてまったく感謝がないというか、「ありがとう」という言葉すらないんです。南米では診療のお礼に鶏や羊を持ってこられたこともあったから不思議に思っていたけれど、考えてみれば、モノだけではなく技術や知恵も惜しみなく出すのが彼らの社会で、僕は普通のことをやっているだけだったんですね。だから、「オレの薬はどうした?」と威張る人もいたくらい(笑)。
何をもって「死」を決めるのか
――お話を伺っていると、世界には様々な価値観があるのだということを、改めて思い知らされます。
「死の概念」も様々ですからね。チベットではこんなこともありました。ある高僧の娘が僕を呼びに来たから家に行ってみると、高僧は横になれないほど痛がっていて、お腹がパンパンに膨らんでいる。黄疸が出ているし、聴診器を当てるまでもなく肺がゴボゴボいっているから、肝臓に腫瘍があって腹水が溜まり、肺にも腫瘍が転移しているとわかりました。
結局、2、3日後に亡くなったんですが、興味深かったのが、彼らがどうやって「死」を決めているかということ。西洋医学なら死の三徴候がありますよね。呼吸が止まって、心肺が停止して、瞳孔が固定し光を当てても縮瞳しなくなったら死と判断する。それで、お坊さんに尋ねてみたら「高僧は自分で死の瞬間がわかる」と言うんです。だから亡くなる前にみんなを集めて座禅の姿勢を取り、最後の言葉を述べる。誰かが脈をとったり呼吸の有無を確認したりせず、「彼が逝くと言ったらそれが死だ」と。

そういった死の概念がある一方で、近年、臓器移植ができるようになってから、脳死の問題が出てきていますよね。脳死は特別な医師しか判断できないわけだけど、僕は、脳死は死ではないと思っています。だって血が巡っているんだから。脳死と判断された人が妊娠していたら、赤ちゃんを生むこともできると言われているし、逆を言えば、臓器や血液、抗体の生産工場にもなり得るわけです。死体解剖の実習の検体も「脳死ならいいじゃないか」と言いかねない。
医者の役割って「重症患者をいかに長生きさせるか」ではないと思うんです。延命ばかりに焦点が当てられて、質の問題が考えられていないんですね。いかに健康寿命を延ばすかが、これからはもっと重要になってくるんじゃないかな。
僕らは今、物質的にはとても豊かな暮らしをしています。だけど、もっともっと蓄えたいという欲が大量生産、大量消費、大量廃棄につながり、文明の様々な負の側面を引き起こしていますよね。「こんな便利なものがありますよ」と商業主義は消費を煽るけれど、そこまでしなくてもいいんじゃないのというか、みんなもっと我慢すればいいのにって常々感じるんです。だからね、「本にサインしてくれ」と言われて、「座右の銘とかメッセージを書いてください」とお願いされたら、僕は「ほどほどに」って書くようにしているんです(笑)。
(聞き手・撮影=成田敏史)
【関連記事】
・「宇宙開発を支える医師の仕事 宇宙の時代の礎となる」三木猛生氏(JAXA)
・「ヒト・モノがない! 医療の原点が見える山岳診療所」荻原幸彦氏(東京医科大学上高地診療所 所長)
・「小説家として“等身大の医療”を伝える」久坂部羊氏(小説家/医師)
- 関野 吉晴(せきの・よしはる)
- 1949年東京都生まれ。探検家・外科医。
一橋大学在学中に探検部を創設し、1971年アマゾン全域踏査隊長としてアマゾン川全域を下る。その後25年間に32回、通算10年間以上にわたり、アマゾン川源流や中央アンデス、パタゴニア、アタカマ高地、ギアナ高地など、南米への旅を重ねる。その間、現地での医療の必要性を感じて、横浜市大医学部に入学。医師(外科)となって、武蔵野赤十字病院、多摩川総合病院などに勤務。その間も南米通いを続けた。
1993年からは、アフリカに誕生した人類がユーラシア大陸を通ってアメリカ大陸にまで拡散していった約5万3千キロの行程を、自らの脚力と腕力だけを頼りに遡行する旅「グレートジャーニー」を始める。南米最南端ナバリーノ島をカヤックで出発して以来、足かけ10年の歳月をかけて、2002年2月10日タンザニア・ラエトリにゴールした。2004年7月からは「新グレートジャーニー 日本列島にやって来た人々」をスタート。シベリアを経由して稚内までの「北方ルート」、ヒマラヤからインドシナを経由して朝鮮半島から対馬までの「南方ルート」を終え、インドネシア・スラウェシ島から石垣島まで手作りの丸木舟による4700キロの航海「海のルート」は2011年6月13日にゴールした。武蔵野美術大学教授(文化人類学)。




 公式SNS
公式SNS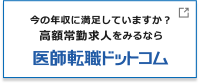
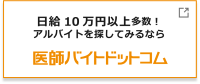


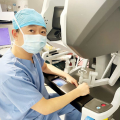












コメントを投稿する