医療がない場所で、医療を求める人のために全力を尽くす【後編】
救えなかった子どもたちのために、世界を変えることを諦めない
加藤 寛幸 氏(小児科医/国境なき医師団日本 会長)

紛争地域や感染症の流行地、難民キャンプで緊急の医療活動に従事する「国境なき医師団(Médecins Sans Frontières= MSF)」。その名前は多くの人が耳にしたことがあるはずだし、活動内容についてのおぼろげなイメージもあるかもしれない。けれども、その活動の実態は、あまり知られていない。納得のいく医療を施すのが難しい現場で、医師たちはどのような活動に取り組んでいるのか。目の前で苦しむ人を救うためにすべてを捧げる……。医師の原点ともいえる活動に打ち込む、加藤寛幸会長にその活動内容や今後の展望などを伺いました。
前編では派遣先での医師の仕事について、中編では、「国境なき医師団日本」の会長としての仕事について、人道援助活動への理解普及を目指した活動や、医師の確保、そして団員の日本でのキャリアについてお聞きしました。後編では、会長の仕事のもう一つの柱、「証言活動」についてお話を伺います。
“知られざる世界”の証言者として
「(中編でお話した)活動を正しく知ってもらう」ことと繋がりますが、もう一つ、会長として重要な仕事が、「証言活動」です。
国境なき医師団は、1971年にフランスの医師とジャーナリストのグループによって創設されました。その医師たちは元々、赤十字の医療援助活動に従事し、内戦中だったナイジェリアのビアフラに派遣されていました。現地の活動だけでは救いきれない命を救うためにはどうしたら良いか、を考えて出した結論が、現地の悲惨な状況を世界に伝えることだったのですが、赤十字には当時“沈黙の原則”があり、現地で見聞きしたことを口外してはならなかったのです。そこで新しい組織の立ち上げを決めました。悲惨な実態を世界に発信することで、世の中を動かし、命を救うことを目指したのです。こうして医療人道援助活動と証言活動を2つの柱とする国境なき医師団が1971年12月に誕生したのです。
だから、我々にとっては、苦しんでいる人たちの実態を世界に証言することは現地での活動と同様に大切な仕事です。私は対外的には国境なき医師団日本を代表する立場であり、我々が行っている活動を多くの人に知ってもらうこと、正しく理解してもらうことが重要と考えています。
人道援助などと改まって言うと、今の日本では少し変わったことのように受け止められるのかもしれません。けれども、欧米ではごく自然な、人として行うべき当たり前の活動として受け止められています。日本も早くそういう状況にまで持っていきたい。
そんな思いがあるから、例えばテレビを観ていても、バングラデシュの状況が伝えられずに、芸能ニュースばかりが放送される現状に腹立たしい思いがしてなりません。

世界に厳然として存在する悲惨な状況を何としても変えたい
つい最近、アフガニスタンにいる知人が、銃を構えている子どもたちの写真をSNSに投稿していました。純粋無垢な子どもたちだからこそ、大人に洗脳されやすいのです。こういう状況をつくっている責任が、第一にはアフガニスタンの人たちにあるのは言うまでもありません。けれども、そうした状況を放置している私たちの、無関心、無責任が、こうした悲惨な状況を生み出しているのも間違いはないのです。
国境なき医師団は、単なる国際機関ではなく、ムーブメントである。これが我々の基本的なスタンスです。何のためのムーブメントなのかと問われれば、「一人でも多くの命を救う」が答えです。世界に厳然として存在する悲惨な状況に対して、NOという意思表示を示すとともに、救える命を一つでも多く救う。この信念は活動に関わるメンバー全員が共有しています。
現状をこのまま受け入れてはならない
理想は高く掲げているものの、実際に現地に赴くと絶望的な気持ちに襲われることも多くあります。バングラデシュでロヒンギャの難民キャンプの悲惨な状況を目の当たりにしたときもそうでした。
けれども、落ち込むと同時に強く湧き上がってくるのが怒りです。こんな状況は受け入れられない、認めてはならないし、諦めては絶対にいけない。
2015年、アフガニスタンのクンドゥーズにあった国境なき医師団の外傷センターに、アメリカ軍が爆弾を落としました。これによりスタッフが14名、患者さんと付き添いの方28名の合計42名が命を奪われたのです。

爆撃を受けたクンドゥーズ外傷センターの入院病棟(2015年10月撮影)
一度にこれだけ多くの人命が失われたのは、国境なき医師団としても初めての出来事でした。非常に衝撃的な事件であり、国境なき医師団インターナショナルの会長が国連の安全保障理事会で抗議演説をしています。
我々のような人道援助による医療機関を攻撃するのが、地域に暮らす患者さんの命綱を奪うという意味で、冷徹な軍事戦略としては効果的なのでしょう。病院さえもが攻撃されるのであれば、もうどこにも逃げ場はないと、相手を絶望感に陥れることができますから。
クンドゥーズでは、周辺にさまざまな施設がある中で、明らかに病院だけがピンポイントで狙われました。もちろん、我々は全力を挙げて抗議しました。けれども国際社会は、一切動かなかった。
当事者であるアメリカは、オバマ大統領が誤爆だとして謝罪声明を出しましたが、それだけです。だから、我々は「“病院を撃つな”キャンペーン」を行っているのです。他国による化学兵器の使用に対しては大騒ぎするアメリカが、自分たちの病院爆撃については内部調査でおしまい。病院に爆弾が落とされるようなことは、断じてあってはなりません。

命を救えなかった子どもたちのために
これまでの経験で忘れることができないのは、命を救った子どもたちではなく、救えなかった子どもたちです。同じような状況で苦しんでいる子どもがいるのなら、今度こそ、あと一人でも、何とかして救ってあげたい。この諦めの悪さ故に、私は何度も海外に出向いているのでしょうし、絶望しながら、諦めきれず、日本での活動を続けている理由です。
毎回、私自身は派遣期間が終われば平和な日本に帰国する。けれども現地の状況は何も変わらないままです。派遣先に到着したときに、大勢の子どもたちが苦しんでいる姿に直面し、全力で治療に当たるものの、帰国時に苦しんでいる子どもたちの数が減っているかといえば、決してそうではない。
そんな子どもたちを置き去りにして、日本に帰る。それなのに私が帰国するときには、子どもたちが別れを惜しんで診療所に集まってきて見送ってくれる。中には泣いている子どももいる。その姿を見ると、この子どもたちのために、何としてでも戻ってこなければ、彼らを苦しめているこの世界を、救えない命を救える世界にしたいと思うのです。
現地にいても、日本にいても、日々、自分の無力さに対する腹立たしさにとらわれています。何としても、こうした状況は変えなければならない。もちろん、世の中が簡単に変わるなどとは、夢にも思っていません。
会長になって3年。成果を感じられるところまでこれていないことは申し訳なく、歯がゆく感じていますが、諦めの悪さが私の唯一にして最大の取りえです。命を救えなかった彼らと、笑顔を見せてくれる子どもたちに顔向けできるよう、これからも諦めずに頑張りたいと思います。

国境なき医師団で2度目の派遣地となったインドネシア東端の小さな島、アロル島で(2005年2月撮影)
(聞き手=竹林篤実 / インタビュー写真撮影=加藤梓)
国境なき医師団(Medicins Sans Frontieres:MSF)は、独立・公平・中立な立場で、医療・人道援助活動を行う国際NGO。アフリカ、アジア、南米などの途上国、中でも紛争や感染症の流行地などでのその献身的な活動は世界中から高く評価され、1999年にはノーベル平和賞を受賞した。
【関連記事】
・「厚生労働省医系技官・加藤琢真氏インタビュー|日本、そして世界で、医療をいかに届けるか~『人・薬・もの』のデリバリーイノベーションを目指して」加藤 琢真 氏(厚生労働省医系技官/佐久総合病院国際保健医療科・小児科医)
・「医師としての存在価値を肯定できる場所から~『リアル』を求めた海外ボランティアで“医療に対する謙虚さ”を学ぶ~」石田健太郎氏(産婦人科医)
・「海をわたる診療船『済生丸』取材企画|【後編】知ってほしい、より広い医療の世界を~へき地医療の先進地域で、日本医療の将来を見据える」若林 久男 氏(香川県済生会病院 院長)
- 加藤寛幸(かとう・ひろゆき)
- 1965年、東京生まれ。1992年、島根医科大学(現・島根大学医学部)卒業後、2001年、タイ・マヒドン大学熱帯医学校において熱帯医学ディプロマを取得。東京女子大病院小児科、国立小児病院手術集中治療部、Children's Hospital at Westmead(Sydney Children's Hospital Network)救急部、長野県立こども病院救急集中治療科、静岡県立こども病院小児救急センターなどに勤務。国境なき医師団参加後は、スーダン、インドネシア、パキスタン、南スーダンへ赴任し、主に医療崩壊地域の小児医療を担当。東日本大震災、エボラ出血熱に対する緊急援助活動にも従事した。




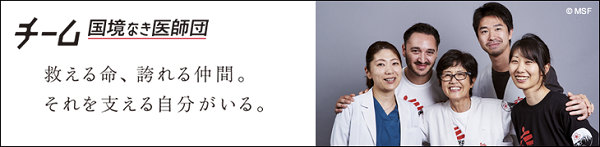
 公式SNS
公式SNS
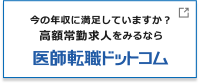
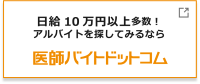





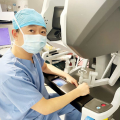














コメントを投稿する