【医師座談会】 『医局を離れる医師たちの本音』~トラブル事例や若手医師の心境の変化から、これからの医師のキャリアと医局について考える~
ライフイベント、大学院卒業にあわせた退局が多数派/「技術習得後にいつでも辞められる」…コスパ重視の若手医師の医局観

従来、医師は大学の医局に所属し、勤務医・開業医・研究職のいずれかのキャリアを歩むことが大半でした。
しかし、近年では社会構造の様々な変化を背景に、医師のキャリアが多様化しています。そんな中で、医局を辞める医師の事情も多様化しているようです。
前編では、医局を辞めた経験のある3人の医師に、その経験談と医局を辞めるメリットやデメリットなどについて語っていただきました。
後編となる本記事では、医局を辞めるということについて、3人の医師の身近で起きたエピソードや最近のトレンドを紹介してもらいます。また、それぞれの経験からみた今後の医局のあり方などについても、深堀りしていきます。
本座談会の前編:【医師座談会】 『医局を辞めるという選択』~経験者から学ぶ、キャリア構築のヒント~
座談会参加者の紹介
C@消化器内科:医師13年目。30代後半、男性。2023年度に大学医局を退局し、その後は関連病院以外の市中病院で勤務中。数年後に、実家のクリニックを継承予定。
I@内科:医師9年目。30代前半、男性。2023年度まで大学医局に所属し、関連病院などで勤務した後に退局。その後は、一般企業でビジネスマンとして週5日勤務しながら、週末は医師として救急外来・専門外来などに従事している異色のキャリアをもつ先生。
S@呼吸器外科:医師20年目。40代後半、男性。若手のころに、最初の医局を退局した経験あり。現在は大学病院勤務で、診療・研究・教育・管理業務に従事。大学病院では当直なしだが、週1回外勤での当直はある。
1.医局を辞めるにあたって、トラブルになった事例はあったか?
司会:先生方の周りで、医局を辞めるにあたってトラブルになったような事例を見聞きしたことはありますか?
I@内科:挨拶が遅くなり、かつ辞める理由が明確でなかったために、関連病院で働けなくなった方はいました。医局側にも次年度の人事調整があるので、妊娠や介護など時期を読みにくいものを除いては、なるべく早めに相談するのがよいのだと思います。
C@消化器内科:身体的な理由で辞められたのに、虚偽の理由だったのかその後治癒されたのかはわかりませんが、問題なく開業して内視鏡もされている先生に対し、当時の教授が立腹していたというのを聞いたことがあります。
また私の周りでも、開業などの理由で辞めたいということを人事調整が始まった後のタイミングで申し出たために、医局がかなりバタついていたことがあります。医局を辞める医師は中堅医師以上のことが多いので、その穴を埋めるのは大変です。
S@外科系診療科:以前は折り合いが付かないときに医局側から引き留められることが多かったですが、最近はあまり聞かなくなりました。引き留めるのにも体力が必要ですし、引き留めるための改善策や条件の提示が難しくなってきているのかもしれません。
辞める側の理由としては、配偶者や家族のことであれば一番丸く収まるでしょうね。
司会:喧嘩別れや、そこまでいかなくても心証が悪い状況で辞めることは、なるべく避けたいですね。大前提として医局人事の調整が始まる前など、できるだけ早めに相談する方が良いようです。
また、医局側が納得しやすいような理由を説明できるということが重要ですね。
2.医師が医局を辞める理由やタイミングは?大学院との関係は?
司会:先生方によってさまざまではあると思いますが、医局に入った医師が辞めてしまう理由やタイミングというのは、結局どのようなものが多いのでしょうか。また、以前と状況は変わってきているのでしょうか。
S@外科系診療科:私の身近なところでは、家庭の事情や収入の少なさ、先行きの不安などを理由に診療科を変えた医師が複数人います。
タイミングとしては、大学院の卒業時はひとつの節目になっている気がします。辞めていく医師の年代的にも、上のポジションが詰まっていて、キャリアアップが目指しにくい感じがありました。最近退局する医師の理由としては、時代の変化もあり無理もないかなと思います。
C@消化器内科:残念ながら、上司や組織自体への不満が理由のひとつになっている場合があります。また、タイミングとしてはやはり大学院の卒業時や、お世話になった教授の退官などを節目に辞める人は多いです。
ただ、最近は卒後4~8年前後の専門医を取った後で、大学院にも行かずに早めに辞める先生も増えていると聞きます。
I@内科:待遇面のほか、妊娠や子育て、介護などのライフイベント、他にやりたいことができた場合などがあると思います。大学院については、最近では医局に附属する大学院以外で、公衆衛生の大学院やMBAといった経営関連の大学院に行く人も増えています。
いろいろな世界にアンテナを張って、フットワークを軽く行動していきたい人にとっては、医局は窮屈になっているのかもしれません。
司会:これまではライフステージが変わっていく中で、収入などの待遇面、家庭の事情、ときには不満などにより辞める人が多かったようですね。
また、本来であれば大学院を卒業するということはその後も研究を含めてグループ内での活躍を期待されるはずですが、それを節目に辞める人も多い現状は、今後の医局や大学院のあり方について考えるべき材料のひとつなのかもしれません。
3.今後の若手医師のキャリア形成と、医局との関係は?
司会:『直美』という言葉が流行ったように、ここ最近の若手医師のキャリアについての考え方や選択は、以前と大きく変わってきているように思われます。
医局での生活および医局を辞める経験をした先生方からは、今後の若手医師のキャリア形成と医局との関係について、どのように見えていますか?
I@内科:世代間で考え方が違うと思いますが、今の私くらいの年代がちょうど狭間な気がしています。専攻医までは経験のための残業などは厭わなかった一方で、今後論文をたくさん書いて定年まで大学で、というキャリアを描く人は減っている感じがしています。
その反面、私の少し上はまだ王道のキャリアが中心で、より若い年代ではコスパよく今稼ぐことにシフトしている人が多い印象です。
そもそも大学病院の働き方がボランティアのようであり、やむを得ず収入を外部から補填するという歪んだ仕組みも、そろそろ限界なのかもしれません。
C@消化器内科:I先生よりも若い20代の外科医に聞きましたが、このあたりの世代は医局を職業訓練校程度にしか考えておらず、いつ辞めようかと皆考えているということでした。
またある研修医に聞いたところ、どの診療科でどこまで習得すれば食いっぱぐれないかという観点で考えている人が多いとのことでした。理解はできますが、実際我々とは全く違った考え方で若手時代を過ごしているようです。
ただし、この話の前者は都市部の私立大学出身、後者は地方国立大学出身ですが東京で働いている先生で、出身大学や働いているところによる考え方の違いは大きいと思います。
S@外科系診療科:そもそもは、大学院生を増やすことで医局の研究業績が上がりますので、これまでは大学院を卒業することで将来的な人事に有利に作用していたのかもしれません。しかし、今後は大学院も淘汰されてくる気がします。内科系で医局に所属するメリットに、学位取得ということはあるのでしょうか。
I@内科:医局のメリットは専門医取得と、病気や産休・育休など代打を要する場面に強く、お子さんがいる女性の医師にとって働きやすい場合もある、ということが挙げられると思います。
まず新専門医制度の中では、医局フリーだと専門医が取りにくくなりました。また、医局と関係ない状況で就職していた場合、何かしらが原因で急に休職しないといけなくなった場合のリスクヘッジであったり、休職後に復職するときの交渉も大変です。
一方、医局派遣であればその限りではない感じはします。さらに、医局派遣の場合は年次に応じて待遇が一律なので、家庭の事情などで緩やかな働き方をしたい方には、メリットになる場合も考えられます。
C@消化器内科:外科の若手に聞いても、やはり専門医については医局以外のプログラムだと情報やサポートが少なかったりしてスムーズに取得できない場合があり、まずは入局を選ぶ人が多いとのことです。ただ、いつでも辞められると思っているというのを聞くと、やはり我々世代との大きな差を感じます(笑)。
司会:保険診療の範囲内においては、かつては皆当たり前のように医局に入局しており、現在でも新専門医制度などを背景に、まずは入局する人が多いですね。
ただし、医局自体や大学院、また医局を辞めることに対する感覚は、大きく変わってきているということがわかりました。
4.まとめ
座談会後編では、多様な事例やその背景にある考え方について紹介してもらいました。医局でのキャリアを一度経験したからこそ分かる視点で深い議論となり、今後のキャリアに悩んでいる医師にとって、非常に参考になるものとなりました。
また今回の座談会を通して、社会がどんどん変化していく中で、大学院や医局そのもののあり方に課題が多いということも浮き彫りになりました。
現状でも、医師の育成や地域医療において医局が重要な機能を担っていることは間違いなく、今後の医局を取り巻く状況や医局の変化について、注視していく必要があります。




 公式SNS
公式SNS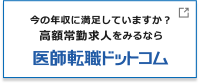
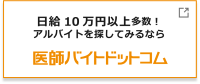





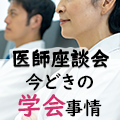
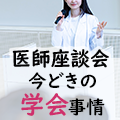

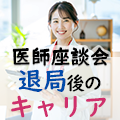






コメントを投稿する