医師がSNSでよく見ているのは?おすすめXアカウント紹介
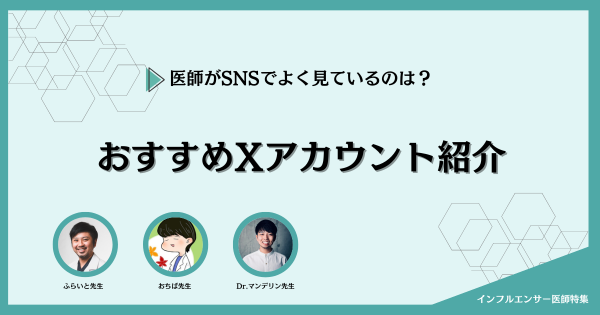
医師にとっても身近なツールとなっているSNS。2021年に実施されたアンケートでは、医師の57%がSNSを利用していると回答しています。
医師は普段SNSでどのようなアカウントをフォローして参考にしているのでしょうか?自らもSNSで積極的に発信されているインフルエンサー医師3名の方におすすめアカウントを紹介していただきました。
今西洋介 / ふらいと先生(新生児科医・小児科医)
Xの仕様変更があってから離れる医療者も増えていますが、未だに自分にとっては情報取得には欠かせないツールです。最近はAIの進歩が著しく、先月出来なかった事が今月できるようになっている事はよく起きる事です。そのため限界助教先生@genkAIjokyoや松井健太郎先生@matsuikentaro1はAIの新機能の解説やAI同士の比較をして下さるのでよく拝見しています。
論文作成と科研費申請のためのプロンプトのセットです
— 限界助教|ChatGPT/Claude/Geminiで論文作成と科研費申請 (@genkAIjokyo) April 8, 2023
✅あくまで下書きとして利用
✅出力の良し悪しを判断できる方が対象
✅節約できた時間を研究自体に回せます
✅常にUp to date
アカデミアパック(英語論文作成と科研費申請のprompt)|genkAIjokyo @genkAIjokyo #note https://t.co/tJlUCbJjhA
ChatGPTが"delve"しすぎ問題の続報https://t.co/EfEyd2hEsB
— 松井健太郎 睡眠・精神医学 (Kentaro Matsui) (@matsuikentaro1) February 17, 2025
2023-2024年にかけて、ChatGPTが出力しがちな特定の単語(delveを中心に)の論文における使用率がめちゃ上がったんだけど、2024年3月を境に少し減ってきている、と。arXiv abstractsを解析したようです… https://t.co/03vKd9bSQy pic.twitter.com/h4NlhVMW2p
今西洋介 / ふらいと先生(新生児科医・小児科医)

新生児科医・小児科医。UCLAにて医療政策学を学びながら、小児医療ジャーナリスト、一般社団法人チャイルドリテラシー協会代表理事として活動。TBSドラマ「コウノドリ」にも取材協力医師として参加。
[instagram]@doctor_nw
[ブログサイト]https://flight.theletter.jp/
おちば先生(腎臓内科医)
TT先生@TT58852391は、実用的かつ勉強になる発信で有名になった腎・膠原病内科医です。若手にも関わらず論文を量産している実績だけでなく、面白さと充実した内容を兼ね備えた単著「無敵の腎臓内科」が話題となっています。定期的な腎臓内科スペース(ラジオ番組)は、ためになるのはもちろんですが、そのゆる〜い関西弁(本人曰く「居酒屋で飲んでるおじさん(笑)」)の語り口調に癒やされる方も多いはずです。笑
<各項目の難易度>
— TT(腎臓内科×膠原病内科) (@TT58852391) September 12, 2024
★:初期研修医向け
★★:内科系後期研修医,非専門医向け
★★★:腎臓専門医向け
・★1つの項目が計10個あり、ここを習得するだけでも診療に幅が出ます。
・“特に読んでほしい対象者”を目次に載せています。“関係ある所だけつまみ食い”する事も可能です。#無敵の腎臓内科 https://t.co/2ui34pZfuc
おちば先生(腎臓内科医)

腎臓内科医。男性医師の育児休業や、J-OSLER・内科専門医試験についてなど、ご自身の体験をもととした記事をブログやXにて発信中。
[X]@autumnleaveskid
[note]https://ikuji-doctor.com/
Drマンデリン先生(総合診療医・家庭医)
私が日々チェックしているXアカウントは限界助教先生@genkAIjokyoです。最新のAI技術についてわかりやすく解説してくれる投稿は、忙しい医療現場にいる私にとって、貴重な情報源となっています。特に医療分野でのAI活用が進む中、最新テクノロジーの動向を把握することは、医師としての視野を広げることにもつながります。
例えば画像診断におけるAIの進化や、医療データの解析手法など、これからの医療に必要とされるデジタルスキルについても考えさせられます。時には難しい内容も含まれますが、ユーモアを交えた解説は読んでいて楽しく、息抜きとしても最適です。医療とAIの共生について考えるきっかけを与えてくれる、私にとって大切な「学びの場」となっています。
ChatGPT PlusユーザーでもDeep Research利用可能になったのでこちらも再掲しておきます
— 限界助教|ChatGPT/Claude/Geminiで論文作成と科研費申請 (@genkAIjokyo) February 27, 2025
「あの本、何が書いてあったっけ…?」なんてことありませんか?
Deep Researchで読書ノートを作ればいつでも本の要点をチェック可能に!
読書の効果を最大化し記憶に残る読書体験をhttps://t.co/FVCVGkeiSS
Drマンデリン先生(総合診療医・家庭医)

総合診療医・家庭医。函館の市中病院で活躍する傍ら、YouTubeチャンネル「YouTube医療大学」の運営や地域の相談窓口「はこだて暮らしの保健室」の設立など、幅広い活動に取り組む。
[X]@Dr_mandheling
[instagram]@dr.mandheling
[YouTube]@YouTubeMedical
まとめ
SNSの利用目的には、情報収集や息抜き、正しい情報の発信など幅広くあるかと思いますが、先生方が紹介されたアカウントを拝見するとタメになりつつユーモアもあるといったアカウントが多いことがうかがえます。
また、AIに関して発信されている方々をよく見ているというコメントも多く、医師の方々のAIへの関心の高さも垣間見ることができました。
各先生がコメントの中で紹介されたアカウントはもちろん、紹介した先生方ご自身のアカウントも、参考になることが多いと思いますので、よければフォローしてみてはいかがでしょうか。




 公式SNS
公式SNS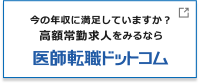
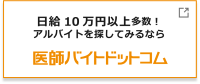

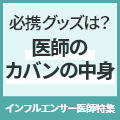
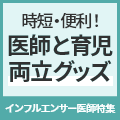
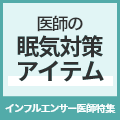
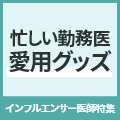

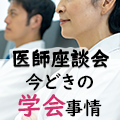
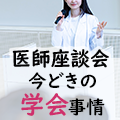







コメントを投稿する