【医師座談会】 「退局してQOLが向上」「医局外だからこその課題も」―退局後のキャリアの築き方とは?
転職で得る自由と引き換えに、専門性を維持する難しさと直面/紹介会社や人脈などを活用した情報収集が転職成功のカギ

従来、医師は大学の医局に所属し、勤務医・開業医・研究職のいずれかの道を歩むのが一般的でした。 しかし、近年では社会構造の変化に伴い、医師のキャリアの選択肢は広がりつつあります。
前回は、医局を退局した経験を持つ3人の医師に、その経緯や医局を離れることのメリット・デメリットについてお話を伺いました。
本記事では、新たな先生方にもご参加いただき、退局後のキャリアの実情や転職時の留意点、そして今後の展望について掘り下げていきます。
本座談会の後編:【医師座談会】退局してから感じたギャップとは?転職活動のコツと、”やりたいことをやる”大切さ
座談会参加者の紹介
K@外科:医師13年目。30代後半の男性、3児の父。医局を退局して4年。サブスペシャリティ(以降:サブスペ)を取得後、大学病院の給与面や家族の事情を考慮し退局。その後、ワークライフバランスを重視し市中病院へ転職。しかし、手術件数の減少によりやりがいの低下を感じ、来春からは専門性をより高められる病院へ転職予定。
I@内科:医師9年目。30代前半の男性、1児の父。医局を退局して1年。大学医局に所属し、関連病院での勤務を経て退局。その後は一般企業に転職し、週5日ビジネスマンとして働きながら、週末は医師として救急外来や専門外来に従事。
M@精神科:医師22年目。40代中盤の男性、2児の父。医局を退局して10年。大学病院の医局で専門医と学位を取得後に退局。その後、4年間の研究職を経て民間病院へ転職。現在は副院長として診療に携わるとともに、医師の採用にも関与している。
1.座談会参加医師たちが退局した理由は?
司会:医局を辞めようと思った理由について、簡単にお聞かせいただけますか。
K@外科:退局理由はいろいろ色々ありますが、サブスペを取得したタイミングで退局した理由は次の3つです。
- 同僚の動向:同時期に中堅が大量退局するため、乗り遅れると辞めづらくなるから
- 子育てのリソース確保:子供が増えたため、妻の実家近くに移住したいと思ったから
- 金銭面:仕事内容以上に、給与面の補填の為に当直回数を増やすしかなかったから
I@内科:私の退局理由は、なんとなく登録したビジネス系の転職サイトでお声かけいただいたのがきっかけです。
ちょうどサブスペの専門医を取得したタイミングだったのですが、長く大学にいるイメージも湧かず、かといって開業意欲もなく、保険一1本も怖いけど美容も向いて無さそうだし・・という感じでご縁をいただき(笑)。もともとビジネスマンには漠然とした興味もありましたし。
M@精神科:私の退局理由は、医局でやりたいことが見つからなかったことと、給与面に不満があったことの2点ですね。当時は人手の少ない医局で、論文も臨床も教育もそれなりに行える中堅という立ち位置でした。「周りにとっては居てくれたら助かるけど、自分はあまりやり甲斐を感じない」状態だったので留学を希望しましたが、当時の医局は「誰が当直と外来するの?」と、個人の成長は二の次といった感じでしたので…。
給与も大学勤務がゆえに週6で働いても、働きに見合った金額はもらえませんでした。とりあえず、どこでも良いから自分の興味あるところに出られたら、と退局を決意しました。
司会:それぞれの退局の背景には、ご家族の事情やキャリアの方向性、そして給与といった現実的な要素が大きく関わっていることがよく分かりますね。ワークライフバランスや専門性の追求、さらには医局の体制との相性など、さまざまな要因が複雑に絡み合っているのが印象的です。
皆さんの決断にはそれぞれのタイミングやご縁があり、改めて医師としてのキャリアパスの多様性を感じます。
2.退局してから現在までのキャリアは?
司会:医局を辞めてから現在までのキャリアについて、簡単にお聞かせいただけますか。
K@外科:退局後は手術がほとんどなく、慢性期患者さん中心の病院に転職しました。週4日勤務しながら、非常勤で週1日は健診や訪問診療、産業医などにも従事しています。
現職のワークライフバランスは申し分ないのですが、やはり手術がやりたい気持ちが強く、子供が少し大きくなってきたこともあり、違う病院に4月より転職します!次の病院は忙しめではあるものの、専門性が高く急変は少ないのでワークライフバランスが比較的保たれていること、開業も視野に入れやすいこと、消化器外科専門医を維持できる、という点から選択しました。
司会:I@内科先生はビジネスのほかにも診療もされているのですか?
I@内科:医師としては、土曜日は毎週専門外来、日曜日は不定期で救急外来などに行っています!卒後すぐの転職パターンは素養で勝負できますが、ある程度年齢を経てからだとやはり専門性は武器にしたいところなので、診療スキルも最低限維持しようと思いまして。
あと、収入の確保という点でもやはり医師という仕事は大きいですね。診療アルバイトの報酬面でも専門医の力はすごいので、ほんとに取っておいてよかったなあと思っています…。
K@外科:専門性が大事なのはすごく分かります。少しでも肩書きがあった方が転職活動しやすいと思って専門医をいくつか取得しましたが、今度は専門医の肩書きとそれに見合う実力にギャップができていると感じ始めたので転職して鍛え直す感じです!
I@内科:フリーになると安定→鍛え直し→のスパンを自分で設定していかないといけないところは、医局所属よりも難しい点かもしれないですね…。
M@精神科:退局後は研究所で研究職に従事していました。関わったプロジェクトが4年で一区切りがついたタイミングで、当時あまり研究職や大学でのポストに興味を持てなかったこともあり、東京の民間病院に転職しました。
そこから東京の病院で3年間、関西の民間病院に3年間勤務し、その後現職の病院に転職して2年になります。
司会:皆さんそれぞれ、退局後のキャリアを模索しながらも、専門性の維持や新たな挑戦を大切にされているのが印象的ですね。
K@外科先生は手術への思いを再確認しつつ、新たな環境へとステップアップを決断され、I@内科先生はビジネスと診療の二刀流を実践しながら専門性を武器に活かしている。M@精神科先生は研究職を経たからこそ、臨床に戻る決断をされたとのことで、キャリアの軌道修正の大切さも感じます。それぞれの選択が、今後のキャリアに悩む医師の参考になりそうですね。
3.転職先はどうやって見つけた?見学の時間の確保などは?
司会:みなさま、転職先はどうやって見つけられたのでしょうか?医局所属の勤務医をしているとお忙しく、見学の時間の確保も難しそうな印象ですが…。
K@外科:最初の転職では、エージェントを通して交渉しました。次に転職する病院はエージェントを介した募集をしていなかったので、直接応募です。そのために現職の時に出張扱いで手術見学して顔を覚えてもらいました。
ニッチな領域なので専門病院自体がかなり少なく、私の住んでいる地域でも転職先にほぼ全ての症例が集まる感じなので、病院探し自体はそこまで苦労しませんでした。
I@内科:私の場合、ビジネス系の転職サイトの中で、複数人のエージェントからお声がけをいただきました。その中で興味のある企業を担当している、かつ信用できそうなエージェントを選びました。ビジネス転職では自分の市場価値の理解も曖昧で、また採用の門戸も狭い中での転職活動となるので、初めての方はエージェントを通すことをお勧めします。
最終的に4つの企業の採用試験を受けたのですが、面接では半日有給を使いまくりました…(都度面接が4次・5次まである上に、日中の時間を指定されることが多くて…)。
K@外科:外資だと4次や5次まで面接があることが普通なのでしょうか?
I@内科:早くても3次まではあることが多いですね。「書類→SPIテスト→1次→2次→3次」のような流れが多いです。
M@精神科:私の場合、最初の研究職に関しては、海外ラボや有名病院に見学に行っていた時に、元上司が「こんな道もあるよ」とこっそり教えてくれたんですよね。その後転職した民間病院は、友人の紹介でした。さらに次の病院は直接メールで問い合わせ、現職の病院ではエージェントのお世話になりました。
候補先は全て見学して院長や事務長などと話はするようにしていますし、知り合いがいれば生の情報を集めるようにしています。見学の時間確保は有休を使ったり、平日の休みを使ったりでしたね。
司会:転職の方法も皆さんそれぞれですね。K@外科先生のように直接応募で病院側と関係を築くケースもあれば、I@内科先生のようにエージェントを活用し、複数の企業を比較しながら進める方法もあるようですね。
一方で、M@精神科先生のように人脈を生かして転職先を見つけるケースもあり、改めて「情報収集の手段」と「動き方」が鍵になると感じます。やはり、事前の見学や交渉が重要になってくるので、時間の確保をどうするかもポイントになりそうですね。
4.まとめ
座談会前編では、医局を辞めた3人の先生方に、現在のキャリアと転職活動の方法を中心にお話をお伺いしました。今回の座談会を通して、退局後のキャリア形成には実に多様な選択肢があることが明らかになりました。
また転職の方法一つをとっても、エージェントを利用する、直接応募する、あるいは人脈を活用するなど、戦略はさまざまですが、「情報収集」と「交渉力」がキーとなりそうです。後編では、フリーで転職活動する際の注意点や退局後のキャリアのギャップ、またこれからの展望についても伺っていきます。




 公式SNS
公式SNS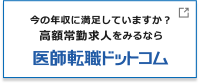
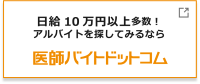





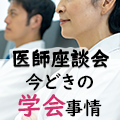






コメントを投稿する