【医師座談会】退局してから感じたギャップとは?転職活動のコツと、”やりたいことをやる”大切さ
円満退局で医局が”もしもの時迎え入れてもらえる場”に/「専門性は最強の保険、活かさない手はない」
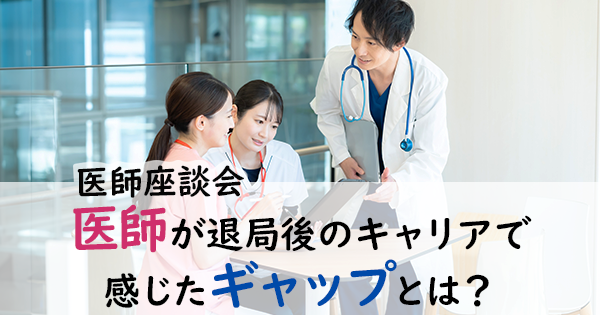
近年では社会構造のさまざまな変化を背景に、医師のキャリアが多様化しています。そんな中で、医局を辞める医師の事情も多様化しているようです。
前編では、医局を辞めた経験のある3人の医師に、実際の退局後のキャリアや転職先の探し方などについてお伺いしました。
後編では、転職活動をする際のフリーならではの注意点やキャリアギャップ、今後の展望を中心にお伺いしていきます。
本座談会の前編:【医師座談会】 「退局してQOLが向上」「医局外だからこその課題も」―退局後のキャリアの築き方とは?
座談会参加者の紹介
K@外科:医師13年目。30代後半の男性、3児の父。医局を退局して4年。サブスペシャリティ(以降:サブスペ)を取得後、大学病院の給与面や家族の事情を考慮し退局。その後、ワークライフバランスを重視し市中病院へ転職。しかし、手術件数の減少によりやりがいの低下を感じ、来春からは専門性をより高められる病院へ転職予定。
I@内科:医師9年目。30代前半の男性、1児の父。医局を退局して1年。大学医局に所属し、関連病院での勤務を経て退局。その後は一般企業に転職し、週5日ビジネスマンとして働きながら、週末は医師として救急外来や専門外来に従事。
M@精神科:医師22年目。40代中盤の男性、2児の父。医局を退局して10年。大学病院の医局で専門医と学位を取得後に退局。その後、4年間の研究職を経て民間病院へ転職。現在は副院長として診療に携わるとともに、医師の採用にも関与している。
1.転職活動をする際に注意している点は?
K@外科:雇用契約書に注意することと、言いづらいことでも自分の意見をはっきりと伝えることですね。
私の場合は現職に転職する際、エージェントを通してかなり細部に渡って交渉し、あとで揉めないよう雇用契約書にしっかり記載してもらいました。
具体的には、当直やオンコール周りなどです。その代わり、自分が病院に貢献できるところとして、他の方ができない&やりたがらないことをやりますとアピールしました。
言いづらいことは全部エージェントが言ってくれるので、自身の意見をはっきりと伝えた方がいいと思います!
I@内科:条件交渉できるところはフリーの大変さでもあり強みでもありそうです(医局所属だとなかなか交渉しづらいですよね)。
自分の強みをはっきりさせること、言いづらいことはエージェントを介して伝えることはビジネス転職にも共通しています。
M@精神科:雇用契約書に記載してもらう内容をしっかり詰めるのは大事ですよね。私自身、医局人事で動いている間は雇用契約書を確認した記憶もなく、研究所の際もほとんど見ていませんでした。
最低限の確認事項だけでも面談時にしっかり話すと「お、こいつは馬鹿な医者じゃないな…適当が通用しないな…」と思ってもらえますよね。他には、退職金規定も含めた院内の就業規定の冊子を頂けるなら頂いておいた方がよいですね!
司会:契約書において、「ここは漏らさないほうがいい」と思われる重要なポイントがいくつかあるかと思います。実際に気を付けている点や、そうしたポイントを見落とさないための工夫があれば、お聞かせいただけますか?
K@外科:絶対外してはならない条件としては雇用期間で、「期間の定めなし(無期雇用)」にすることです。これを怠ると経営者に容易に解雇されてしまいますので。
私は外科系で当直やオンコールなどの拘束時間を気にしていたので、その点の把握は徹底しました。また時間外労働の発生基準の把握も大事かと思います。
ほかには、常勤認定基準が週〇〇時間以上などと決められている学会もあるので、各学会の認定基準も意識する必要があります。私は元々労務に興味があったので、ネットで詳しく法令など調べていました。
I@内科:個人的に大変勉強になります!もはやK@外科先生にエージェントをお願いしたい(笑)
司会:「常勤」というと社会保険だけのことを考えてしまいがちですが、「専門医更新のための認定基準」は盲点になりそうですね。
M@精神科:雇用契約書の記載事項や条件面でのすり合わせに関しては、王道なキャリアを歩んできた先生ほどちゃんとやった方がよいと思います。「自分を安売りしない」という視点ですね。
K@外科:この辺りは知識さえあれば交渉を有利に進めることができるので、その意味では一般的な労務知識は退局前につけておいた方が良いと個人的には思います。エージェントも必ずしも親切丁寧に教えてくれるとは限りません。
ちょうど今は「医師の働き方改革」の真っ只中なので、病院側も気にしているところだと思います。
M@精神科:エージェントの視点から見ると、経歴がしっかりしているドクターは、極端な話「横にいるだけで内定が決まる」ような存在なので、プラスαの要求をするのはハードルが高いかもしれませんね。
現在、私は採用面接をする立場にいるのですが、採用者目線で見ると、やはり専門医の有無や転職歴、休職回数の多さは気になるポイントです。実際の採用判断においても、こうした要素は重要視されることが多いと感じています。
I@内科:勤務医でも、しっかりと専門性を高め、ブランディングと交渉を適切に行えば、自由診療とそこまで大差のない待遇を得ることができる、という考えはもっと広まっても良い気がしますね。逆に言えば、ここに自由診療と保険診療の待遇の差が現れているのかもしれません。
司会:雇用契約書の重要性、交渉のポイントについて、非常に具体的かつ実践的なお話をいただきました。
特に、『言いづらいことはエージェントを通じて伝える』『事前に労務知識を身につける』といった点は、多くの医師にとって参考になる内容かと思います。
2.医局をやめる前と辞めた後で描いていたキャリアとのギャップは?
司会:医局を退局する前と後で、ご自身が描いていたキャリアのイメージと実際のギャップはありましたか?
例えば、ワークライフバランスの変化や、思いがけない方向へのキャリアの展開、新たに見えてきた可能性などがあれば、お聞かせください。
I@内科:私は単純に、医師と同じくらいの収入をビジネスでも得ることができれば、二刀流のような形で将来も安泰だろう、くらいに考えていました。
しかし、いざ転職してみると、これまで関わることのなかった業界の方や経営者の方々から面白がっていただけることが多く、そのご縁から想像以上に新たな進路が開けたと感じています。
すぐに形にならなくても、異業種の友人と新規事業について語り合う時間は何にも代えがたい貴重なものですね。
M@精神科:私は、退局する際には、専門医資格も学位も取得し、論文もそれなりに執筆していたため、転職に対する大きな不安はありませんでした。
ただ、退局後も医局と円満な関係を維持できていることは、意外なギャップかもしれません。講演に呼んでもらったり、同門会に参加したり、論文の執筆を手伝ったりと、これまで通り良好な関係を続けているおかげで、いざという時にはそれなりの待遇で迎え入れてもらえる場として存在してくれている感覚があります。
子どもが大きくなったら、単身赴任もアリかな…なんて思ったりもしますね(笑)。
K@外科:現職のワークライフバランスについては、事前に想定していたイメージと大きな違いはありませんでした。週4勤務にすることで、残りの1日を興味のある分野に充てることができ、想像以上に視野が広がったと感じています。
一方で、医局時代とは異なり、手術件数が極端に減ってしまったことには未練を感じる部分もあり、これが予想外のギャップだったかもしれません。そのため、今年再転職することを決めました。
転職を考えている先生方も、ご家庭の事情などさまざまな理由があると思いますが、一度、自分の仕事に対する正直な気持ちを言語化し、整理することが大切だと感じています。
「もうやり切った」と思えるのであれば、次のキャリアに進んでも後悔しないのではないでしょうか。
司会:医局を離れてからのキャリアの広がり、意外な人とのつながり、そして本当にやりたいことへの立ち返り・・先生方それぞれのリアルな経験をお聞かせいただきました。
「自分の仕事に対する正直な気持ちをアウトプット(吐露)する」というのは、まさに転職やキャリアチェンジを考える上での重要な視点ですね。
3.保険医療の在り方の変化による、キャリアの考え方への影響はあった?
司会:最後に、今後の保険診療の在り方も大きく変化しそうですが、高額療養費制度の見直しやOTC薬の保険適用除外などの議論が進む中で、先生方のキャリア設計に何か影響はありそうでしょうか?
M@精神科:周囲の先生方は比較的のんびり構えている印象ですが、SNSなどで交流していると、「医師としての知見を活かしながら、本業以外のキャリアも築いていかなければ」という焦りが生まれてきますね。
最初の1〜2年は、仕事を選ばずにさまざまなことに取り組んでいましたが、やはり興味のないことは続かないと感じ、現在は興味のある分野を主体に複業をしています。
特に、発達障害を含む障害福祉分野に関心があり、この領域で事業を展開したいと考えています。こうした活動を始めると、結局は「本業の専門性を高めながら、その境界領域の知見を広げていく」ことの重要性を強く実感するようになりました。
そのため、以前は疎かにしがちだった自己研鑽にも、通勤の電車内などの隙間時間を活用して取り組むようになりました。以前は遊び感覚で参加していた学会も、最近では真剣に聴講するようになりました(笑)。
I@内科:SNSでは危機感を持って発信している先生も多く、それがモチベーションになりますよね!
自分はかろうじて専門医資格を2つ持っている程度ですが、アルバイトや副業をするにしても、やはり専門性をさらに高めていかないとまずいな…と感じています。
K@外科:「医療費削減の観点からも、社会貢献の観点からも、専門性を活かした予防医学やヘルスケアの重要性は今後ますます高まる」と考えるようになりました。
結局のところ、やることはどんどん増えていきますが、やりたいことをやっている限り、それがポジティブな動機であれば何でもアリかなと思って実践しています。
極論を言えば、医師であれば何もしなくても生きていくことはできます。でも、せっかくの一度きりの人生、やりたいことをやった者勝ちだと感じています。
この考えに至ったのも、SNSを通じて起業している先生方や、多様な分野で活躍する人々と出会えたことが大きかったのかもしれません。少しでも勇気を出して新たな一歩を踏み出せば、人生は大きく変わるかもしれませんね。
I@内科:仰る通りですね!せっかく医師免許や専門医という「最強の保険」があるのだから、活かさない手はありません。
これまでとは違う環境でも、前向きに飛び込んでみることで、思わぬご縁につながることもあります。ぜひ、皆さまにも参考にしていただきたいポイントですね!
司会:「専門性を活かして医療の枠を超えたキャリアを築く」、「フリーだからこそ目的を持って非常勤や事業に取り組む」、そして「医師免許という最強の保険があるからこそ挑戦できる」という考え方は、今後の医療環境を見据えたキャリア形成の大きなヒントになりそうですね。
4.まとめ
今回の座談会では、医局を離れた後のキャリアの多様性が浮き彫りになりました。単なる転職ではなく、専門性を活かした戦略的な選択や、ワークライフバランスの調整、さらには医療の枠を超えた新たな挑戦について語っていただきました。
転職活動の方法も、エージェント活用・直接応募・人脈など多岐にわたり、いかに情報収集と交渉が鍵を握るかが明らかになりました。また、保険医療の変化を見据え、複業や新規事業に挑む姿勢も印象的です。
医師免許という「最強の保険」があるからこそ、一歩踏み出す勇気が生まれ、それが未来を切り開くことに繋がるのかもしれません。結局のところ、キャリアも人生も「やりたいことをやった者勝ち」です。
今後の皆さまの選択が、より充実したものになることを願っています!




 公式SNS
公式SNS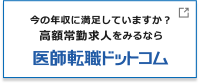
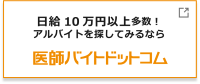





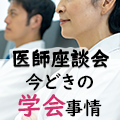






コメントを投稿する