混迷・高額療養費見直し問題 現場の救急医はなぜ異論の声を上げたのか?
志賀隆(救急医/国際医療福祉大学医学部 救急医学主任教授)
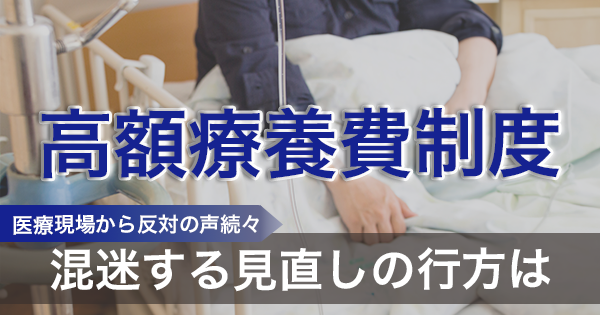
今通常国会で焦点となった「高額療養費制度」の見直し案。自己負担の上限を引き上げる政府案に対し、患者団体や学会などから相次いで反発の声が上がり、石破総理が全面的な凍結と改めての議論を約束する事態になりました。
昨年11月の政府案の公表後、一貫して現場から異論の声を上げてきた救急科専門医の志賀隆さん(国際医療福祉大学成田病院教授)に、今後の議論のポイントや今後の医療現場に求められることを聞きました。
志賀隆教授出演のPIVOT TALK「【「高額療養費制度」見直しの問題点】医師からも反対論/2025年8月から引き上げ/健保の差/自営業者が不利/年収1,160万円シナリオ/応能負担と相互扶助のバランス/平均5,586万円、高額治療が増加」(2025年2月8日公開)
1.高額療養費制度 現場からなぜ発信? 課題意識は
――高額療養費制度に関する問題は、通常国会開始後の今年2月以降に話題になりましたが、志賀さんは、その前の段階からSNSなどで危機感を発信されていましたね。
はい、2024年の12月末ごろ、X(もとTwitter)で、医師を名乗るアカウントの方が危機感を表明しているポストを見たとき、「これはやばい」と感じました。
政府案では、収入が多い人ほど、月額の負担額上限が大幅に引き上げられることになっていました。例えば年収1,650万円の人は、自己負担の月額上限が25万円程度から44万円程度にまで引き上げられます(2027年8月からの負担上限額)。たくさん稼いでいるんだから、いいでしょ? と思うかもしれませんが、例えば自営業の方なら、病気で働けなくなったら収入は途絶えてしまい、そこでこの負担が続いたら生活が破壊されてしまいます。
高額療養費制度は、医療による生活の破綻につながる「破滅的医療支出(※)」を防ぐ根幹です。普段から応能負担として多くの保険料を払っている人が、いざ高額な治療費が必要になったら生活を破滅させられる理不尽な状況が生まれるのは防がなければならないと考えました。
※破滅的医療支出……WHOの定義では、自己負担医療費が家計全体の支払い能力(可処分所得から最低生活費(≒食料費)を引いたもの)の4割を超える状態
――高額療養費制度に該当するケースというと、がんで長期に高額な治療が必要な場合などがまず頭に浮かびます。救急領域でも、高額な医療費で生活が破壊される懸念があるんでしょうか?
例えば、長期の集中治療が必要になるケースですね。最近、壊死性筋膜炎(劇症型溶血性レンサ球菌感染症)の患者さんがとても増えました。壊死性筋膜炎の場合、何度も手術が必要になり、集中治療室で長期間治療を受けなければならないケースも少なくありません。
私の担当した患者さんにも、幼いお子さんが複数いらっしゃる方で、半年以上の集中治療室での治療が必要になったケースがありました。8万点越えのレセプト確認依頼を何度も受けましたので、毎月かなりの医療費がかかっていたと想定されます。
2.見直し凍結の今後、どんな議論が必要?
――志賀さんは早い段階から、政府案に対して異論の声をSNS等で上げておられました。こうした行動に対して、周囲の医療関係者からはどんな反応がありましたか?
そうですね、賛同の声ばかりではありませんでした。声を上げ始めたころには「もう既定路線だから、騒いでも意味がない。静かにしていたら?」というアドバイスを受けたこともありました。「高収入者はほんの一部。世間の共感を得られないだろうし、やむを得ないのでは」といったご意見もいただきました。もちろん、議論を深めるうえでは慎重な意見も必要ですので、感謝しています。
潮目が変わったと思ったのは、やはり天野慎介さん(全国がん患者団体連合会理事長)たち患者団体のみなさんが、当事者へのアンケート調査を実施し、その結果をもとに提言活動を実施されてからですね。また医療政策学者の津川友介さん(カリフォルニア大学ロサンゼルス校医学部准教授)が、データや数字をもとに政府案の問題点を指摘されたことも大きかったと感じます。それとともに、現場の医療者がSNSで違和感の声を上げたり、学会や医師会の中にも反対声明を出すところが増えてきて、大きなうねりとなっていきました。
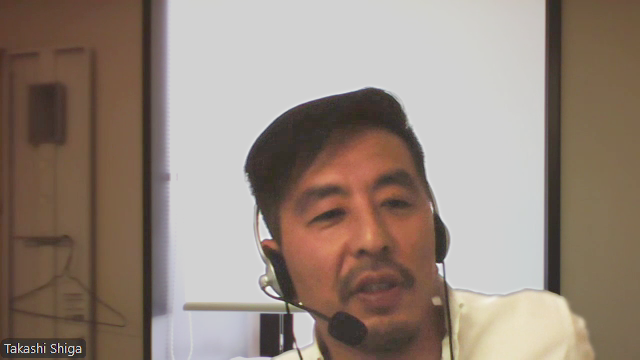
志賀隆さん(筆者撮影)
――通常国会において、石破総理は高額療養費の自己負担上限見直しをいったん凍結しました。どう感じられましたか?
「民主主義っていいなあ」と思いました(笑)。政府の方針で決まったこと、それも社会保障審議会で有識者も賛同したことですから既定路線だと思われがちですが、多様な人が多様な意見を出したことで違う決定が下された。それが民主主義のあるべき姿だと思います。
――石破総理は秋に向けて、改めて議論を進めていくと表明しています。志賀さんとしては、どのような議論が進むことを希望しますか?
マイノリティの声を聞いてほしいですね。もともと政府側のマクロの数字合わせで、患者さん本人などマイノリティの話を聞かずに進めてしまったことで批判を受けたわけです。経済的理由で治療を受けられなくなるかもしれない、そのリスクのある当事者の声を大事にして議論を進めてほしいと感じます。
3.持続的な医療のために、現場からすべきことは?
――高額療養費見直しは凍結になりましたが、そもそも医療の持続性が危ぶまれている状況は変わりません。国民医療費が46兆円を超えて増え続ける一方、6割の急性期病院が赤字という状況も生まれています。今後、どんな取り組みが必要だと考えておられますか?
やはり、低価値・無価値医療の削減ですね。風邪の抗生物質、インフルエンザなら受診など重症度の低い患者さんにあまり意味のない治療があります。そしてエビデンスが乏しいけれど、日本だけで使っている薬などもあります。それらは見直していくべきです。また人口あたりの病床が多いと医療費が高くなる傾向も知られており、地域の病床数の調整も必要です。
オーストラリアでは公立病院と民間病院の2種類があり、がんや心臓病、救急医療など生命に必須なものは公立病院で無料もしくは一部の自己負担で受けられるけれど、関節置換や眼や鼻の手術などすぐに命にはかかわらない治療については民間病院(多くの場合は民間の医療保険で受診する)という棲み分けを行っています。日本でも医療制度の維持のためには、こうした濃淡のある制度を作っていく必要があるかもしれません。
――患者側にとって、これまでのようなフリーアクセスは望みにくくなるかもしれませんね。医師側の働き方や制度にも影響はありますか?
そうですね。現状の専門医制度に関しては、課題があると感じています。いまは一つの大学の整形外科に数十名の専攻医が入ることができたりしますが、本来は患者さん側のニーズを考えて育成人数を決めるべきです。地域に一つの科の専門医が多ければ、医師喚起型の医療が行われてしまうかもしれません。
最近では、美容医療も含めて生死に関係が薄い分野の人気が高まっていますが、その対策としてがんや心臓病、救急などに従事する医療者の待遇改善も欠かせません。そう考えていくと、限られた財源で医療の質を維持していくためには、患者さん側も医師側も「不便との共存」が必要になると感じています。
4.流動性が高くなる未来を医師はどう生きるか? 志賀医師のメッセージ
――少子高齢化、国民医療費の増加などの社会状況は今後深刻化していきます。そんな状況の変化の中で、若い医療者はどのようなキャリアを志向すべきか、志賀さんからのメッセージを教えてください。
少子化や高齢化、さらには生成AIをはじめとする技術革新が進む中で、今後、日本の医療の制度は確実に流動化します。だからこそ、「少子化だから小児科は諦めようかな」という形でキャリアを考えるのはやめたほうがいいと思います。
いま将来性があるように見える診療科でも、今後その通りかは誰にもわかりません。昨今のアメリカのように、大統領が代わったら一気に状況が変わってしまうなんてこともあるかもしれません。目先の待遇で診療科を決めてしまったら、その待遇が変ったときの後悔は大きくなります。
不安定な状況があるからこそ、自分自身がどんなことに喜びを求めるか? 好きな領域はどこか? ということをしっかり見極めたほうがいいと思います。もちろんワークライフバランスも大事です。その両方を考えたうえで、自分が納得して選び取った進路であれば、状況が多少変わったとしてもやり続けられます。
波が高まる時代だからこそ、自分の中にしっかりとした「根」を張り、波にさらわれてしまわないようにすることが大事なのかなと思っています。
(聞き手・文=市川 衛)
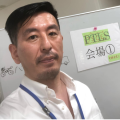
- 志賀 隆(しが・たかし)
- 1975年、埼玉県生まれ。2001年、千葉大学医学部卒業。学生時代より総合診療・救急を志し、米国メイヨー・クリニックでの救急研修を経てハーバード大学マサチューセッツ総合病院で指導医を務めた救急医療のスペシャリスト。東京ベイ・浦安市川医療センター救急科部長などを経て2020年6月から国際医療福祉大学医学部救急医学教授、2021年4月から主任教授(同大成田病院救急科部長)。安全な救急医療体制の構築、国際競争力を産み出す人材育成、ヘルスリテラシーの向上を重視し、日々活動している。『考えるER』(シービーアール、共著)、『実践 シミュレーション教育』(メディカルサイエンスインターナショナル、監修・共著)、『医師人生は初期研修で決まる!って知ってた?』(メディカルサイエンス)など、救急や医学教育関連の著書・論文多数。

- 市川 衛(いちかわ・まもる)
- 武蔵大学准教授(メディア社会学)。東京大学医学部を卒業し、NHKに入局。医療・健康分野を中心に国内外での取材や番組制作に携わる。現在は武蔵大学准教授に加え、READYFOR㈱ 基金開発・公共政策責任者、広島大学医学部客員准教授(公衆衛生)、㈳メディカルジャーナリズム勉強会 代表、インパクトスタートアップ協会 事務局長などを務めながら、医療の翻訳家として執筆やメディア活動、コミュニティ運営を行っている。




 公式SNS
公式SNS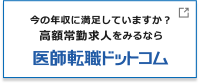
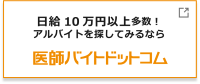

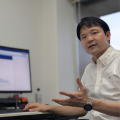



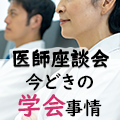
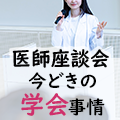







コメントを投稿する