患者さんの「奥行き」に触れられる訪問診療―病院の外にある「やりがい」とは
石黒 剛(医療法人白青会 いしぐろ在宅診療所(岡崎)院長)

病院から在宅へ。病床数がOECD各国の中で最も多く、社会保障費や病院従事者の負担も大きい日本では、在宅医療への転換が推進されています。実際に在宅患者数は年々増加傾向にあり今後も需要の増加が見込まれる中で、課題の一つとなっているのが担い手となる医師の確保です。
医師へのアンケートでは、在宅医療は給与やワークライフバランスが良いといったメリットが挙げられたものの、「急性期病院のような対応ができない」「やりがいを感じにくい」といった声もあり、在宅医療を選択する医師は未だ足りていない状況です。
病院とは求められるものも異なる中で、在宅医療に取り組んでいる医師はどのようなやりがいや魅力を見出せるのでしょうか?いしぐろ在宅診療所(岡崎)の石黒剛院長にお話を伺いました。
『Dr.コトー診療所』のような「人間くささ」と「半歩先を照らす」姿勢
――『Dr.コトー診療所』が医師を目指したきっかけとのことですが、特にどのようなシーンに魅力を感じられましたか?
改めてどこかなって考えると…、「郷に入っては郷に従え」じゃないですが、自分の言うことを聞かせるより、相手のことを尊重している印象があって。
有名なのは、島の男の子が虫垂炎になって、本島まで運ぶ時間がないから船の上で手術するシーン。今、医師として見ると「そんなことやったらヤバいよ」と思いますけど(笑)、それ以外に選択肢がない場合に、より最適な解を一生懸命考えられるのはすごいなと。
―― 確かに、すごいシーンですよね。
でも、やる時はやるけど、船で帰る時にはゲロゲロ吐いてたりする(笑)。そういうダメなところもある「人間くささ」や、柔らかな雰囲気から感じられる「温かさ」に惹かれました。
一番印象的だったのは、土砂崩れで車が巻き込まれ、子供のお腹に傘が貫通しちゃうシーン。両親はパニックになって「早く抜け!」って言うんですけど、先生は抜いたら死んじゃうから病院で手術しようと説得するんです。
――緊迫した場面ですね。
先生も必死なはずなのに、子供に対しては「大丈夫だよ」って、とにかく安心させようとする。根拠がなくても、その言葉で安心できることってあると思うんです。
僕ら医師は医学的に正しいことをやるべきですが、それ以上に人にとって大事な部分をないがしろにしたくない。患者さんやご家族にかける言葉一つひとつに気をつけます。悪い状況でもそのままストレートに伝えるのではなく、まず「今どう感じてるか」を伺って、不安や感覚をすり合わせていく。
結局、みんな分からないことは怖い。僕らは医師として少し先の未来を知ってる部分もあったり、でも不確実だったり。それでも「半歩先を照らす」というスタンスは、コトー先生から学んだものとして気持ちの中にありますね。
「自業自得」で終わらせない。「なんでこういう状況に?」を知る、奥行きのある医療

―― 医師としてよりも、人間的な部分に惹かれたんですね。
そうですね。例えば以前、アルコール中毒、肝硬変でお腹が水でパンパンという方のところへ行ったんです。家はゴミだらけで、医学的に見れば自業自得かもしれない。でも、「その人はなんでこんな状況になっちゃったんだろう?」って思うんです。
―― 背景を知ろうと。
色々聞いていくと、地元でうまくいかずに出てきて、こっちでもうまくいかず、仕事終わりにお酒を飲むのが習慣になった、と。まさか自分が肝硬変になるとは思ってなかった、と。
それを聞くと、すごく人間っぽいな、と。僕もボタンを掛け違えばそうなるかもしれない。家族を事故で失ったら、僕も酒に溺れるかもしれない。そこに自分との共通点や人間としての不安定さを感じると、この人のためにできることをやってあげようと思えるんです。
―― それが在宅医療の面白さでしょうか。
はい。その人の「奥行き」に思いを馳せたり、覗き込むことができる。外来みたいに数分で効率的に回さないといけない状況では、僕のやりたい医療はできなかった。
病気って、多くが生活の結果でもあるじゃないですか。生活習慣病は特にそうです。だから、その人の生活を知ることは、今の病気を理解することにも繋がる。それができるのが、訪問診療のいいところかなと思ってます。
在宅医療は医師にとってリスクに対するリターンが高い
―― 最近実施した在宅医療に関する医師のアンケートでは、在宅医療のメリットとして給与ややりがい、働きやすさなど、デメリットではスキルの維持やオンコール対応、車での移動や訪問先の環境などが挙げられました。石黒先生は実際どう感じていらっしゃいますか?
うーん、全部「事実」じゃないですかね。まあ、そうですよね、っていう感じです。何に価値観を置くかですけど、全部その通りだと思います。
その上で、僕がメリットとして感じているのは、「リスクに対するリターンが高い」ことなんです。
―― リスクに対するリターン、ですか。
医療って、どんどんリスクの高まる仕事だと思ってて。病院で手術するとか、関係性ができていない患者さんに難しいことを行うのは、思いがすれ違ったり、うまくいかなかった時のリスクが極めて大きい。しかも報酬はそこまで高くないし、訴えられるストレスもある。
外来も見落としが紛れ込むリスクがある。元気な人生を望んでいる人への医療は、クオリティを求められるし失敗も許されない。
僕は、リスクを取ってる割にリターンがアンバランスだと感じていました。
―― 一方で、在宅医療は?
高いリスクは取っていないんです。開業リスクはありますが、患者さんとは信頼関係が前提だったり、病院で精査した上で紹介されることが多い。
何より、患者さんが医療に求める期待値が、劇的な「治癒」ではなく、現状維持や痛みの緩和といった「ケア」の要素が大きい。医学的な期待値がそこまで高くないんです。
―― なるほど。
もちろん、介護面の知識が必要とか、移動が大変とかはありますが、病院で医療をするよりリスクが低くてリターンが高い。僕は病院に勤めていても守ってくれると思っていなかったし、「完璧になる」自信がなかった。医学は深すぎて一人で完結できない。患者の期待値も高すぎて「わからないことがリスクになる」世界では自分は挑み切れなかった。
在宅は、「等身大の自分で、等身大の医療ができる」。それが僕には合ってるし、継続できるなと思っています。
在宅医療で重要なのは「再入院予防」と「在宅看取り」の対応
―― 在宅医療といっても色々あると思いますが、先生が大事にされている点は何ですか?
在宅医療で大事な点は「再入院予防」と「在宅看取り」の2つだと思っています。これをちゃんとやらない在宅診療所は存在する意味がない。
昔は診療報酬の関係で、施設訪問メインで荒稼ぎできた時代もありました。ただDo処方で薬を出すだけで、熱が出たら救急搬送、みたいな。
――在宅医療にそういうイメージを持たれている病院勤務の先生もいるかもしれません。
僕らは施設でなく居宅メインでやっていますが、居宅か施設かで一概に言えるものでもない。それぞれいろいろありますが、大事なのはやはり在宅看取りと再入院予防です。
調子が悪くなったらすぐ病院、という流れで病院はパンクしかけています。病院に行っても治療のしようがない患者さんを自宅でちゃんと最後まで見る、あるいは入院しないようコントロールする。僕らが自宅と病院の間のゲートキーパーとして機能することにこそ社会的に意義があるんです。
だから、転職などでしっかりとした在宅医療をしているクリニックを選ぶ時の指標になるのは、「ちゃんと看取りをやってるか?」「再入院予防のために何をしてるか?」だと思いますね。
――具体的にはどういうところを見ればいいでしょう?
例えば、検査機器は何を持っているか、入院についてどう考えているか。特に「この入院いらなくない?」というものを安易に病院に回していないか。
肺炎の悪化のように自宅で治療できるものは自宅で治療していく。その時、入院した時の予測、家で過ごす時の予測をちゃんと伝えて、家族と一緒に選んであげること、「シェアード・ディシジョン・メイキング」といいますが、それができるかどうかが大事だと思います。
病院での「治療」から在宅での「支援」へ。主役は医師でなく患者さん

―― 病院と在宅医療とでは医師のマインドセットも大きく変わりそうですね。
全然違いますね。病院は医師が「治療」するために「管理」しないといけない。僕らは「治療」というより「支援」に近い。覗き込んで支援する感じです。
自宅は僕らの管理下じゃない。医療者が100%責任をもって管理する所じゃなく、患者さん自身や家族の管理下です。だから目標は、病気とどう付き合って、どう納得して過ごしていくか。
――お話を伺っていると「患者さんが主役」、という意識を強く感じます。
そうです。一方で患者さんが主役だからこそ、僕らは「無責任」とも言えるんです。
――無責任、ですか?
「あんたが決めたんでしょ」って言えちゃう。「病院行きたくない」って言ってた人が「苦しい」となって、「今どうしたい?行きたいなら連れてくし、苦しいけど行きたくない方を選ぶならできるだけ苦しくない手伝いはするよ」と。
それで「先生ならどっちがいいと思う?」と訊かれたら、「〇〇さんの価値観なら、家で過ごした方がいいよ」とか、「すごく心配している家族がいるなら病院行った方が良いんじゃない?」といった話をあくまで個人的な意見としてすることはあるかもしれない。
どうするか一緒に決めていく、それがシェアード・ディシジョン・メイキングなのかなと僕は思います。
主役にするからこそ無責任でもあり、無責任に支える。病院での医療と感覚はだいぶ違います。
――ディシジョン、「決める」といっても患者さんの意見も結構変わることもあるかと思います。
そうですね。ACP(人生会議)も「Plan」ではなく現在進行形の「Planning」だから、変わっていいんですよ。人生行き当たりばったりじゃないですか。僕らは半歩先を照らしつつ、躓いたら手を差し伸べられる距離感で見守り、大失敗しないように支える。
病院だと先生方に身を委ねて命を他者に管理される側面があると思います。それが良かったり安心できたりという人もいて、自由だと思いますが、僕だったら自分の人生は自分で決めていきたい。自分の家に帰るっていうのは、「自分の人生の所有権・決定権を自分の手元に戻す」行為な気がしてて、僕らはそれを尊重したいと思っているんです。
患者さんの人生の奥行きに触れ、自分の人生に納得する
――在宅医療をしていて良かったと感じるエピソードはありますか?
3年目に出会った男性患者さんのことはよく覚えています。夫として、父親としてすごくユーモアもあって魅力的な方で、年齢も上の方と対等に近い形でいろいろな話ができて。
その方が亡くなった後にお参りに行ったときは、『「いつも飲んでたお酒、先生お酒好きって言ってたから」と主人から』って、奥さんからお酒を受け取りました。
そのお酒は今でも残っていて、少しずつ飲んでます。
患者さんの人生を聞ける、その「奥行き」を感じる原体験でした。
――疾患だけでなく、その人の背景まで。
訪問診療で見るご家庭って、「普通」の家庭ってほとんどないんです。どの家庭も、まるで短い小説を読んでるようで面白い。
疾患を見てるというより、その人自身やその背景を見てる。「なんでこの人こうなったんだろう」が、診療する中で繋がって合点がいく瞬間もある。
不仲な夫婦を見て「明日は我が身だな」とか(笑)。今目の前にいる人たちを大事にしないと、と思いますね。
――先生ご自身の人生観にも影響が。
自分の人生に納得できるようになりました。
医師って決められたレールの上を走りがちで、「本当にこの人生でいいのか?」って思う瞬間が誰しもあると思う。
在宅医療は、手技がどうこうより、自分の人生に対する答えが立体的になっていく気がします。患者さんたちが、命をもって「ちゃんと納得して生きなきゃダメだよ」って教えてくれる。
別に1〜2年在宅やって、合わなければ急性期に戻ってもいいと思うんですよ。失うものがなければ、得るものもない。失うことを恐れたら、新しいものは得られないですから。
人間らしく対応するために行う「まわりくどい効率化」

――石黒先生がご兄弟で運営されている医療法人白青会やいしぐろ在宅診療所の特色についてお伺いできますか?
特色は、「TTP=徹底的にパクる」という言葉もありますが、「いいものはとにかく取り入れる」こと。クリニックに限らず、世の中のいい会社がやっていることは取り入れる。だから、どんどん変化していく組織です。
あとは、「効率よくやる」こと。税金でやってるわけですから、効率よくやらないと社会への説明責任を果たせない。
――在宅医療で「効率」というのは、少し意外でした。
これ、さっきまでの温かい話とトレードオフの関係じゃなくて。忙しかったら、人は相手に冷たく当たるに決まってるんです。
だから、効率よくやって、人間が人間らしく対応できる時間を捻出する。人の心を殺すような最適化は望んでなくて。患者さんとの繋がりに繋がる、「まわりくどい効率化」と呼べるかもしれません。
――「まわりくどい効率化」、いい表現ですね。医療法人白青会の取り組みであるパートナーシップ制度にも繋がりますか?
まさにそうです。パートナーシップ制度のコアは、「現場レベルの支援」です。
業務マニュアルや教育プログラムが各職種・レベル別に全部揃ってる。普通の開業コンサルは、経理や労務といった院長の仕事の経営面の代行はできても、現場の看護師や事務の支援はできない。やったことないですからね。
――確かに、そこが一番困りそうです。
僕らは長くやってきて、それを言語化・仕組み化してきた。開業1週間はスタッフが現地で研修もします。
経理や労務の管理は、正直誰でもできる。でも、現場が分からないと、経営と現場が対立してしまう。僕らは、院長・看護師・事務がワンチームになるための「土台」を提供する。
困ったことがあれば、社内のWikipediaみたいなナレッジシステムで検索できるし、常にアップデートもされる。医師だけでなく、看護師さんや事務さんにとっても不安の少ない仕組みがコアですね。
訪問診療への道はいつまでも開いているわけではない
――最後に、訪問診療の道に進むか悩んでいる医師へメッセージをお願いします。
もし迷ってる人がいたら、「やっちゃった方が早い」ですね。あなたが迷ってるってことは、周りの先生も迷ってる。
訪問診療にトライするなら、向こう数年以内だと思います。僕らは7年前に始めましたが、それでも「もう周回遅れだな」と思ってましたから。今、興味がある時点で、だいぶ遅れてる。
――そんなにですか。
10年後に新規参入しようとしても、市場はもうないですよ。少なくとも美味しい思いはできない。やりがいがあるといってもやりがいだけで飯は食えないんで。ちゃんと稼ぎながらやりがいも、って思うと、やっぱり早く始めることが一番だと思います。
(聞き手・文=エピロギ編集部)
医療法人白青会 関連情報
- ・Youtube「医療法人白青会【在宅医療×ミニマム開業】チャンネル」
- ・『こんなボクでも開業できました!』石黒 謙一郎 著(中外医学社、2022年)
- ・『訪問診療ミニマム開業支援ガイド: 自己資金0円で半年開業するためのパートナーシップ制度』石黒 謙一郎、山本 拓 著(Kindle版、2024年)

- 石黒 剛(いしぐろ ごう)
- 医療法人白青会 いしぐろ在宅診療所(岡崎)院長。
名古屋大学医学部卒業。岡崎市民病院にて初期研修後、いしが在宅ケアクリニックを経て、2019年にいしぐろ在宅診療所を兄である石黒 謙一郎医師と開業。訪問診療の現場で日々「等身大」の医療を提供しつつ、医療法人白青会にて医師が低リスクで開業できるパートナーシップ制度の仕組みを構築。




 公式SNS
公式SNS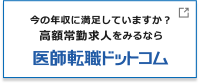
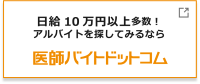













コメントを投稿する