未来の医療「病気を治療するアプリ」をつくる【後編】
すべては医師として「患者さんによくなってもらいたい」の思いから
佐竹 晃太 氏(呼吸器内科医/株式会社CureApp 代表取締役CEO)

身近にあるスマートフォンで使える「治療アプリ(※)」によって、まったく新しい治療アプローチを生み出そうとする医療系テクノロジー・ベンチャー企業「キュア・アップ(CureApp)」。同社を起業した佐竹晃太氏は、国内の病院で臨床医を経験した後、海外に留学をされています。そしてその留学先で経営学や最先端医療ITの世界に触れたことがきっかけで、起業を思い立ったといいます。
現在は医師兼CEOとしてオフィスとクリニックに立つ佐竹氏に、起業のプロセス、そして医師としての想いを伺いました。
※治療アプリはキュア・アップの商標です。
アメリカで出会った医療用ソフトウェアの可能性
私が治療アプリと出会ったのは、アメリカへ留学した時でした。
私は北海道北見赤十字病院で2年、内科研修医として勤務し、日本赤十字社医療センターなどで3年間、禁煙外来も含めて呼吸器内科の臨床に携わりました。臨床を外れて留学したのは、一度日本を離れ、世界を見てみたいという願望があったことと、新しいことを学んでみたいという思いからでした。
2012年、上海中欧国際工商学院(CEIBS)へ留学し、経営学修士号(MBA)を取得しました。その後、2013年、医療ITをアカデミックに研究する「医療インフォマティクス」を学ぶべく、アメリカのジョンズホプキンス大学公衆衛生大学院へ留学します。ここで私は運命の出会いを経験します。
それが当時の担当教員が教えてくれた、前述した一本の論文でした。その論文で私はアメリカの医療系テクノロジー企業「ウェルドック(WellDoc)」が開発したスマートフォンアプリ「ブルースター(BlueStar)」の存在を知ったのです。
一介の医師だった私にとって、疾患の治療法といえば「薬」か「医療機器」しか頭にありませんでした。そこにソフトウェア、しかもスマートフォンアプリという身近なツールで具体的な治療効果を出す、しかも糖尿病の新薬と同等の効果を出しているというデータを見たとき、まったく新しい治療法だと本当に驚きました。一人の医師として、その論文を読む前と後で、治療に対する考え方ががらりと変わりました。
エビデンスが出ているだけでなく、事業として成り立っていることも大きな驚きでした。ただ、医療用ソフトウェアを事業として成立させている企業を調べてみると、当時は、ウェルドックの事例を除いて、まだまだどれも発展途上の段階でした。
「今後、日本でも医療用ソフトウェア事業の需要は伸びてゆくだろう。もし今、日本で起業し、いち早く事業を成功させ、海外に展開したら、10年〜20年後、その分野を代表するグローバル企業になれるかもしれない」
製薬や医療機器開発など、すでに強力なライバルが先行する分野で起業しても、勝ち目はない。しかし、医療用ソフトウェアは、まだアメリカですら芽が出始めたばかりの状況でした。今から起業すれば、グローバル市場でも存在感のある企業に成長できるのではないか。医療業界に限らず、イノベーションは、大抵アメリカで起こり、数年遅れて日本で始まるものの結局アメリカに飲み込まれてしまうのが現状です。製薬や医療機器の領域もまた、すでにアメリカやヨーロッパの企業と差がついてしまっています。でも、医療用ソフトウェアなら、今から動けば日本もグローバルに戦える可能性があるのではないかと思いました。
そうして私は起業を思い立ったのです。
それまでは起業家になろうなんて考えたこともありませんでした。しかし、これから巨大なビジネスに成長する可能性があり、多くの患者さんを救うことのできる事業領域の存在を、黎明期に知れたこと。それが自分にとって千載一遇のチャンスなのだと感じたのです。
とはいえ、起業するには資金も、情報も、そして仲間もいませんでした。
その時頭に浮かんだのが、共同創業者であり取締役CDO(最高開発責任者)として名前を連ねている鈴木普です。
彼は私と同じ大学の医学部出身で、部活の後輩でした。学生の頃から医学部にいるのにプログラミングに熱中していたのがとても印象的だったのです。それで、帰国後にさっそく連絡を取りました。当時の彼は、東北大学でバイオインフォマティクスの博士号を取るべく研究員をしていました。「起業するんだけど、手伝ってくれないか?」と声をかけたら、彼は医療用ソフトウェアに興味を持ってくれ、「まずは1週間に1回程度、1〜2時間電話で相談に乗りますよ」と言ってくれました。
2014年7月、キュア・アップを創業し、鈴木と二人でアプリのプロトタイピングを始めました。最初のプロダクトは禁煙治療のアプリでした。私の専門が呼吸器内科だったこと、そして禁煙治療という治療成績が悪い疾患領域に治療アプリを使ってアプローチできると考えられたからです。

未来の医療、「遠隔医療」を実現する
キュア・アップの治療アプリは、分類上はいわゆる「遠隔医療」の一つであり、遠隔治療を行う「医療用ソフトウェア」にも該当します。
アメリカではさまざまな企業がすでに遠隔医療の事業に進出し、高付加価値のサービスを生み出しています。黎明期である日本においても、一部の遠隔医療サービスが実際の医療機関に導入されているとともに、地域間医療格差是正のため、政府も推進していくことを明示しています。
従来型の医療がそうであるように、遠隔医療においても診察を通じて診断し、それを元に治療を行うという過程があります。
従来は、医師が患者さんと対面し、血液検査やレントゲンなどを用いて疾患の特定「診断」を行います。その診断に応じて、点滴や投薬、手術などの処置を行うことが治療にあたります。
遠隔医療では、対面の診療に代わり、例えば無料のテレビ電話ソフト「スカイプ」などを用いて、離れた場所にいる医師と患者さんをつなぐ「遠隔診療」が行われます。
日本でもこれまで、原則として離島や僻地、慢性期疾患の再診で遠隔診療が認められていましたが、2015年の厚生労働省の通達によりその限りではないとの見解が示されました。
診断をするには顔が見えさえすればいいのか? もちろんそんなことはありません。単純に顔を見るという要素だけが遠隔化されるだけでは、医療の質の低下が疑問視されることにもなりかねません。テクノロジーによって、対面診療に劣らない遠隔医療こそが実現されなければならないのです。
例えばアメリカでは医師が診断の際に行う「聴診」も遠隔化することで、医療の質を高めようとする事例があります。患者の自宅にスマートフォンと連携できる「スマート聴診器」があり、使用すると、聴診データがスマートフォンの先にいる医師へ送信され、診断に役立てられるというものです。
では、禁煙治療において遠隔診療を行う上で、客観的なデータに立脚した診断をどう行えばよいのでしょう?
禁煙治療では「呼気一酸化炭素(CO)濃度」が、その経過や、治療の成功・失敗を判断する上で重要な指標となります。であれば、その測定器を遠隔化して治療に役立てようと考えるのが自然です。しかしその測定器は10〜15万円と高価なため、個人では購入が難しく、一般的には医療機関にしかありません。遠隔で禁煙治療を行うのであればCO濃度測定は諦め、医療の質を犠牲にせざるを得ないのか? しかし私は医師として、そこは妥協したくなかったのです。
私が出した答は、「無いのであれば、つくってしまおう」ということでした。とはいえ、弊社はソフトウェアの会社。ハードウェアの技術者はいません。人もいなければ知見もない中での挑戦でした。自分たちでアイデアをかき集め、試行錯誤を繰り返し、開発したのが業界初となるIoTデバイス「ポータブル呼気 CO 濃度測定器一体型治療アプリ」でした。従来は医療機関でしか測定できなかった呼気CO濃度測定を在宅で、安価に行うことを可能にするとともに、従来よりも高頻度で測定結果を得られることから、治療効果の向上をも期待できます。
諦めず、妥協しないことで、自分たちが想像すらしなかった結果が出せる。それがベンチャーの底力になるのかもしれないと感じた開発でした。

こうした遠隔診療や診断の次に求められるのが、離れた場所にいる医師と患者をつないで行う遠隔治療です。大掛かりなものでは、東京にいる医師が、遠隔操作が可能な手術ロボットによって北海道のオペ室にいる患者さんを手術する「遠隔手術」などが挙げられます。
一方、キュア・アップの治療アプリや、前述したアメリカのウェルドックが開発したモバイルアプリ、ブルースターなどは、自宅での遠隔治療を提供するソリューションです。
遠隔治療を行う医療用ソフトウェアの最新事例では、アメリカでは「noom」が印象的な成果を挙げています。いわゆるダイエット支援アプリなのですが、医学的エビデンスに基づいたアプローチから肥満を治療することができるのが特徴です。このアプリを使用した78%のユーザーが、9ヶ月間に渡って持続的な減量に成功したというデータが学術誌『ネイチャー』の関連出版誌である『Scientific Reports』で紹介されました。
他にも、抗がん剤治療を受けている患者の合併症の早期発見を目的にしたアプリ「MOOVCARE™」があります。抗がん剤治療で通院されている患者さんは、免疫力が落ちるため肺炎などの合併症に罹りやすいことが知られています。まだ研究段階で事業化されていませんが3ヶ月に1度の通院では気づくことができないようなわずかな変化を感知することにより、より早期に合併症を発見し治療に移行できるので、合併症関連死を減らすことが期待されています。
また日本ではサスメドが開発、臨床研究中の、認知行動療法に基づいた不眠症治療を行うアプリ「yawn」の他、NTTドコモと東京大学が提携して開発している2型糖尿病・糖尿病予備軍を対象としたスマートフォンアプリなどがあります。
そして、遠隔医療の周辺に、健康促進のためのヘルスケアアプリやウェアラブルデバイス、診断や診療を伴わない遠隔相談サービスがあります。遠隔治療を行う医療用ソフトウェアの市場規模は定かではないのですが、これらモバイルヘルス全体の市場規模では、アメリカでは10年後に9兆円市場を持つ産業になると予測されるデータもあります。
日本のモバイルヘルスの市場規模をアメリカの3分の1から4分の1に見積もった場合、10年後は2兆円程度の市場を持つ産業に成長していると推測できます。
遠隔治療の医療用ソフトウェア事業はまさに黎明期であり、今後さまざまな試みが行われていくでしょう。臨床研究まで進んでいる弊社としては、この分野のリーディングカンパニーとなるべく、日々試行錯誤を続けています。
していることはバイオベンチャー。鍵となる「薬事承認」取得に向けて
キュア・アップの治療アプリのビジネスモデルは、簡潔に言えば、製薬企業の医薬品と同じです。
医薬品のビジネスモデルは、まず病院で医師によって患者に薬が処方されると、患者が薬代として病院に3割のお金を支払い、国民健康保険によって残りの7割が支払われるようになっています(保険償還)。そしてその一部が製薬企業に支払われる。このビジネスモデルにおける医薬品の代わりにアプリが処方され、病院から製薬企業に支払われるプロセスの代わりに、弊社に支払われるということです。
このビジネスモデルでは、保険償還の対象となるための「薬事承認」を得ることが事業をスケールアップする上で重要なポイントになるため、現在準備を進めています。
先程挙げた診断用アプリ「join」が医薬品医療機器等法の承認を受けた前例はあるものの、「アプリ自体が治療効果を持つ」ことでの薬事承認の前例はありません。治験で治療効果を出せたアプリはまだないため、越えなければいけないハードルは高いです。
前編でアプリ開発時にUXデザインに力を入れたというお話をしましたが、薬事承認を得るために必要なデータを、使う人のユーザビリティを保ちつついかに取得するか。「治療効果がある」というエビデンスを得るための工夫も考慮しなくてはいけませんでした。開発や治験だけでなく、国の制度の中でまったく新しい「医療用ソフトウェア」というものをどう診療報酬の中に組み込んでいくのかなど、課題は山積しています。
また、将来的には、海外展開も視野に入れつつ、「アプリの製薬会社」のようなイメージで、色々な疾患に対して治療効果を持つアプリケーションを開発、提供していけたらと考えています。

医師という強みを活かした起業
医療用ソフトウェア事業で起業する際、医師であるということは大きなメリットになりました。
例えば、鈴木とプロトタイピングを重ねた「CureApp禁煙」は、初期段階で慶應義塾大学病院へ導入していただいています。実際に患者さんに使ってもらい、フィードバックをいただけたことで、その後の開発プロセスをおおいに加速することができました。
こうしたことが可能になったのは、私が医師としての共通言語を持っていたからだと感じます。
臨床医として数多くの患者と出会ってきた経験から、患者さんが何に悩み、何をしてほしいかが分かる。病院内の組織構造について現場レベルで知っているため、現場の医師とも同じ目線でコミュニケーションができる。今は起業家・事業者として病院に行くことが増えましたが、使っている共通言語は臨床医をしていた頃と同じです。
それに、「病気で困っている患者さんによくなってもらいたい」という気持ちも同じです。患者や医療との関わり方が変わっただけで、今も、医師として、事業を行っています。
変わらない、医師としての想い
今、起業して、3年が経ちました。
2017年2月6日には、Beyond Next Ventures、慶應イノベーション・イニシアティブ、SBIインベストメントを引受先とし、総額で3.8億円の資金調達を行うことに成功しました。
もちろん、事業をつくっていく中で辛い場面もありました。
生まれて初めての肩書でもある「社長」という存在。社長は、仮にその月内に事業資金が入金されなければ会社が倒産するような場面でも、いつもと同じ顔をしてオフィスに立って仕事をしなければならない。そして、いつもと同じ顔で投資家の方々に会い、事業の説明をして、資金調達をお願いしなければなりません。億単位のお金が動くタイミングでは、気付くと何日も眠れていないなんてこともあって、自分でも認知していないストレスを感じているようです。
それに、小さなベンチャー企業で前例のないことをやろうとすると、目指していることに共感してくれ、かつそれを実行できる能力を持った優秀な仲間が必要なのですが、なかなか難しい面があります。ビジョンや夢に共感してくれ、「これまで治しきれなかった病気をソフトウェアという新しいツールで治す」というアプローチの新しさ、社会に与えるインパクトに興味を持ってもらえるように、必死でアピールをしていますが、採用はすごく大変でしたし、今も苦労しています。
勉強は、努力すればできるようになる。でも、事業をやっていると、お金のことも採用も、自分の努力ではどうしようもない相手次第な難しさに何度も直面させられます。
それでもやってこられたのは、人を治すということは素晴らしい仕事だと、私が心から思っているからです。
専業の医師であった時の私の治療方法は手術や薬だけでした。今、その方法はソフトウェアに変わりましたが「患者さんに早く元気になってほしい」という気持ちはずっと同じです。
だから私の肩書は今も、医師兼起業家です。どちらが欠けても、キュア・アップは成立しません。
今でもオフィスと同じフロアにクリニックを設け、医師として夜間に診療を行い、治療アプリを使っていただいている患者さんから感想を聞いたりアドバイスを提供したりしています。また、週に1回、日本赤十字社医療センターで医師として勤務をしています。それらの知見を事業に活かしながら、今日も開発を進めています。
20歳ほど年上の起業家で医師の知り合いがいるのですが、以前その方に「医師には4種類ある」と教えられたことがあります。
1人目が臨床医として目の前の患者を治す医師。2人目が研究者として新しい治療法を開発する医師。3人目が医療制度や医療政策を通じ、政治家として患者を救う医師。最後の4人目が、医薬品や医療機器など、治療のための道具をつくる、事業家としての医師です。
臨床医だけをしていた頃と少し関わり方は変わったけれど、今も自分は医師なのだと感じています。今でも患者さんに「ありがとう」と言われることが、一番嬉しい。それはずっと変わりません。
(聞き手・森旭彦)
【関連記事】
佐竹晃太氏インタビュー「未来の医療「病気を治療するアプリ」をつくる【前編】|患者の“孤独な闘い”を助ける、新しい治療法を目指して」
「手のひらに収まる画面が診察室に~遠隔医療のこれから」
小児科オンライン・橋本直也氏インタビュー「医療の未来を創る~若き医師の挑戦【前編】」
「医師は人工知能と 明日を夢見ることができるのか〜IBM「Watson」が拓く医療の未来〜」

- 佐竹 晃太(さたけ・こうた)呼吸器内科医/
(株)CureApp 代表取締役CEO - 2007年慶應義塾大学医学部を卒後、日本赤十字社医療センターなどで呼吸器内科医として勤務。2012年に上海の中欧国際工商学院(CEIBS)へ留学し、経営学修士号(MBA)取得する。2013年米国ジョンズ・ホプキンス大学の公衆衛生学修士(MPH)プログラムにて医療インフォマティクスを専攻。公衆衛生学修士号(MPH)取得(2013年〜2014年)。帰国後、CureApp,Inc.を創業。現在も日本赤十字社医療センターにて週1回の診療を継続し、医療現場に立つ。




 公式SNS
公式SNS
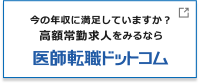
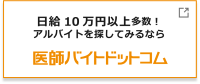


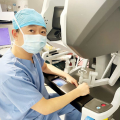













コメントを投稿する