医師と自然写真家、二つの視点で“いのち”を見つめて【前編】
井上 冬彦(井上胃腸内科クリニック 理事長・院長/自然写真家)

一九九七年、アマチュア写真家の最高賞と謳われる林忠彦賞に一冊の写真集が選出されました。『サバンナが輝く瞬間(とき)』と題された本には、雄大なサバンナの自然と、そこで暮らす動物たちの姿が収められています。動物たちの生き生きとした表情が高く評価された作品ですが、その写真集を作り上げたのは、当時大学病院に勤めていた医師・井上冬彦氏でした。
医師と写真家――この二つの仕事は、一見何のつながりもないように見えます。しかし、井上氏は三十年以上もの長い年月を掛けて、医業と写真家業に本気で取り組み、双方に通じる「癒し」と “いのち”について問い続けてきました。その挑戦は現在も続いています。
二つの視点で「いのちの表現者」を目指す井上冬彦氏に文章をお寄せいただきました。前編・後編に分けてお届けします。
- 目次
-
- 1.プロローグ
- 2.「好きなことは趣味に」と医師の道へ
- 3.サバンナへの旅立ち
- 4.通い続ける理由
- 5.最初の転機 ―医療と写真の融合―
プロローグ
内科臨床医を続けながら、三十年以上東アフリカの大自然に向き合い、写真・表現活動に取り組んでいる。
きっかけは、「動物学者になってアフリカの大地に立ちたい」という子どもの頃の夢だった。医師を志したために、その夢を一時あきらめた私が、初めてアフリカのサバンナを訪れたのが三十二歳。この旅が人生を変えた。
当初は思いもしなかったプロの写真家になり、生命の表現者を目指すようになっていった。やがて、医師と自然写真家、この二つはともにかけがえのないライフワークとなり、お互いが影響を及ぼしながら進化してきたように思う。
振り返れば、幸運だったと思う。だが、ここに導いてくれたのは私の中の“負のエネルギー”だった。弱さ・未熟さがもたらした様々なストレスがなければ、今の人生はなかったはずだ。
「好きなことは趣味に」と医師の道へ
赤面症・あがり症で人付き合いが苦手だった少年時代。楽しみは、昆虫採集や魚捕りだった。
中学生の頃のお気に入りは、自然の映像をとらえた本やテレビ番組で、その頃から動物学者になってアフリカの大地に立つことに憧れ始めた。
当時、自然好きの父の書斎で見つけた古典的名著・クシーメックの『セレンゲティは滅びず―地上最後の野生王国』。何度も読み返しては、サバンナとそこに生きる動物たちに思いを馳せていた。
開業医の両親は、医師を目指すことを勧めた。だが、人と接するのが苦手な自分に務まるわけがないではないか……。「他の道はありえない」と決めつける親に反発し、高校二年までは漠然と自然関係の仕事に就きたいと思っていた。しかし、医師に対する憧れがなかったわけではない。不安が勝っていただけなのだ。大学受験の頃には、多少の迷いがあったが、気持ちは医師に傾き始めていた。
最後に決断させたのは、挑戦せずに医師への道から逃げるのを潔しとしなかったこと、そして医師をしながら蝶の採集を終生の趣味にしていた父の「自分の一番好きなことは趣味にしろ」という言葉だった。
サバンナへの旅立ち
医学生時代も人と交流するより自然の中に入っていくのが好きだった。
物事を始める時はいつも神経質になりすぎ、嫌なことからはいつも逃げたいと思う弱い性格を克服できずにいた。
志望科を決める時も、一時は基礎医学に行こうと考えた。が、これも逃げなのだ。内科医を目指したかったが「患者さんとうまく接することができない」と思い込んでいた。迷った末に、内科の研修だけは受けてみよう(当時は二年間)と決断したが、不安は杞憂だった。最初の半年で、大切なのは、上手に接することではなく、熱意だと分かり、すぐにやりがいのある素晴らしい仕事だと感じられるようになっていった。
だが、甘くはなかった。大学病院での研修が終わり、医師として独り立ちするとともに、安易な対症療法では満足せずに、より本質を求めようとしすぎる自分と、その実現にはあまりにも弱い心身とのギャップに葛藤が始まっていった。激務の中でたまっていくストレス。それを発散するために医療以外で何か打ち込める趣味を探していた。釣りやダイビングにも凝ってみたが、どれも中途半端に終わった。子どもの頃に憧れたアフリカはあまりに遠く、長期の休みをとることも難しく、訪れる機会は来なかった。
念願かなって初めてアフリカ・サバンナを訪れたのが三十二歳。病棟の勤務が終わり、学位論文を書き上げ、内視鏡室専属になった時である。
当時は、仕事の苦悩をはるかに超えた家族の心の病というストレスを抱え、自分ではどうしようもない無力感に包まれていた。心労が重なり、医療にも十分に打ち込めず、いつも沈みこんでいた。そのような状態での旅立ちだった。
旅は十一日間のごく普通のパッケージツアーだったが、初めて見たケニア・サバンナの自然は鮮烈だった。
連日深い感動に包まれ、心身ともに癒されていった。
なんだろうこの解放感は……。
広大な大草原と目まぐるしく変化していく美しい光。
暑さを癒すさわやかな乾いた風。
死と表裏一体の生を謳歌する動物たちの命の輝き。
動物親子の無償の愛の姿に触れるたびに心が温かくなっていった。

画像1 ライオンの家族
この時、私の中で湧き上がってきたのは「この感動を伝えたい」という強烈な想いだった。しかし、その術がなかった。父から借りたカメラで表現しようと思ったが、帰国後に期待しながら見た写真(当時はフィルム)は失敗作ばかり。感動の伝わるような写真など一枚もないではないか……。
悔しくて、半年後に再び挑戦した。周囲からは「また行くのか」と批判されたが、気にならないほどのめり込み始めていた。
通い続ける理由
二度目のアフリカは、憧れのタンザニア・セレンゲティ国立公園を訪れるツアーだった。今度は、自分のカメラとレンズを買って臨んだが、意気込みとは裏腹に、今度も失敗作ばかり。それから独学で写真を勉強し始めた。医学もそうなのだが、基本は習っても、それ以上は自分のオリジナリティにこだわるのが私の流儀。自分の失敗作を何度も眺めては研究した。その頃市場に出始めたオートフォーカス一眼レフカメラは、技術のない私の強力な武器になってくれたように思う。
また、お目当ての動物を見せるために移動を繰り返すツアー旅行の限界も感じ、自ら旅の計画を立てるようになり、その成果は少しずつ表れ始めた。
当時描いた三つの夢がある。大きなギャラリーでの個展(厳しい審査を通る必要がある)、出版社から依頼されて作る写真集、そして海外での出版だった。当時の実力からすると荒唐無稽な夢だったことは間違いない。写真仲間からは「冗談だろう?」と笑われていたが、何かに突き動かされるようにサバンナへ通い続けた。
大学病院の激務の中で長期休みをとるための調整や周囲への気兼ね、出発前・帰国後の忙しさ、それに費用の工面など、通い続けることは簡単ではなかった。それでも行き続けようとするエネルギーは尋常ではなかったように思う。今思えば、深刻な家族の問題に向き合うため、そしてそのような状況でも医療を続けていく力を自然の中でもらっていたのだろう。当時は意識していなかったが、癒され、元気をもらうために通っていたことは間違いない。帰国後も次の旅を夢想し、計画を立てることで現実のつらさを忘れようとしていた。その負のエネルギーがなければ、当時の状況で通い続けるなんてありえなかっただろう。とっくにやめていたはずだ。
最初の転機 ―医療と写真の融合―
最初の転機は、サバンナに八年間で十五回通った成果を発表した初の個展だった。プロへの登竜門とも言われる会場の審査を通過して行われた大規模写真展。一つ目の夢の実現だった。新聞等が紹介してくれたこともあり、まったく無名の素人写真家の個展に連日千人近くの方が来てくださった。
「感動を伝えたい」との想いで開催した写真展。会場でそれが伝わった喜びに浸っていたが、それだけではなかった。ある編集者から写真集の打診があり、翌年には第二の夢であった写真集が出版されたのだ(画像2)。さらにその本によってアマチュア作品の最高賞である第六回林忠彦賞を受賞することができた。アマチュア写真家にとってこれほどの名誉があるだろうか。まったく無名だった私が写真家としてデビューすることになったのである。
さらにうれしかったのは、多くの方々からいただいた「癒された」「元気になった」「今日一日幸せになりそうです」といった感想文だった。
当時は大学病院に勤めていたが、安易な対症療法や症状・病気しか診ない医療に疑問を感じていた。症状は体からのメッセージであり、安易な対症療法ではなく、その意味を読み解き、原因を究明し、それを解決することで病気の治癒を目指すべきではないか……。一時的な対症療法は必要だが、その薬を必要としなくなるように導くのが本来の姿だと思っていた。また、最終的に治すのは自分の治癒力であり、それを高めるには癒しが必要なはず。しかし、その想いとは裏腹に、忙しすぎる過酷な医療現場と自らの心身の弱さ・未熟さから、実現の困難さにジレンマに陥っていた。
そのような時に開いた初の個展で、多くの人が写真を観て元気になり、癒されていく姿を見た瞬間、光明が差し始めた。自分の医療の欠落部分を写真で補えるかもしれない……。この瞬間、写真と医療がリンクし始めたのである。
これが大きな転機となり、「人を癒す写真とは何か」について考えながら再びサバンナへ通い続けるようになった。そして三年後におこなったのが写真展「サバンナに心癒されて」。以後、様々な医療施設や学会で「癒しの環境づくりとしての写真展」を開催してきた。そのたびに同様の感想をもらうだけでなく、写真集を観た病気の方々からも「元気になった」「食事ができるようになった」等の手紙をたくさんいただいた。この反応は私を深く癒していった。
このような経験を経て気付いた、とても大切なことがある。それは、自らを癒す大切さと、人を癒す行為が自らを深く癒すということだった。以後、私の興味はますます癒しと医療の関係、人を癒す写真とは何か、に移っていった。
*
後編に続く。
【関連記事】
・「看取りの現場には『あったかい死』がある ~その先にみえた、いのちのつながり~」國森康弘氏(写真家・ジャーナリスト)
・「小説家として“等身大の医療”を伝える」久坂部羊氏(小説家/医師)
・「医師としての存在価値を肯定できる場所から~『リアル』を求めた海外ボランティアで“医療に対する謙虚さ”を学ぶ~」石田健太郎氏(産婦人科医)
- 井上 冬彦(いのうえ・ふゆひこ)
- (医)井上胃腸内科クリニック理事長・院長。日本内科学会認定医、日本消化器病学会認定専門医、日本消化器内視鏡学会専門医・指導医。
1979年東京慈恵会医科大学卒後、1992年同大学第三病院内科講師。恵仁会・松島クリニック診療部長を経て2005年井上胃腸科・内科クリニック(現・井上胃腸内科クリニック)を開院。
1996年に写真集『サバンナが輝く瞬間(とき)』を出版し第6回・林忠彦賞を受賞。クリニックの院長を勤める傍ら、複数の写真集を出版するなど自然写真家としても精力的に活動している。いのちの表現者を目指し、2018年7月、初の写文集(写真絵本)『マイシャと精霊の木』出版。

- 『マイシャと精霊の木』
- 写真・文:井上冬彦
発行所:光村図書出版
発行日:2018年7月20日 初版第1刷
内容:
自然界は弱肉強食といった単純な図式ではなく、もっと複雑なバランスの上に成り立ち、われわれが思っている命は大きな生命の一部を見ているにすぎません。
本書は、この哲学的で難解なテーマを、マサイの少年マイシャが精霊の木との対話のなかで学んでいく寓話形式で表現し、子どもに分かる内容に昇華させています。
読後には、きっと新しい自然観、生命感を得ることができるでしょう。
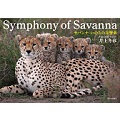
- 『Symphony of Savanna』
- 写真:井上冬彦
発行所:新日本出版社
発行日:2016年12月 初版第1刷
内容:
生命とは何か。
その深い思想に裏付けられた精緻な写真には、動物の生態写真を超えた何かを感じる人がたくさんいます。
サバンナの美しい光景とそこに生きる生き物たちが発する無言の声から、深遠な生命の意味を感じてみてください。





 公式SNS
公式SNS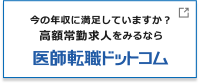
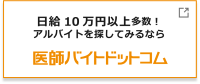


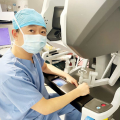













コメントを投稿する