看取りの現場には「あったかい死」がある ~その先にみえた、いのちのつながり~
國森 康弘(写真家・ジャーナリスト)

「おーい、息が止まったぞー」
息子さんの声に、家の裏手から娘さんが駆け付けてきた。老いた母の手を握る。
「おばあちゃん!」
息が止まって何十秒かは経っていた。「おばあちゃん、おばあちゃん……」。娘さんの呼びかけに応えるように、母はもう一度、息をし始めた。
それを確かめた娘さんが、両手で母の手を握り直して、言った。
「おばあちゃん、ありがとう。……もう、ええよ」
お迎えが来ているのなら、もうゆっくりしていいのよ。娘さんの言葉に安心したかのように、母は完全に呼吸を終えた。
息を引き取ったその目からは、涙がこぼれていた。生きてきたほぼすべての時間を過ごした集落の自宅での、「大往生」だった。
看取りの場に満ちた「あたたかな空気」
娘さんは、認知症が深まり老衰が進む母を心配し、自分の家に呼び寄せたりしたが、最終的には母の希望通り自宅に戻ってもらった。
亡き母のその涙を見て、娘さんは「ああ、おばあちゃん、これでよかったんやね」とぼろぼろと泣きながら、ほほ笑んだ。「おばあちゃん、ありがとう」。孫やひ孫、ご近所さんも寄り添った。
「あのとき悲しかったけど、あったかいものがそこにあった。満足感というのか……母が大事なものをくれた気がする」と、娘さんは振り返る。
看取りの場には、死別の悲しみ、辛さだけでなく、充足感、もっと言えば生きる力を感じさせるような、厳かであたたかな空気が満ちていた。
つながれていたはずの、たくさんの「いのち」があった

"We will kill you, if you don't leave this city now."
ごった返す市場で、ふいに後ろから男に告げられた。振り向いたが、押し寄せる人の波で、相手が誰か見分けが付かなくなった。2003年当時、ソマリアの首都モガディシオには、アルカイダを含む30の武装組織が割拠していた。
かつてイギリスとイタリアから保護領にされたあと、米ソ冷戦の波にのまれ、90年代には米軍らに軍事介入される。平均寿命50歳前後、無政府状態で、内戦が今日まで続く「崩壊国家」。失業率は9割ともいわれ、家族を養うために仕方なく、武装勢力や海賊に加わる者も少なくない。長引く紛争で病院は機能せず、治療を受けられずに死んでいく乳幼児がいた。
銃撃や爆撃に巻き込まれた子、栄養失調に陥った子……。イラクでも、スーダンでも、子どもたちが目の前で死んでいった。亡き子を抱く、親の慟哭が胸にこだましている。
「私たちの悲しみを、日本の人たちに伝えてほしい。どうか、戦争を止めてほしい」
そう言われた。
戦争や貧困という人災がなければ、この子たちはもっと生きられたはず。この子たちの多くが大人になって、結婚して、子どもを授かったり、養子、里子を育てたりして、いのちをつないでいたはず。
悲しみを感じながら、その死を報じてきた。
「つめたい死」から「あったかい死」の現場へ

いのちのバトンリレーがブチリと断ち切られる「つめたい死」の現場を伝えながら、いつしか、別の死を見据えるようになった
あったかい死――。冒頭の母娘のように、住み慣れた場所で、大切な人に寄り添われながら、授かったいのちを生き切る、天寿まっとうの営み。
あの母は滋賀県東近江市の永源寺地域の集落で、認知症を抱えながら、1人暮らしを続けてきた。医療介護福祉の専門職の連携があり、家族の通いがあり、そしてご近所さんたちの毎日の寄り添いが、そこにあったから。
その1人、永源寺診療所の花戸貴司医師は、白衣を着ない。白衣は壁をつくりかねない、と。「医者1人にできることは限られている。格好つけず、地域の一員としてともに生き、みんなで地域づくりをする」。そんな決意のあらわれだ。
元々は脳卒中連携パスの連携会議として始まった東近江医療圏の「三方よし研究会」は月1回の頻度で、このほど100回を突破。全国から注目を浴びる。その地域版「チーム永源寺」も盛んだ。
いずれも花戸さんら、医療介護福祉の専門職の参加はもちろん、消防隊員、警察官、図書館の司書、寺の住職、教育者、行政職員、商工関係者、民生委員、ボランティアなど、その輪はどんどん広がり、「まちづくり」――病気や障がいを抱えていても、安心して、自分らしく生き抜けるまちづくり――の要の1つになっている。
天寿をまっとうできることの「あたたかさ」を伝えたい
1人ひとりのいのちには、生きとし生けるもののいのちには、必ず終わりがくる。致死率100%。100年生きる人もいれば、幼くして病で亡くなる子もいる。老いや死そのものに対しては、医療で抗うことはできない。
ただ、死の先には続きがある。残る者が、亡き人の分も、大切にいのちを次につないでいく、という続きが。私たちは死ぬからこそ、いのちをつなごうとするのだ。
天寿をまっとうする、あたたかさ――。私たちはまずこれを知り、そして、目指すのではないか。自分や身近な人だけでなく、イラクやソマリア、シリアの子どもたちも、誰もが授かったいのちを生き切り、まっとうできる世を実現させようと心を砕くのではないだろうか。
涙のなかに、笑顔がある。あたたかい看取りの先に、いのちのつながりが見える。
そんな「いのちのうみ」を、医師を含む誰もが感じ取りながら、そして各々の専門性を持ち寄りながら、天寿まっとうの「世づくり」をともにできればと願っている。
【関連記事】
石田健太郎氏(産婦人科医)「医師としての存在価値を肯定できる場所から ~ 「リアル」を求めた海外ボランティアで“医療に対する謙虚さ”を学ぶ」
- 國森康弘(くにもり・やすひろ)
- 兵庫県生まれ。京都大学大学院経済学研究科、英カーディフ大学ジャーナリズム学部修士号取得。
神戸新聞記者を経て、イラク戦争を機に独立。写真家・ジャーナリストとしてイラク、ソマリア、スーダン、ウガンダ、ケニア、カンボジアなどの紛争地や経済貧困地域を取材。国内では戦争体験者や野宿労働者、東日本大震災被災者のほか、近年は特に看取り、在宅医療、地域包括ケアの撮影に力を入れる。



 公式SNS
公式SNS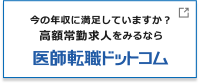
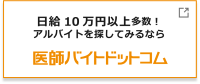

















コメントを投稿する