アメリカの医療安全を大きく変えたダナ・ファーバー事件
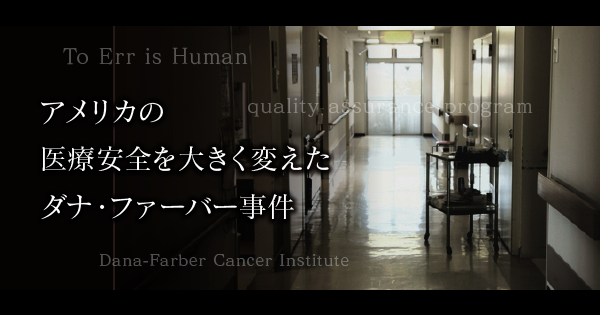
アメリカで医療事故に対する組織的な責任を問う動きが注目されるきっかけとなった、ダナ・ファーバー事件。世界トップレベルの医療機関で起きた二十数年前の事故は、米医療界の意識を大きく変えました。今回はダナ・ファーバー事件を起点に、米国の医療事故対策や、医師の過失責任に対する考え方の変遷を紹介。あわせて、日本における医療安全の歴史も辿ります。
ダナ・ファーバー事件の発生原因と事故後の対応
治験中に起きた死亡事故
1994年、アメリカ。ハーバード提携機関のダナ・ファーバー癌研究所(以下、ダナ・ファーバー)で患者1名が死亡、1名が心不全になる医療事故が発生しました。
記者をしていたベツィー・リーマンと元小学校教師のモーリーン・ベイトマンは、自身の乳がんが転移したことでダナ・ファーバーの治験に参加していました。大量化学療法によって行われていた治験が3クール目に差し掛かったとき、ベイトマンは副作用によって心不全を発症。近接する病院のICUに転送され、蘇生処置を受けたことで一命を取り留めました。
一方、リーマンも副作用の影響を受け入院しましたが、程度が軽かったため退院する予定となっていました。しかし退院の前日に容態が急変し、蘇生処置を施されるも、そのまま帰らぬ人に。後に、2人には抗癌剤のサイクロフォスファミドが予定量の4倍も過剰に投与されていたことが分かったのです。
事故はヒューマンエラーの連鎖で発生
事故の存在が発覚したのは、リーマンが死亡してから2カ月も後のことでした。施設の職員が治験データを整理していたときに、誤った量の抗癌剤が投与されていた事実を知ったのです。
悲劇は、治療プロトコールの曖昧な記載から始まりました。担当医でフェロー2年目のジェームズ ・M・フォランはプロトコールの記載を読み違え、4日間で投与すべき治療薬の分量を1日分と誤解。その結果不適切な処方箋を作成してしまいました。
薬剤師のキャロリン・A・ハーベイは、治療の3クール目が開始してから投薬の量が多いことに疑問を抱き、フォランに連絡を取りました。フォランとハーベイは、あらためて治療計画書を確認したものの、治験で計画されている量なのだろう、という結論に至ったのです。
全20ページにわたるプロトコールの1ページ目には要約があり、確かに誤解し得る記載がされていました。11ページ目には1日分の量が明記されていたものの、担当医の目に触れることはありませんでした。
その後も、オーダーに確認のサインをした医師、抗癌剤の投与を担当した看護師など、診療に関わった約25名の職員の誰もが誤りに気付きませんでした。
血液検査での異常値が臨床試験用にのみ記録され患者カルテには記載されなかったこと、病棟にプロトコール冊子がなく看護師が誤りに気付けなかったこと、投薬量の確認や医師と意見が食い違った際の投薬拒否といった看護師の義務が職務規定に記載されていなかったことなどから、医療者間の相互チェックがなされず、患者は亡くなってしまったのです。
事故が発生した背景には、医療者個人のチェックの不十分さが挙げられます。しかしそれ以上に、エラーの連鎖を引き起こす、リスク管理システムの構築を怠った組織側に問題がありました。
機能していなかった医療安全対策
事故の発覚後、ただちに内部調査委員会が発足。さらに、外部識者を長とする原因調査委員会が設置されました。そして、過剰投与に至ってしまった原因究明として、病院の管理システムと情報伝達システムの問題点の洗い出しが行われたのです。
さらに、事件を報じたボストン・グローブ紙の一面記事をきっかけに、州当局や医療機関の審査格付けを行う医療施設評価合同委員会(JCAHO)も緊急査察を実施します。
州当局は査察の結果、10数点の組織上の欠陥を指摘し、特に医療の質を保証する「組織的な取り組みの欠如」を問題としました。
実は州当局やJCAHOは以前から、医療現場で問題が発生した際の原因究明と改善(QAP:quality assurance program)を義務付けていました。しかし、ダナ・ファーバーではQAPが全く機能していなかったのです。
また、JCAHOも、患者からの強い副作用の訴えにも関わらず対処がなされなかったことを問題とする調査結果を発表。看護師の責任を軽んじる組織体制が問題視されました。
ダナ・ファーバーは州当局やJCAHOの指摘を全面的に受け入れました。QAPを改善し、医療の質を守るためのフィードバック体制を機能させ、看護師の権限を強める等の組織体制の改善など、計39の再発防止策を発表したのです。
メディアに大きく取り上げられ、社会や医療界が注目
ダナ・ファーバーが再発防止の努力を続ける間、事件は州当局やJCAHOを動かした記事以降、何度もメディアに取り上げられることになります。ボストン・グローブ紙などに3年間で28回も記事が掲載されるなどして、事件はアメリカの医療界だけでなく社会全体から注目されました。こうした医療事故は、実はダナ・ファーバー以前も多数発生しており、中には訴訟にまで発展したものもあります。アメリカでは70年代以降、医療過誤訴訟の保険料が高騰。医師達はリスクマネジメントの重要性を認識し、医療安全対策が進められていました。しかし一方で、「医療従事者は誤りを犯さない」という考えが医療者側・患者側双方に浸透していたこともあり、訴訟を恐れ、医療事故がもみ消されるケースなどもあったようです。
事件をメディアが大きく扱ったのは、ダナ・ファーバーが当時世界最高レベルの医療機関だったことだけが理由ではありません。亡くなったリーマンはボストン・グローブ紙で健康・医療部門の記者を務めていました。同僚記者が報道したことで、世間の関心を集めることになったのです。
医療事故の根本的原因は「個人の過失」から「組織の課題」の時代へ
ダナ・ファーバー事件が明るみになった1995年は、タンパ市の切断足取り違え事件が発生した年でもあり、社会的に医療界への不信感が高まっていた時期でした。
これらの事故や世論の高まりを受け、JCAHOは「警鐘的事例」(医療事故)の事例収集と防止に乗り出します。事故が起きる根本的原因には、必ず組織あるいは運営上の体系的欠陥があるという前提に基づき、医療機関の審査に、警鐘的事例の報告と原因分析、再発防止の取り組みに関する項目を追加。医療機関に事故の原因分析を行うことを義務付けました。また、アメリカ医師会(AMA:American Medical Association)もそれまでの「医療過誤は例外的事象」という姿勢を変え、「医療過誤防止のためには、組織的・体系的な取り組みが必要」だとして、関係機関とともに全米患者安全基金(NPSF:National Patient Safety Foundatio)を設立します。
リーマンの死から2年後の1996年に、イェール大学癌センターのデビッド・フィッシャー博士が発表したダナ・ファーバー事件の影響に関する論文によると、アメリカの癌専門医療施設の7割以上が、事件の報道を機に抗癌剤の誤投与を防ぐシステムの導入や見直しを行ったといいます。
1999年、米国医学研究所(IOM:Institute of Medicine/現・米国医学アカデミー)は「To Err is Human」(邦訳『人は誰でも間違える』)と題する委員会報告を発表。医療事故防止の取り組みの強化を宣言しました。この宣言を受けて、米国連邦政府は「省庁間横断・医療の質改善タスク・フォース(QUIC)」を設立。アメリカ合衆国における具体的な医療事故対策の方向性が示され、連邦政府が管轄する医療保険・医療施設において医療事故防止施策が実施されていきます。
ダナ・ファーバーが事故後に医療過誤防止に真摯に取り組み医療体制を大規模に見直したことにより、アメリカ全体の病院管理基準が変化。かつて医療者個人の過失責任として扱われていた医療事故が、事件をきっかけに組織の課題として捉えられるようになり、ダナ・ファーバー事件は、制度の必要性を裏付ける上で教訓的な出来事となりました。
ダナ・ファーバー事件を起点にして、アメリカの医療安全に対する意識が変わったのです。
日本でも始まった医療事故を防ぐ取り組み
きっかけとなった2つの事故
日本でも、1999年に発生した2つの事故をきっかけに、医療安全が注目されることになります。
1.横浜市立大学の事故
手術時に2名の患者を誤って入れ替え、双方に予定と異なる手術を施してしまった事故。事故が発生した直接的な原因は、看護師が2名の患者を手術室へ同時に移送したために、受け渡しを誤ってしまったことです。移送後も麻酔担当医・執刀医ともに入れ替わりに気付かず、手術が実施されてしまいました。事故の発覚は手術が終了し、患者をICUで観察しているときでした。
2.都立広尾病院の事故
入院患者に誤った投薬をしたことで死亡させてしまった事故。患者は関節リウマチを治療するために入院しており、その手術の翌日に事故が発生しました。看護師が他の患者に投与する予定の薬を誤って注入したことが、原因だと推定されています。
日本で起こったこの2つの事故は、処置に関わった医療者のエラーで引き起こされたとともに、ミスを誘発する組織のシステムも原因にありました。こうした組織の欠陥は、ダナ・ファーバー事件の状況とよく似ています。
新たに始まった医療事故調査制度
横浜市立大学と都立広尾病院の事故は多くのメディアによって報道されました。その後、日本の社会における医療安全への関心が高まり、警察への医療事故の届出が増加することとなりました。
こうした状況を受け、厚生労働省は2001年、医療安全対策検討会議を発足させたほか、医療機関などから医療事故事例(ヒヤリ・ハット事例)の収集を開始。国による医療安全の取り組みの一歩を踏み出したのです。
その後、2014年の医療法一部改正により、医療の安全確保を目的とした「医療事故調査制度」が創設。2015年10月に施行されました。
組織の課題として医療事故を調査・分析し、再発防止のための安全管理の体制を確立させる仕組みが、ようやく日本でも構築されたのです。
悲しい事故に学んだ現在の医療安全対策
アメリカ、日本ともに、医療事故を医師個人の過失ではなく組織のシステムエラーと捉え、過去の事例に学ぶ仕組みが作られたきっかけは共通で、医療事故の存在が公になったことでした。時期もほぼ同じ、1990年代のことです。契機となった事故が組織の不十分な危機管理体制に起因していたという点も類似しています。
アメリカと日本で医療安全の取り組みが始まった背景には、悲しい事故と、その事故に真摯に向き合い再発防止に取り組んだ、医師を始めとする医療従事者や関係者たちの存在があったのでした。
(文・エピロギ編集部)
<参考>
・李啓充「連載 市場原理に揺れるアメリカ医療【番外編】ダナ・ファーバー事件(1)」(医学書院)
・李啓充「連載 市場原理に揺れるアメリカ医療【番外編】ダナ・ファーバー事件(2)」(医学書院)
・李啓充「連載 市場原理に揺れるアメリカ医療【番外編】ダナ・ファーバー事件(3)」(医学書院)
・李啓充「連載 アメリカ医療の光と影(13)医療過誤防止事始め(7)」(医学書院)
・李啓充「連載 アメリカ医療の光と影(14)医療過誤防止事始め(8)」(医学書院)
・李啓充「連載 アメリカ医療の光と影(18)医療過誤防止事始め(12)」(医学書院)
・李啓充「連載 アメリカ医療の光と影(19)医療過誤防止事始め(13)」(医学書院)
・医学書院「座談会 ヘルスケアリスクマネジメントの現状と課題」
・浦島充佳「〔連載〕How to make <看護版>クリニカル・エビデンス〔第20回〕崩壊するプロ組織(2)」(医学書院)
・浦島充佳「〔連載〕How to make <看護版>クリニカル・エビデンス〔第21回〕崩壊するプロ組織(3)」(医学書院)
・黒川清、児玉安司「医療の安全性 "To Err is Human" 」(月刊学術の動向『医療の安全性 "To Err is Human"』(財団法人日本学術協力財団 2000年2月号 PP.6-13)
・増成直美「投薬過誤事件における医療従事者の法的責任 -抗がん剤の投与に着目して-」(日本赤十字九州国際看護大学紀要 第12号 2013年11月)
・古場裕司、畑中綾子、横山織江、村山明生、城山英明「米国における医療安全・質向上のための法システム―情報収集, 行政処分, 安全・質評価の観点から」(社会技術研究論文集 2004年2巻 p.285-292)
・李啓充「特別講演 米国における医療過誤防止努力」(医療の安全に関する研究会 newsletter No.19 2001.10.15発行)
・浦島充佳「ダナファーバー癌研究所におけるリスクマネジメント・リフォーム」
・日本評論社『人は誰でも間違える より安全な医療システムを目指して』
・厚生労働省「主な医療安全関連の経緯」
・横浜市立大学医学部附属病院の医療事故に関する事故対策委員会「 横浜市立大学医学部附属病院の医療事故に関する中間とりまとめ報告書」
・日本医療安全調査機構「沿革」
・都立病産院医療事故予防対策推進委員会「都立広尾病院の医療事故に関する報告書 ―検証と提言―」
・岸友紀子「『医療過誤』から『医療事故』に新聞報道はどう変化したかデータベースを用いて日本の新聞における医療事故報道の変遷を研究」(m3.com)
・増成直美「投薬過誤事件における医療従事者の法的責任 -抗がん剤の投与に着目して-」(CiNii)
・寺田暁史「医療事故を巡る近年の動向について」
【関連記事】
・「ホスピス・緩和ケアの歴史【前編】」
・「妊産婦の命を守りたい~“手洗い”の創始者 産科医イグナーツ・センメルヴァイスの生涯」
・「弁護士が教える医師のためのトラブル回避術【第17回】|ロボット医療における医師の責任」
・「医師が医療に殺されないために【前編】」鈴木裕介氏(医師/ハイズ株式会社 事業戦略部長)



 公式SNS
公式SNS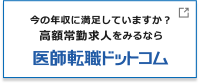
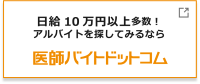

















コメントを投稿する