【医師座談会】「今どきの学会、どう楽しむ?」~コロナ禍を経た学会事情とリアル参加の価値~
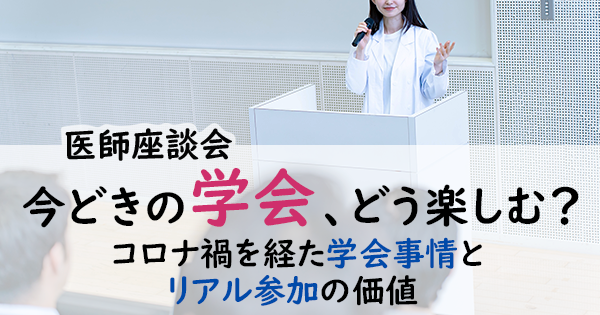
医師の学びの場、そして出会いの場でもある「学会」。コロナ禍を経てオンライン開催が広まり、今では現地とオンラインの “ハイブリッド” 形式も珍しくなくなりました。
そんな今どきの学会事情について、診療科もキャリアも異なる3人の医師が集まってざっくばらんに語り合いました。
前編では、コロナ以降の学会スタイルの変化や、学会期間中の過ごし方、キャリアとの関係、そして懇親会での出会いについて、それぞれのリアルな声をお届けします。
本座談会の後編:【医師座談会】「今どきの学会、どう楽しむ?」~学会ごとのカラーからお弁当事情、懇親会の裏話まで~
座談会参加者の紹介
DIO先生(総合診療医):地方の基幹病院に勤務する総合診療医。内科学会、病院総合診療医学会、プライマリケア学会などに所属し、臨床・教育・研究と多方面に関わる。コロナ禍以降、オンラインやハイブリッド形式の学会に積極的に参加しており、子育てや家庭との両立を図りながら、地方在住でも学会の機会を逃さない工夫を続けている。現地に赴くときは、家族を連れて学会+旅行を楽しむスタイルも。最近では、地域医療と教育の接点に関心を持ち、学生指導や若手医師のキャリア支援にも力を注いでいる。
[X]URL:https://x.com/generection1
チラ先生(呼吸器内科医):市中病院で呼吸器内科を専門とする医師。所属学会は呼吸器学会、内科学会、肺癌学会、結核・非結核性抗酸菌感染症学会、アレルギー学会など多岐にわたる。学会では自ら演題を出すことも多く、常に最新の知見をキャッチアップする姿勢が印象的。特に現地開催を重視しており、ポスター会場でのディスカッションやランチョンセミナーでの臨場感を大切にしている。「現地に行ってこそ学会の価値がある」がモットー。診療におけるリアルな悩みを学会の場で持ち帰り、日常臨床へと還元することを目指している。
[X]URL:https://x.com/mdchin_chiiiira
にことら先生(救急医):複数の急性期病院を経験してきた救急医で、現在は医師としてだけでなく、医療系の企画・運営・教育など多方面で活動。救急医学会、臨床救急医学会、日本災害学会、整形外科学会に所属。現地学会への積極参加はもちろん、企業出展や企画協力など、学会の“裏側”にも精通している。人とのつながりを何より大切にし、「学会はロビー活動の場」と語るその姿勢から、多くの若手医師の相談役的存在にも。交流と実践に重きを置きながら、医療をより良くする仕組みづくりに関心を持ち続けている。
[X]URL:https://x.com/DrNikotora
1. コロナ禍で変わった学会のかたち
司会:まず最初の話題ですが、やはり大きく様変わりしたのはコロナ禍による学会スタイルですね。先生方はどう感じていますか?
DIO先生:以前は「現地参加してこそ学会」という雰囲気が当たり前でした。ところがコロナ以降はオンライン開催が一気に普及し、地方勤務でも気軽に聴講できるようになりました。自宅や病院の空き時間に講演を視聴できるのは本当に助かります。ただ、画面越しでは会場の熱気や一体感がどうしても伝わらない。特に質疑応答のやりとりや廊下での偶発的な出会いはオンラインでは再現できません。便利さと同時に、現地開催ならではの価値を改めて実感しました。
チラ先生:私が参加する呼吸器学会でも、最近は参加者数が戻りつつあります。会場全体の熱量は感じられますが、ポスター会場ではまだ寂しさを感じます。オンライン配信で内容だけを追うのは効率的ですが、やはり現地で人と顔を合わせて議論すると記憶に残りやすいですし、自分の診療のモチベーションにも直結します。
にことら先生:災害医学会などは基本的に現地開催中心のままです。やはり「人と直接話すこと」が学会の目的だからです。オンラインだと知識は得られても、横のつながりや信頼関係は築きにくいからです。運営側から見ても、ハイブリッド開催は費用が倍かかるため、今後はハイブリッド開催から録画配信にシフトする学会も増えるのではないかと感じています。
司会:学会のオンライン化により知識を得るハードルは確かに下がりましたが、地方勤務でも移動せずに参加できるのは大きな利点ですね。
一方で、学会が本来持っていた「場としての魅力」である熱気、偶発的な出会い、直接対話から生まれる議論は、オンラインでは補いきれませんね。つまり、学会は「情報」だけでなく「人と空気」を介して学ぶ場なのだと再認識させられます。今後は便利さと臨場感をどう両立させるかが大きな課題になるでしょう。
2. 「学会に行く」って何をしてるの?学会期間中のリアルな過ごし方
司会:次に、学会は発表を聴くだけではなく、学会中の過ごし方も先生によってさまざまです。皆さんはどのように過ごしていますか?
DIO先生:私は「せっかく現地まで来たのだから観光もしたい」と思いつつ、結局は講演やセッションを回って終わってしまうことが多いです(笑)。ただ、地元の名物を食べるくらいは必ずしています。やはり学会に来ると、日常と違う空気に触れることができるので、学びも頭に入りやすい気がします。
にことら先生:私は逆に観光はほとんどせず、人に会うことを第一にしています。つまり「ロビー活動」がメインです。救急の学会だと毎年同じテーマが繰り返されることも多いので、それよりは久々に会う先生に挨拶して近況を話したり、新しい人を紹介してもらったりする時間が重要です。そこから共同研究や勉強会につながることもあり、演題以上に大切な活動だと考えています。
チラ先生:私は会場によって過ごし方を変えています。近場の学会なら演題を中心に回って帰りますが、遠方なら半日くらい観光を組み込みます。以前、仲間と一緒に参加したときは、発表が終わった瞬間にみんなで打ち上げに行ったこともありました。やはり学会は職場から物理的にも精神的にも離れることができる、数少ない「非日常」の場なので、少しリフレッシュを兼ねて楽しむのも大切だと思います。
司会:学会の過ごし方に「正解」はなく、それぞれの立場や目的に応じたスタイルが存在することが分かります。
演題を聴き込んで知識を深める人、人脈形成やロビー活動を重視する人、あるいは開催地の文化や食を楽しむ人。どれも、その人が学会に何を求めているかの現れです。働き方改革が進む今、「楽しみながら学ぶ」姿勢は、学会の新しいあり方として今後さらに広がっていくのではないでしょうか。
3. キャリア選択に影響を与える学会との出会い
司会:学会はキャリア形成にも影響します。皆さんは具体的にどのような経験がありますか?
DIO先生:私は、学生時代に教育系の学会に参加したことが、自分の研究テーマを考えるきっかけになりました。あのときは「ちょっと面白そうだから行ってみよう」という軽い気持ちでしたが、結果的に後の進路に大きく影響しました。初期研修後には本格的にその学会に参加するようになり、今ではその経験がキャリアの土台になっています。
チラ先生:私は呼吸器内科を選んでから関連学会に参加し始めました。診療経験が広がるにつれて、肺癌や非結核性抗酸菌症など日常臨床に直結するテーマを深く学びたいと思うようになり、自然と参加学会数も増えました。学会を通じて得られる知識は、日々の診療に直結する実感があります。
にことら先生:私は、若手の頃は「上司に言われたから出る」という感覚で参加していましたが、今は「自分の活動にどうつなげるか」を意識しています。特に最近は家族を連れて行くこともあり、託児所の有無や家族向けの企画があるかどうかも重要です。キャリアだけでなくライフスタイル全体に影響を与えるのが学会だと思います。
司会:学会は単なる研究発表の場ではなく、医師のキャリアを方向づける「分岐点」になり得ます。学生時代の小さな関心が後の研究テーマにつながることもあれば、日常診療から専門性を広げる契機になることもあります。さらに、ライフステージに合わせて戦略的に学会との関わり方を変える医師もいます。
つまり、学会はキャリアの「地図」であり「出会いの場」といえます。そこでの体験が人生を大きく動かす可能性があることを、先生方のお話から実感しました。
4. 出会いは懇親会にある?リアル交流の醍醐味
司会:懇親会についても聞かせてください。懇親会での交流が、大きな出会いやチャンスにつながることはありますか?
DIO先生:外部講演の依頼や共同研究に発展したことがあります。普段の診療だけでは出会わない先生と直接つながれるのが懇親会の魅力です。
にことら先生:懇親会は「誰と行くか」が大切です。有力な上司に紹介してもらえると、一気に人脈が広がります。逆に一人で行くと、正直きついこともあります。
チラ先生:私はまだ大きな出会いはありませんが、それでも「いつ何が起きるか分からない場」であることは確かです。名刺交換一つでも、のちの縁につながる可能性があります。
司会:懇親会は、成果が保証される場ではありません。しかし、普段の診療や研究では接点のない人と自然に会話できる「偶発性」が大きな価値になるようですね。紹介や雑談をきっかけに共同研究や講演依頼に発展することもあれば、「まだ大きな成果はない」と感じる人にとっても、次につながるきっかけの芽は確かに存在します。
結局のところ、懇親会は「何が起きても不思議ではない可能性を秘めている場所」と表現できます。その「不確実性」を楽しめるかどうかが、学会での人脈形成を豊かにするポイントとなりますね。
5. まとめ
前編では、コロナ禍で変わった学会のあり方や過ごし方、キャリアに与える影響や懇親会での交流について議論しました。学会は、知識を深めるだけでなく、「出会う」「感じる」「考える」ための大切な時間です。コロナ禍を経てスタイルは変わっても、医師たちが学会に求めるものは変わっていないです。
次回の後編では、それぞれの学会の個性や、ちょっと気になる「お弁当事情」、さらには「学会での異色イベント」についても掘り下げていきます。お楽しみに!
本座談会の後編:【医師座談会】「今どきの学会、どう楽しむ?」~学会ごとのカラーからお弁当事情、懇親会の裏話まで~




 公式SNS
公式SNS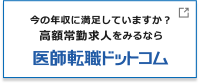
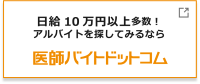


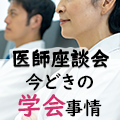











コメントを投稿する