【医師座談会】「今どきの学会、どう楽しむ?」~学会ごとのカラーからお弁当事情、懇親会の裏話まで~
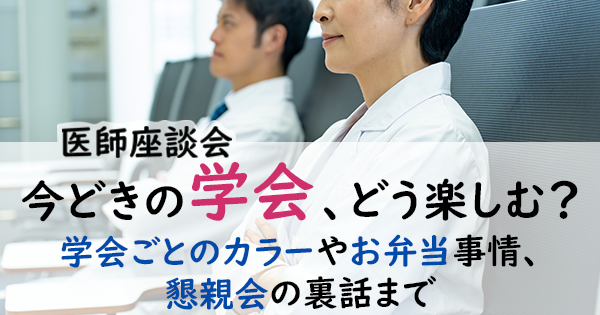
医師にとって学会は、単なる知識習得の場ではなく、人と出会い、文化に触れ、自分のキャリアを考えるきっかけになる大切な機会です。
前編では、コロナ禍で変化した学会スタイルや参加方法、学会とキャリアとの関わりについて取り上げました。
後編となる本記事では、3人の医師がそれぞれの視点から「学会の個性」「お弁当事情」「懇親会やイベントの裏話」について、リアルな体験談を語っていただきます。
本座談会の前編:【医師座談会】「今どきの学会、どう楽しむ?」~コロナ禍を経た学会事情とリアル参加の価値~
- 目次
座談会参加者の紹介
DIO先生(総合診療医):地方の基幹病院に勤務する総合診療医。内科学会、病院総合診療医学会、プライマリケア学会などに所属し、臨床・教育・研究と多方面に関わる。コロナ禍以降、オンラインやハイブリッド形式の学会に積極的に参加しており、子育てや家庭との両立を図りながら、地方在住でも学会の機会を逃さない工夫を続けている。現地に赴くときは、家族を連れて学会+旅行を楽しむスタイルも。最近では、地域医療と教育の接点に関心を持ち、学生指導や若手医師のキャリア支援にも力を注いでいる。
[X]URL:https://x.com/generection1
チラ先生(呼吸器内科医):市中病院で呼吸器内科を専門とする医師。所属学会は呼吸器学会、内科学会、肺癌学会、結核・非結核性抗酸菌感染症学会、アレルギー学会など多岐にわたる。学会では自ら演題を出すことも多く、常に最新の知見をキャッチアップする姿勢が印象的。特に現地開催を重視しており、ポスター会場でのディスカッションやランチョンセミナーでの臨場感を大切にしている。「現地に行ってこそ学会の価値がある」がモットー。診療におけるリアルな悩みを学会の場で持ち帰り、日常臨床へと還元することを目指している。
[X]URL:https://x.com/mdchin_chiiiira
にことら先生(救急医):複数の急性期病院を経験してきた救急医で、現在は医師としてだけでなく、医療系の企画・運営・教育など多方面で活動。救急医学会、臨床救急医学会、日本災害学会、整形外科学会に所属。現地学会への積極参加はもちろん、企業出展や企画協力など、学会の“裏側”にも精通している。人とのつながりを何より大切にし、「学会はロビー活動の場」と語るその姿勢から、多くの若手医師の相談役的存在にも。交流と実践に重きを置きながら、医療をより良くする仕組みづくりに関心を持ち続けている。
[X]URL:https://x.com/DrNikotora
1.それぞれの学会、どんなカラー?
司会:学会は同じ「研究や発表の場」といっても、雰囲気や文化が大きく違います。現場での実感として、先生方はどのように受け止めていらっしゃいますか?また、若手医師が学会を選ぶときに「この学会は自分に合う、合わない」と感じるポイントもあるかと思います。学会を選ぶ際のポイントなども含めて教えてください。
DIO先生:内科学会は日本最大級の学会だけあって、とにかく重厚感があります。全国から専門医が集まり、シンポジウムや教育講演のレベルも非常に高いです。質疑応答も容赦ないので、発表側はかなり緊張しますね。反対に病院総合診療医学会は、臨床現場に直結するテーマが多く、教育セッションも充実していて若手にやさしい雰囲気があります。自分の経験をベースにした発表も歓迎されるので、初めて挑戦する若手医師にとっては「登竜門」として最適だと思います。また、プライマリ・ケア学会は、多職種が自然に交わる場です。心理的、社会的側面にまで踏み込むため、似顔絵コーナーやマッサージブースといった独特な仕掛けまであります。最初は戸惑いましたが、医療を生活や地域と結びつけて考える空気を実感できます。
チラ先生:呼吸器学会は教育的な要素が強く、最新の知見を学びたい若手にとってはありがたい場です。肺癌学会はさらに専門性が高く、討論のレベルも一段と厳しいです。発表者はかなりの準備を要します。結核・非結核性抗酸菌学会は、行政や保健所の方も参加しており、臨床と公衆衛生の視点で議論されるのが特徴です。診療だけでなく、制度や社会との接点を感じられるのはこの学会ならではですね。
にことら先生:救急系も分かれています。救急医学会は重症管理を中心に学術性が非常に高いです。一方で、臨床救急医学会は多職種参加型で、院内チームの運営やコミュニケーションにも焦点が当たります。災害医療学会は、消防や行政、ボランティアなど非医療職も多く参加しており、「社会全体でどう危機に対応するか」を学ぶ場です。立場を超えたディスカッションができるのは貴重ですね。
司会:なるほど。お話を伺うと、「どの学会に参加するか」で得られる経験の質が大きく変わることが分かりますね。大規模で学術性が高い学会では自分を鍛えられる緊張感があり、一方で多職種型や地域性の強い学会では人との距離が近く、横のつながりを築く場としての役割が大きいようです。若手の先生にとっては、自分のキャリアの段階に応じて学会を選ぶことが重要になってきますね。
2.お弁当が美味しい学会はどこ?
司会:少し雰囲気を和らげて、身近な話題に移りましょう。学会といえば「ランチョンセミナー」ですよね。先生方も多く参加されてきたと思いますが、お弁当の印象や地域色など、思い出に残っていることはありますか?
DIO先生:正直に言えば、大きな差はあまり分かりません(笑)。ただ、プライマリ・ケア学会は出店ブースで、地元の特産品やスイーツが販売されていて、食に関しては楽しめますね。学会参加の「ちょっとした息抜き」として、毎回楽しみにしています。
チラ先生:ランチョンセミナーのお弁当は全国共通の業者が多く、基本はどこも似ていますね。ただ、パシフィコ横浜の時に崎陽軒のシウマイ弁当が出たのは嬉しかったです。また、コーヒーブレイクセミナーで地元のお菓子が提供されると、それだけで学会が地域と結びついている実感が湧きます。
にことら先生:ランチョンセミナーは企業が一括で手配することが多いため、正直クオリティに差があります。運営の立場からすると、コストや契約の調整が大変なんですよね。参加者は「お昼を楽しみに」来ていますが、主催者にとっては頭の痛い部分でもあります。
司会:やはり「学会ランチ」は小さな楽しみの一つですね。普段は忙しい診療の合間に立ち食いで済ませることも多い中、ゆっくり腰を据えて食べられるだけで贅沢に感じられます。そこに地元色や工夫が加わると、学会全体の印象にも影響しているようです。運営側からすればコストや業者調整の大変さもある一方で、参加者の体験を形づくる重要な要素ですね。
3.懇親会の裏話と、ちょっと変わったイベントたち
司会:学会のもう一つの楽しみといえば懇親会や展示です。一番学会の個性が出る部分だとも思います。先生方は印象に残った出来事や、「学会ってこんな一面もあるんだ」と感じた経験はありますか?
DIO先生:ディズニーアンバサダーホテルで学会があったときは本当に驚きました。駅を降りるとみんなディズニー客なのに、自分だけスーツ姿で浮いていたのは今でも忘れられません(笑)。非日常感に包まれながらの学会は、ある意味で良い思い出でした。
にことら先生:救急医学会では、懇親会に芸人やアーティストを呼んでいた時期がありました。クールポコや由美かおる、が〜まるちょばを懇親会で見たことがあります。災害学会ではマッサージブースが設置され、学会そのものが「体験型イベント」になっていました。
チラ先生:肺癌学会の懇親会で夏川りみさんのコンサートが行われたこともありました。地方開催だと、その土地の伝統芸能が披露されることもあります。医学だけでなく文化交流の場でもあるんですよね。
司会:まさに「非公式の学び」とも言える場面ですね。講演や発表はもちろん大切ですが、こうした余白の部分で人間関係が広がり、キャリアに影響する出会いが生まれるのも学会の醍醐味。文化やエンターテインメントが加わることで、学会は「知識の場」から「体験の場」へと広がっているように感じます。
4.まとめ
後編では、学会ごとの個性や雰囲気、お弁当事情や懇親会の裏話まで、日常診療の場からは見えにくい一面を取り上げました。
学会は知識のインプットにとどまらず、人や文化との出会いを通じてキャリアや価値観を広げてくれる場です。
コロナ禍を経て、医師たちの「学会との付き合い方」は確かに変わりました。オンラインやハイブリッドの普及によって参加のハードルは下がり、地方や家庭を持つ医師にとってはチャンスが広がりました。一方で、現地ならではの臨場感や偶然の出会いは、オンラインでは代替できないという声も強く、医師たちの学びの場は“情報”から“交流と体験”へと広がりを見せているようです。
今回の座談会では、専門もキャリアも異なる3人の医師が、それぞれの視点から学会の魅力や違和感、ちょっとした裏話まで率直に語ってくれました。「学会は発表だけじゃない」「人と話す時間にこそ価値がある」「お弁当や懇親会も、記憶に残る一部」そんな等身大の声から、学会のもつ多層的な価値が改めて浮かび上がりました。
学会は、知識を得るだけの場所ではなく、「医師としての感性やネットワークを育てる場」でもあります。現地の空気を感じながら新たな誰かと出会い、自分の立ち位置を再確認する、そんな体験が、忙しい日常の中にふとした貴重な時間をもたらしてくれます。




 公式SNS
公式SNS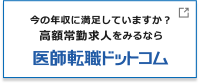
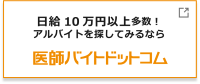


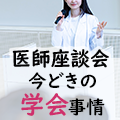











コメントを投稿する