【第7回】明日の記憶~若年性認知症と夫婦の絆の物語
石原 藤樹 氏(北品川藤クリニック 院長)
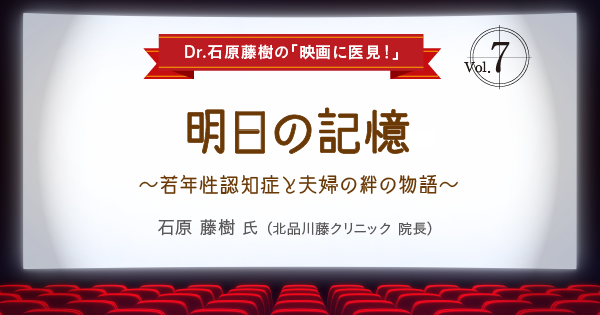
医療という題材は、今や映画を語るうえで欠かせないひとつのカテゴリー(ジャンル)として浸透しています。医療従事者でも納得できる設定や描写をもつ素晴らしい作品がある一方、「こんなのあり得ない」と感じてしまうような詰めの甘い作品があるのもまた事実。
シリーズ「Dr.石原藤樹の『映画に医見!』」は、医師が医師のために作品の魅力を紹介し、作品にツッコミを入れる連載企画。執筆いただくのは、自身のブログで100本を超える映画レビューを書いてきた、北品川藤クリニック院長の石原藤樹氏です。
第6回の『シッコ』に続き、今回は『明日の記憶』をご紹介いただきます。
現役医師だからこそ書ける、愛あるツッコミの数々をお楽しみください(皆さまからのツッコミも、「コメント欄」でお待ちしております!)。
映画『明日の記憶』の概要
今日ご紹介するのは、2006年公開の日本映画『明日の記憶』です。若年性認知症を扱った荻原浩のベストセラー小説に惚れ込んだ渡辺謙が、自らエグゼクティブプロデューサーを務め主役も演じた作品で、公開当時は大きな話題になりました。
大手広告代理店の営業部長として勤務する50歳の佐伯(渡辺謙)は、物忘れと体調の悪さに苦しみ、やがて仕事にも支障を来すようになります。病院の神経内科を受診して、若年性アルツハイマー病と診断された主人公を、それから過酷な運命が次々と襲うのです。仕事が全てのエリートサラリーマンが仕事を失った時、最後に残ったものは何だったのでしょうか? 感動のドラマが待っています。
見どころは主役2人の演技と、感動的な夫婦愛のドラマ
この映画の見どころは、何と言っても主人公の佐伯を演じた渡辺謙とその妻を演じた樋口可南子の演技です。渡辺謙は映画化を自ら熱望しただけあって、認知症と診断された苦悩を全身で熱演。それを支える樋口可南子が素晴らしく、経済的な自立と夫への愛との間に揺れ動く心境を、抑えた演技で巧みに表現しています。自分のことすら理解出来なくなった夫を受け入れるラストのアップは、掛け値なしの名演でした。
原作が発表された2004年当時の認知症に対する世間の捉え方と、実際の診断や治療などの段取りが分かりやすく描かれていることも、一般の方にとっては興味深い点であると思います。
監督の堤幸彦はテレビドラマの独自の演出で人気を集めた鬼才で、どちらかと言えば若者層をターゲットにしたマニアックな作品が多かったのですが、本作は過去の日本映画なども参考にしつつ、より幅広い年齢層の観客に向けた分かりやすい作品に仕上げています。ただ、原作にはない幻想シーンなど監督独自の表現にも取り組んでいて、そのやや誇張された演出などは、好みの分かれるところだと思います。中でも、映画のラストで若い頃の主人公と現在の主人公とが野焼きの窯で一体化する場面は、監督の個性と作品世界とが、見事にマッチしていたと思います。
認知症を演じることは難しい
認知症の人物が登場する映画は沢山ありますが、認知症の患者を主人公にして、真正面から認知症をテーマにした作品は、国内外を問わずそれほど多くはありません。認知症の患者を役者が自然に演じるということはそう簡単なことではありませんし、映画は娯楽として成立しなければいけないので、そのさじ加減が非常に難しいからだと思います。
この作品では渡辺謙が主人公を熱演しています。役者の演技としては優れていると思いますが、認知症をリアルに表現しているかと言うと、疑問が残ります。前半では認知症という診断を認められずに、興奮して医者を怒鳴りつけたり、病院の屋上から飛び降りようとするなど、あまりにオーバーアクトであきれてしまいますし、本当にこんな患者がいたら医者はたまりません。
後半では被害妄想や徘徊、意欲低下による閉じこもりなどを表現していますが、それぞれに力が入りすぎていて、「演じている」という感じがどうしても気になってしまいます。興奮していると体にも力が入ってしまい、動きが力強くなってしまうのですが、実際の認知症患者は心と体がもっとアンバランスなものですよね。多分もっと力を抜いて演じた方が、リアルになったのではないかと思います。しかし、それではおそらく役者としては、やりがいがないと感じる結果になりそうです。この辺りは認知症を演技するということの限界を見た思いがします。
認知症の診断にはまずHDS-R(長谷川式)が使用されていて、その後にMRIと機能性の画像検査が施行されています。今は少なくとも専門科ではHDS-RよりMMSEが主体だと思いますが、2004年当時としては不自然というほどではありません。しかし、初期のアルツハイマー病が想定されているのに3語の想起が全く出来ないなど、結果はやや不自然で誇張されています。また、診察室は大きな机を挟んだ対面式で、神経内科のそれとしては不自然だと思います。本来認知症の診断には、神経所見をとるなどの診察が必要ですが、それが困難な構造になっているからです。
フィクションの認知症から学ぶこと
「認知症」という診断名が使用されるようになったのが2004年で、そのためにこの映画の原作ではまだ「痴呆」という言葉が使用されています。アリセプト(ドネペジル)の発売が1999年で、この映画の時点では治療薬はこの一択でした。映画の背景にあるのはそうした時代です。
映画の主人公は認知症であることを職場に隠して仕事を続けていましたが、それが上司に知れたことで職を失ってしまいます。これは若年性認知症のみの特殊なケースと公開当時は考えられていたと思いますが、定年が延長して高齢者の多くが働くようになった現在では、もっと一般的な問題となる可能性があります。病気を理由とする差別はあってはならないものですが、認知症の進行した状態では多くの仕事の継続は困難となりますから、実際には水面下でのこうした過剰な反応は、なくなることはないようにも思えます。認知症の患者はその病状の初期において、認知症であることを隠そうとして、かえって精神の均衡を崩し病状が進行することがありますが、これも社会の状況の反映であると言えるかも知れません。
私達医師は認知症という病気を、その時点の最新の医学知識において、常に判断しようとしています。ところが一般の人の病気に対する意識は、同じようにアップデイトされる訳ではありません。患者が認知症になることによってどのような世界に身を置くことになるのかは、むしろ映画やドラマを見ることの方が、専門書を読むより学ぶべき点が多いかも知れません。
認知症の映画なんて、と思われる皆さんも、患者にとっての認知症を理解するために、この映画を一度見てみるのはどうでしょうか。最初はツッコミどころ満載に思えますし、事実その通りですが、それこそが実は一般の人にとっての「認知症」なのです。
【関連記事】
・「Dr.石原藤樹の『映画に医見!』【第6回】|シッコ~アメリカの医療制度を徹底的に批判した問題作」
・「小説家として“等身大の医療”を伝える」久坂部 羊 氏(小説家/医師)
・「“医”の道を切り拓く~世界の女性医師たち~【第5回】|近代ホスピスの母 シシリー・ソンダース」

- 『明日の記憶』
- 3,800円(税抜) 発売中
発売元:東映ビデオ
販売元:東映
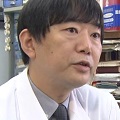
- 石原 藤樹(いしはら・ふじき)
- 1963年東京都渋谷区生まれ。信州大学医学部医学科大学院卒業。医学博士。信州大学医学部老年内科助手を経て、心療内科、小児科を研修後、1998年より六号通り診療所所長。2015年より北品川藤クリニック院長。診療の傍ら、医療系ブログ「北品川藤クリニック院長のブログ」をほぼ毎日更新。医療相談にも幅広く対応している。大学時代は映画と演劇漬け。




 公式SNS
公式SNS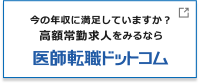
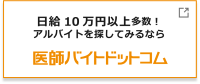




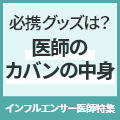
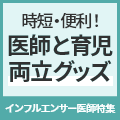


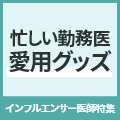











コメントを投稿する