「臨床も研究も、向かう先は同じ」 脳外科から基礎研究に転身した大須賀覚氏が語る、アメリカでの新薬開発
大須賀 覚 氏(がん研究者/アラバマ大学バーミンハム校 助教授)

「ほとんどのがんの基礎研究者は、新薬を一生で一つも作れない」――。自身が携わる研究の道を、大須賀覚氏はそのように語る。
かつては日本で脳神経外科医として、脳腫瘍患者の手術・治療に従事していた大須賀氏だが、その後、基礎研究者に転身。現在はアメリカのアラバマ大学バーミンハム校(UAB)医学部脳神経外科助教授として、脳腫瘍の新規薬剤の研究開発に従事している。
2018年からは研究者の立場から、がん治療に関する情報の発信もしており、4月2日には共著『世界中の医学研究を徹底的に比較してわかった最高のがん治療』(ダイヤモンド社)が出版された。
困難な研究の道に、なぜ、自分の一生をかけるのか。拠点をアメリカに移した理由や海外での研究生活、そして日本語で情報発信を続ける理由とは。一時帰国中の大須賀氏を取材した。
治療法のない患者からの「私は助かりますか」という問い
――大須賀先生は、国内で外科医をされていた当時から研究に興味があったのでしょうか。
私は筑波大学の医学群医学類を卒業し、同大学の脳神経外科に入局しました。7年目に専門医を取得するまでは脳外科医として手術に明け暮れる日々だったと記憶しています。しかし当時から研究がすごく好きで、臨床と並行して臨床研究や基礎研究をしていました。MRIなど脳画像の研究や、脳腫瘍細胞を使ったちょっとした基礎研究だったのですが、その後、だんだんと脳腫瘍研究への興味が強くなっていきまして。
というのも、脳腫瘍は発生部位が脳ですから、どうしても切除に限界があって、悪性で浸潤性のものだと、患者さんを手術だけで助けるのが難しい。「手術だけでは治らない病気」として認知されています。
――その後、基礎研究者に転身されるきっかけは。
患者さんを本格的に診るようになった頃、最初に担当させていただいた若いお母さんのことを今でも覚えています。その方の病気は脳幹部のグリオーマ、非常に予後の悪いがん。手術で切除することもできず、放射線も化学療法も効きが悪い。残念ながら、現行の治療でできることはとても限られている。そんな患者さんをいきなり担当したんです。その衝撃が大きかった。
そのお母さんは当時の私とほとんど同じ年で、小さなお子さんが2人いて。お子さんはお母さんが病気になったこともよく理解できていなかった。そのお母さんに「私は助かるんですか」と聞かれたんです。

「我々にできることはない」なんて言えない。「やれることをやっていきましょう」と言うしかありません。そのとき、「現行治療ではできることがない、それでも自分はこれ(現行治療)をずっとやっていくのか」というジレンマを強く感じました。
なんとか、自分の手で今の治療を先に進める研究をしてみたい。目の前の患者さんを治すことが大事なのはもちろんですが、今は治せない患者さんを治すための治療法を作りたい。それに関わりたい、と思うようになったんです。
――その後は、大学院に進学され、基礎研究を始められたとうかがっています。
そうです。慶應大学には佐谷秀行教授という、がん研究分野で大変にご高名な先生がいらっしゃいます。佐谷先生は基礎研究者として、お薬を作っている方です。その研究室に大学院のときにお世話になっていて、初めて本格的な基礎研究を体験して、基礎研究のいろはを佐谷先生から学びました。
実はその大学院に行くまでは、自分でお薬を作りたいとは思っていたものの、一方でそんなことはできないだろう、と思っている自分もいました。実際に使われるような新薬を作るのは大変なことで、いくつもの難関があります。そこまではできないだろうから、せめていつか誰かがお薬を作るためのステップになるような論文を出すために研究をする――研究者には、そんな意識の人が多いかもしれません。当時の私もそうでした。
しかし、佐谷先生のところでは、基礎研究から本当にお薬を作って、臨床試験に持ち込んで……ということをちゃんとやっていた。夢物語でなく、本当にできることなんだ、と思ったとき、あらためて自分でもやってみたいという気持ちになったんです。この道が患者さんにつながっていることを確信できた、と言いますか。
脳腫瘍の研究が進むアメリカへ
――アメリカに拠点を移されたのはなぜですか。
簡単に言えば、アメリカの方が脳腫瘍の研究が進んでいるからです。脳腫瘍の研究に使われる研究資金も多く、研究者自体も大変に豊富です。
――両国間で、具体的にどういった違いがあるのでしょうか。
基礎研究は、分野によって、アメリカが進んでいるところと日本が進んでいるところがあります。脳腫瘍の研究分野については、研究している人が多いのがアメリカである、と言えそうです。
例えば脳腫瘍研究のラボは、日本では一つの大学につき一つくらいしか研究室がない。脳外科のラボが脳腫瘍の研究をしていたりします。一方アラバマだと、脳腫瘍だけを専門に研究室を運営しているところが15程度あるんです。
また、脳腫瘍研究のための資金の規模が非常に大きい。そうすると研究の土壌が豊かになって、技術や知識とか、マテリアルをもらえるチャンスが多くなる。研究で「これが欲しい」と思ったとき、それを持っているラボに行って頼めば「OK!」で済む。スピード感が違いますね。
日本の場合、ラボが少ないことで、何かが欲しくても頼む相手が海外のラボになってしまう場合が多いんです。そうするとまた、マテリアルをもらうためのたくさんの手続きが必要になる。そういった構造上の問題があります。

逆に日本ではメジャーながん、例えば肺がんや胃がんの研究費は大きいです。iPS細胞研究も日本の方が研究費を獲得しやすそうですね。国ごとにお金が出やすい領域に違いがある。脳腫瘍の場合はお金が出やすいのがアメリカだった、というところかと。
――大須賀先生が渡米に至るまでの経緯を教えてください。
博士号を取得して、2014年に渡米しました。アメリカで腰を据えて基礎研究できる道を探して、ポスドクとして米国エモリー大学ウィンシップ癌研究所に所属、研究をスタートしました。以降は同じボスに師事して、2019年10月から現在のUABに移籍しています。
――米国に留学する医師の方はいらっしゃいますが、多くはその後、帰国され、臨床医に戻られます。珍しいキャリアですね。
幸い、筑波大の医局の教授がとても理解がある方でした。私がしたいことは脳外科と切り離されたものではなく、脳腫瘍の基礎研究は脳神経外科の進歩のためにも必要。私がちゃんとキャリアを積めるなら、それは医局のためにもなるとおっしゃってくれて。「戻ってこい」とは言われませんでした。教授をはじめとした医局の皆さんの、ご理解とご支援には本当に感謝しています。
あと、家族の支援があったことも大事だったと思います。おそらく医師が留学するときに困るのは、配偶者にも仕事がある場合に、相手のキャリアはどう形成するか、という問題。私の場合、妻も医師で「二人でキャリアアップしていこう」という前提がありました。一方、実際に留学している人は、配偶者が非正規職になってしまっている人も多いです。さらに、子育ての問題もある。時には家族みんなの方向性がうまく合わなくなってしまうこともある。
それを防ごうと、うちは2人ともキャリアを積めるところを必死に探しました。こうした条件が合う大学を探して、1年半くらい、さまざまなアプローチをしました。結果、妻も一緒にエモリー大学の公衆衛生大学院(MPH)に留学し、現在は米国の政府系機関で勤務しています。妻も一緒にキャリアを積むことができたので、片方に変な負担をかけずに済み、こちらでの暮らしを継続していけているのかもしれません。
アメリカと日本 研究生活の「違い」
――海外で基礎研究をする方の生活がどういったものか、なかなか想像がつかないのですが……。
基本的に、毎朝7時、8時に仕事場に行き、そこから18時、19時まで働いています。これはアメリカにしては長い方ですね。他の方は、朝は同じかもう少し遅めに出てきて16~17時に帰る人が多い。労働時間が短いです。分野や研究の状況にもよりますが。
――日本の脳外科の現場と比較すると、やはり環境は違いますね。
確かに違いますね。私は米国では臨床をしていませんが、聞く限りではアメリカのドクターはそもそも、労働時間が短いです。あとは、夜は家族みんなで時間を過ごすもの、という価値観もあります。
――7時から19時までは、全ての時間を研究に充てられているのでしょうか。
研究と、あとは事務仕事です。研究費の書類を書いたり、共同研究者と話し合う時間を作ったり。そういうミーティングの時間も多いですね。
――研究以外の業務にも時間が割かれているのですね。
書類仕事、特に研究費申請に充てる時間が多いのはアメリカの特徴かもしれませんね。研究費を獲得することの重要性が極めて高いので、日本よりもかける時間が多くなっていると感じます。これは時期にもよりますね。あとは、共同研究者とのミーティングでしょうか。
特に最近の研究は、どんどん分業制になってきています。一つひとつが高度化し、「すべて自分でやる」というのは難しい。「できる人に頼んでやってもらう」が基本です。研究を進めるためにはコラボレーションが必要なので、そのコミュニケーションはしっかりとっていますね。
――言語の壁も大きいかと思いますが、大須賀先生は英語が得意だったのでしょうか。
いえ、本当に不得意でした(苦笑)。大学受験のときから英語が苦手科目で、大学でも「ダメなクラス」にいたほどです。ずっと苦手ですし、今でも1日1時間は英語の勉強をしています。正直、苦労していますよ。

しかし、こればかりはやるしかない。そこで、留学したいと思った頃から英語を勉強し始めました。発音のスクールにも通って。私も年年歳歳、少しずつ学んでいって、今は日常生活には支障はありません。ただし、研究上、特殊なディスカッションをするとか、自分が経験したことのないシチュエーションになると、何を言ったらいいんだ、とはなりますね。
はっきり言ってしまえば、母国語ではない以上、完璧に話せるようになるときなんて来ません。だから、思い切って飛び出すしかない。実際に海外に行ってみるとわかりますが、研究者には英語がネイティブではない人がいっぱいいます。むしろ公用語は「ノンネイティブの英語」だと言われるほどです。物怖じせずにぶつかっていくしかないと思います。
成功の可能性が低くても「新薬開発」に取り組む理由
――現在、取り組まれている研究について、説明していただけますか。
私の研究は悪性脳腫瘍、特にグリオブラストーマを対象にしています。放射線治療や化学療法が効きにくい腫瘍ですが、それはなぜなのか、ということを調べていて。こうした場合、おそらくは正常な脳と脳腫瘍でレセプターとなる分子の発現が違うと考えられます。それをコンピューターで解析して発見する、これが第一ステップです。
そうやって発見した分子をさらに分析し、例えば「どうやらこの分子が放射線抵抗性に関わっていそうだ」とわかったら、その分子を細胞に入れたり、抜いたりする。その結果、細胞が予想されたように放射線抵抗性になるのか、を分析するというのが次のステップ。
そこからは、マウスで試す。動物実験でも同じ結論が得られるかどうか。ここが明らかになれば、その分子の発現を抑える薬を作れば、放射線が効くようになる。
ここまで来たら、最終ステップとして、見つけた治療抵抗性の分子メカニズムを抑える薬を既存薬から見つけてきたり、新たに創薬していきます。最後に、マウスモデルで実際に効果が示されることを確認して創薬の「基礎研究」段階は終了。臨床試験に移ります。
とはいえ、一つの研究だけに取り組んでいるわけではなく、こうした研究を同時に複数、走らせています。その上で「これはうまくいきそうだな」というものが出てきたときに、それを集中して仕上げる、という流れですね。

――基礎研究から新薬が生まれる確率はとても低いともうかがっています。それでも研究に取り組むのはなぜですか。
そうですね……。もちろん、「自分なら絶対に作れる」といった自信があってのことではない、というのは事実です。がんのお薬は、たとえ臨床試験まで到達しても、そこから成功するのは3〜4%。ほとんどのがんの基礎研究者は、実際に患者さんに投与される新薬を一生で一つも作れないんですよ。それくらい、難しい世界です。
おそらく、研究を本気でやったことがある人はみな感じると思うのですが、時としてめちゃめちゃに辛い時期というのがやって来ます。いくらやっても全然いい結果が出ないことが続く。その中で、「じゃあ」といろいろな論文を読んだり、他の人がやっている研究を見学したりすると、他にも同じような壁にぶつかって、何らかの解決策を見つけている人がいる。
彼らの手法や解決策からヒントを得て、新たなアイデアが浮かんできて、自分の課題にもスッとハマって解決して、先に進める瞬間というのがあって。「これはこういうことだったんだ」と真実がわかったときには本当に底知れぬ楽しみがあります。だから、難しい世界でも、続けていられるんですね。
――その楽しみを感じる瞬間は、どれくらいの頻度であるものなのですか。
小さいものから大きいものまで、いろいろですね。「ハマった!」という爽快な瞬間よりも、「どうにもならない……」ということの方が多いですよ。ほとんどそう。でも、1年に何回か、「これは壁を超えたな」と思う瞬間があります。
新薬研究は、もし難しい病気のお薬を見つけることができれば、ものすごい数の人を助けられる可能性がある。それを励みにしていますね。
臨床医も研究者も、ゴールは「患者さん」で一致している
――臨床医と研究者、どちらも経験した大須賀先生から見て、どのような違いがありますか。
それはどういう立場で臨床するか、どういう立場で研究するかによりますね。私の場合、大きく仕事を変えているようで、脳腫瘍にずっと向き合っているのは変わりません。だから、あまり違いがあるとは思っていないんです。患者さんに向かって進んでいるという点では変わっていないので。
もちろん、個別の患者さんに向き合う機会は減っています。臨床の魅力は、人にもよりますが、患者さんに直接、関わって、良くなって帰ってもらうとか、そうした直接的なものですよね。研究で直接、患者さんに関わるのはなかなか難しくなります。そんな環境下で、どうやってモチベーションを保つか、というのが、臨床から研究に移る上では考えるべきポイントかもしれません。

私にとって研究の楽しさとは、自分でいろいろと考えて、悩んで、あれこれ試して……とやりながら、物事の真理を発見するところ。最終的なゴール地点は患者さんで一致するのですが、どのような経路を辿るのか、ということだと思います。
――アメリカで研究をしながら臨床もするというのは、さすがに現実的ではありませんでしたか。
そうですね……。脳外科の場合は科の特性上も非常に難しいかもしれません。そもそもアメリカで臨床を本気でやりたいと思うと、レジデント(研修医)からやり直さないといけない。そこからさらに(アメリカの)脳外科医として経験を積むので、また一人前になる頃にはいくつになってしまうのか、という問題があります。
もう一点、基礎研究もかなり高度化し、臨床の片手間でできるものではなくなっている、ということもあるでしょう。世界の他の基礎研究者と戦おうと思うと、臨床後の夜中に頑張ればできる、という世界ではない。私もやはり、「本腰を入れてやりたい」という想いで、臨床医から研究者になりました。
――新薬開発をする上で、臨床の経験は生きていますか。
それは絶対に生きます。医学研究というのは何のテーマでもそうですが、基本的に「患者さんが困っていることを解決する」ためのもの。それができる研究が価値のある研究です。
そうなったときに臨床家が強いのが、実際に医療現場で問題になっていることを熟知していること。解決するべき問題を捉えやすいんです。あまりに臨床を知らない人だと、サイエンスとしてはいいのですが、実際の人の困りごとを解決できないことがある。もちろん、すべてのサイエンスに意味が必要なわけではないのですが、医学にとってはやはり人がゴールであると、私は思います。実際、患者さんの治療につながらないものは研究費も獲得しにくいですしね。
だから、臨床家が基礎研究もするというのが理想ではあります。しかし、日本でそれをするのはとても難しくなっています。これは悲しいことでもありますね。医師はもう、臨床の業務だけでとても忙しい。アメリカのようにもっと医師の時間がマネジメントされていれば、あるいは、と思いますが。
――大須賀先生のキャリアは、転身しているようで一貫しているのですね。
そう、私は思っています。臨床はやっぱり人と接することが楽しみで、研究は科学の真理を追求することが楽しみ。新薬開発、これは広い言葉なので私は創薬がメインですが、その魅力はやはり、患者さんにつながっていくことです。臨床から研究、そして創薬へと、円を描くようにつながっているのが、自分のキャリアだと思います。最終的に「人」に関わらないものはやろうと思わないですね。
情報発信も、人の命を救う「医療」である
――また、先生は日本語で医療情報の発信をされており、Twitterには3. 9万人のフォロワーがいます。本業の傍ら、本の執筆やSNSの更新をなさるのも、人につながるからでしょうか。
そう言えるかもしれませんね。もともと書くことが好きだったので、Facebookでいろいろと情報発信をしていたんです。医療やサイエンスのニュースについてのコメントが中心でした。
そうこうしているうちに、専門であるがんの領域で、ひどく不正確な情報が日本で広がっている、という問題に気付きました。医師時代はこのことにあまり気付いていなかった。確かに臨床医時代に、患者さんから「この数百万円の自由診療を試していいですか」といった質問を受けることはありました。でも、それが社会にとって重要な問題だとは思っていなかったんです。

大須賀氏によるブログ。「怪しいがん治療の見抜き方」や「末期癌の友人にどのように接するべきなのか」といったがん患者とその近親者に向けた記事が並ぶ
SNSが普及して、その問題に気づいてみると、日本では標準治療を否定するような書籍がミリオンセラーになったり、雑誌は医療批判を繰り返したりしている。逆に、科学的な根拠のある治療をしている側からは、わかりやすい情報発信がほとんどされていない。「何か自分ができることはないかな」と、友達限定だったFacebookの投稿をオープンにしていきました。その後、本格的に情報発信をするようになったのが、2018年の3月くらい。ブログやTwitter、noteを始めて、急に多くの人にフォローしていただけるようになって。
情報発信をしていると、その情報によって本当に行動を変えてくれる人がいることがわかります。「食事でがんが治ると思っていました」「それが不正確だと先生の発信で理解できました」と直接、言ってもらうと、これも一種の「医療」なんだ、と強く感じます。
先日、登壇させてもらったイベントで、ある方に話しかけていただいて。その方はがん患者さんで、ネットに広がる情報に惑わされて、科学的根拠のない怪しい「がん治療」にはまってしまっていたそうなのです。しかし、ある時にTwitterでたまたま私の書き込みを見かけて、間違っていたんだと気づき、標準治療に戻ることができた、とおっしゃるんです。「命を助けてもらいました」と言われて、それはうれしかったですね。情報発信は命を救うこともできるんだ、と。
積んだキャリアは、必ずどこかにつながってくる
――今後、日本に戻ることは考えていらっしゃいますか。
大前提として、今の私の目的は、お薬の開発に注力することです。それはどこの国でも構いません。しかし今だとアメリカでするのが一番、都合がいい。だから今はアメリカでやっています。一方、私としては日本の脳腫瘍の研究をどうにかしたい、という想いもあるので、チャンスとプッシュがあれば、というつもりですね。
とはいえ、私は研究者としてのキャリアがまだまだ不足しています。当然、現時点で研究者として成功しているとは全く思っていません。まだまだ駆け出しの下っ端です(笑)。まずは自分のラボを持って独立し、自分の研究室を運営して成果を上げていきたいですね。うまくいった、なんて気持ちはなくて、すべてはこれから。まさに今だって、全力で戦っているつもりです。
――日本国内で臨床と研究の間で悩んでいる医師の方々に、何か伝えられることがあるとしたら、どんなことでしょうか。
一つ、日本の外から見て感じるのが、日本では研究をするメリットが見えにくくなっていますよね。大学で臨床をしながら研究すると、お金は儲からないし、とにかく忙しい。非常に過酷な労働環境になる。パートで医師をする人の方がお金をたくさんもらえて、時間の余裕もあるとなると、研究をする医師はなかなか生まれにくいでしょう。
それでも大学に残って一生懸命研究することが、そもそもいいことなのか。真面目に頑張れば頑張るほど、忙しくて貧しくなる現状に疑問を持つお医者さんもたくさんいるはずです。しかしこれは、今の日本のシステムがそうさせているだけ。他の人にない技術や知識は、世界的にはやはり高く評価されるので、アメリカではそういう人の方が高給を取ります。日本の環境ではモチベーションを維持するのが難しいのなら、私のように海外に留学してもいいでしょう。
また、時代が変わる可能性も大いにあります。今の日本の医療システムがそのまま未来に残っていくとは思えませんから。どこかで大変革が起きる可能性もあります。その結果が良いものになるのか、悪いものになるのかまでは、まだわかりませんが……。
忘れてほしくないのは、自分に他の人ができない医療技術や知識があるのなら、それは価値があるということ。今は周囲がそれを評価してくれない時代だからといって、そんな目先のことには惑わされないでください。世界ではそのような人が評価されるし、国内の状況も変わるかもしれないのですから。

また、もしやることが途中で変わったとしても、何もかもムダになんてなりません。積んだキャリアが、その次につながっていくことは絶対にあるんです。私は医師としてのキャリアを途中で辞めてしまいましたが、それが今、研究に生きている。情報発信もそうで、どこからか降ってきたように取り組んでみたものが、日本での出版にもつながりました。結局、経験したことはどこかに貯まって、いずれ花が咲くのでしょう。完全にムダなことなんて、人生に一つもありません。
私もまだ、ゴールに達している人ではない。走っている最中です。だから、一緒に苦しんで頑張りましょう、というのが伝えたいことですね。私が海外で研究を続けることで、少しでも日本で頑張る方々の選択肢が増えればうれしいです。
(聞き手・文=朽木誠一郎+ノオト/撮影=栃久保誠)
【関連記事】
・「クラウドファンディングは臨床研究の課題を解決するか〜『ネット寄付1,600万円』の舞台裏」勝沼俊雄氏(東京慈恵会医科大学 小児科学講座教授)
・「3人の子どもを育てながら臨床・研究の現場で働く」大西由希子氏(朝日生命成人研究所 治験部長)
・「勤務医が知っておきたい医学論文作成のイロハ【第1回】」康永秀生氏(東京大学大学院医学系研究科 教授)
・「『外科医』という仕事の魅力」山本健人氏[けいゆう先生](消化器外科医/京都大学大学院医学研究科)

- 大須賀 覚 氏(おおすか・さとる)
- 1978年生まれ、アラバマ大学バーミンハム校(UAB)脳神経外科助教授。2003年筑波大学医学専門学群を卒業、脳神経外科医としての勤務を経験した後、慶應義塾大学医学部特別研究員(PD)。2014年より、難治性脳腫瘍の新薬開発の研究のため渡米。エモリー大学ウィンシップ癌研究所を経て2019年10月より現職。医学博士。過去には、リンダウ・ノーベル賞受賞者会議に参加、日本脳神経外科学会奨励賞受賞など。著書に『世界中の医学研究を徹底的に比較してわかった最高のがん治療』、監修書に『研究者・留学生のためのアメリカビザ取得完全マニュアル』。

- 『世界中の医学研究を徹底的に比較してわかった
最高のがん治療』 - 著者:津川 友介、勝俣 範之、大須賀 覚
発行所:ダイヤモンド社
発行日:2020/4/2
目次:
はじめに がんになったらどの治療法を信じればよいのか
第1章 「最高のがん治療」はどのように決められるのか
第2章 「最高のがん治療」では何をするのか
第3章 食事やサプリでがんは治るのか
第4章 どうしてがんができるのか
第5章 「トンデモ医療」はどうやって見分けるのか
第6章 どうやってがんを見つけるのか
第7章 がんを防ぐために普段の生活で何ができるのか
おわりに この本は「情報のワクチン」である
内容:
世界で活躍する医師と専門家の英知を集めたがん解説本の決定版!「日本の抗がん剤治療のパイオニア」「医療データ分析の研究者」「新薬開発の研究者」の3人が自分の専門分野を語るから、詳しいのにわかりやすい。2人に1人ががんにかかる時代、すべての日本人必読の書。学歴と収入が高い人ほどトンデモ医療にだまされる!(ダイヤモンド社書籍紹介ページより)




 公式SNS
公式SNS
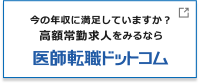
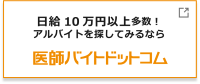


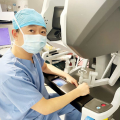













コメントを投稿する