メスを置き、リハ医として生きる 後編
地域で生活するための医療がしたい
石川誠 氏(医療法人社団輝生会 理事長)
前編では、リハビリテーション医療のアプローチ法や今後の展望についてお話しいただきました。後編では、石川氏が脳神経外科からリハビリテーション科へと転科された経緯や、近森リハビリテーション病院や輝生会を立ち上げ、日本のリハビリテーション医療体制を築きあげてきたこれまでの取り組みについてご紹介いただきます。

「この患者の人生はすべて君が責任を持つんだな」
私が脳神経外科医として働き始めた頃は交通戦争のまっただ中、バイクの運転者にヘルメットの着用が義務化される前で、頭部外傷が非常に多かったんです。脳出血や脳梗塞、クモ膜下出血といった脳血管障害も多く、それらは脳神経外科の対象疾患になっていたため、脳神経外科の医師は猫の手も借りたいという忙しさでした。
インタビューの始めにもお話ししましたが、脳神経外科としての仕事に熱意を燃やしていたんですが、手術をしても、どうにも患者さんがあんまりよくならないんです。命は助かるけども、障害が残ってしまう。当時の脳神経外科医は、「脳神経外科的処置が終わったら患者さんとはさよなら」という考え方でした。例えば整形外科医は、骨折の手術の後のリハビリもちゃんと担当するのに、脳神経外科は手術したら、後は知らん顔するわけです。「果たしてこれでいいんだろうか」と疑問を持ったのが、後にリハ医に進むことになった最初のきっかけでした。
入局3年目に、長野県の厚生連佐久総合病院に赴任することになりました。佐久総合病院は農村医学のメッカで、地域を見、生活を見ながら、農民と一緒に健康管理や疾患の治療をしようという雰囲気に満ち溢れていて、非常に地域を大事にするところだったんですね。
そうした場所に、脳神経外科という臓器別のウルトラ専門家として赴任した私は、自分だけ地域医療とは別のことをやっているような違和感がして仕方がありませんでした。当時は脳神経外科で手術をした後、歩けなくなったり、寝たきりになってしまったりする人がたくさんいたもんですから、それを何とか地域に帰して生活できるようにするとなると、リハビリを知らなくてはどうしようもない。「地域医療とは何ぞや」という大テーマを突きつけられました。
浅間連峰を臨む佐久市は農村医学のメッカ。その浅間連峰で1972年に起きた浅間山荘事件時、連合赤軍に頭を打ち抜かれた機動隊が運び込まれたのをきっかけに、佐久総合病院に脳外科が設立された。
あるとき、40代くらいの働きざかりの患者さんが入院されて、私が手術をしました。その方は歩いて入院されたんですが、術後に寝たきりになってしまったんです。そのとき、当時の院長である若月俊一先生が、私にこう仰いました。
「この患者を手術したのは君か。まったく動かないではないか。君はどうするつもりなんだ。君が手術したのだから、この患者の人生はすべて君が責任を持つんだな」
私も若かったものですから、頭の中が真っ白になり「そんなこと言ったって、わざとやったんじゃない。しょうがなかったんだ」って自己弁護的な発想をしてしまいました。でも、若月先生としては「手術をした医師がすべての責任を持って当たり前」ということを教えたかったのでしょう。私にそれくらいの覚悟があるのかを問いたかったのだと思います。
若月先生の言葉は、私がその後、一気にリハビリテーションの道へ進むきっかけになりました。佐久総合病院に行き、病気ばかり診る「臓器別専門家」に対して、生活も診る「地域医療」に触れたこと。これがなければ、リハに進むという決断はしませんでした。
臓器別専門家は、完全に治る病気を診る分にはいいですけど、治らない病気や障害を抱えた人たちは問題が山積みです。この問題に対応するのがリハビリだと考えたわけです。
奇人変人扱いされたリハビリテーション医
私は佐久総合病院にいる間にリハビリを勉強しようと思っていました。ところが、そういう考え方が脳神経外科では危険分子とされてしまいました。脳神経外科は猫の手も借りたい忙しさですから、「こいつ脳神経外科を辞めて違うところに行っちゃいそうだぞ」と危険視されたんでしょう。それで大学に連れ戻されてしまったわけです。
大学に戻されて悶々としていたときに、東京の虎の門病院から、ぜひリハビリテーションを手伝ってくれと声がかかりました。私は渡りに船と考え、脳神経外科を辞める決意をして虎の門病院へ行き、リハビリの勉強を始めたんです。
当時は脳神経外科の仲間や先輩から「リハビリなんかで飯が食えるわけがないし、あんなもの医者がやる仕事じゃない」とぼろくそに言われました。奇人変人扱いです。その頃、リハビリテーション部門は非採算部門の代表格で、「リハを充実させると病院は経営難になる」とまで言われていました。
虎の門病院に入っても、リハビリテーションを専門にしようとする医師は私だけで、そこでまた奇人変人扱い。PTやOT、STは何人かいましたが、「変わった医者が来た」くらいに思っていたみたいです。
ただ、看護師の反応は良好でした。「これまでリハのことを考える医者はいなかったけど、一生懸命考えてくれる医者が来た」ということで、好感を持ってくれたようです。
現場とアカデミックの両面で学ぶ
日本の病床数は他の先進国の何倍も多いのです。私は、リハビリテーション医療が発展しなかったことと、付き添い看護制度があったことが、日本の病床数を増やしたと思っています。リハビリテーション医になった頃から「看護とリハがしっかりすれば、少ない病床数でやりくりできる」と考えていました。
付き添い看護制度が当たり前の当時、虎の門病院の看護は別格と言ってもいい程進んでいたんです。どんなに手のかかる患者でも家族に頼ることはなく、すべて看護師が対応していて、患者が自立できるように徹底的に支援していました。寝たきりにするとか、褥瘡ができるなんていうことは考えられない。ベッドサイドで看護師がやっていることを見て学ぶのは、一番勉強になりました。
それに上乗せして、PT、OT、STと一緒に訓練室に入って、教わりながら実際に訓練をやりました。PTと一緒に海水パンツ一つでプールに入って患者さんを動かしたりと、できることはもう何でもやったわけですよ。そうしてやったことは全部、自分の糧になりました。
「現場のやり方を見るのが一番勉強になった」と石川氏。写真は、千葉県船橋市の要望を受け開院した船橋市立リハビリテーション病院の作業室。
それとは別に、当時、府中にあった神経科学総合研究所のリハビリ研究部門に毎週通って、アカデミックの最先端のところも勉強しました。また東大病院リハビリテーション部にも通って、教授の上田敏先生からも学びました。どこか一つのリハビリテーション学教室に入ったのではなくて、まったく違うところで少しずつ勉強したんです。そのため時間はかかりましたが、おかげで何とかリハ医として格好がつくようになりました。
それでも、リハの専門医を取るのにはずいぶん苦労しましたね。全国で66番目だったので、私より先に取得した先輩は60数人ぐらいしかいないわけです。リハの専門医ができて3~4年ぐらいだったので、毎年20人ぐらいしか取得しないんですから、かなり少なかったみたいです。
付き添い看護の撤廃――近森病院の改革
リハビリテーションの体制づくりを学ぶために、いろいろな病院を見学したり、いろいろな人に相談したりしましたが、これだと思えるような、そのままモデルにできるようなやり方は見つかりませんでした。そうしているうちに、自分なりに理想のリハビリ体制を立ち上げたいと思うようになっていたんです。
私の考えるリハビリテーション医療には二つの大きなテーマがありました。一つは地域と密接に関われる所でリハをやりたい、もう一つは救急医療を行っている所でリハをやりたいということです。虎の門病院は、都会の病院に多い、地域密着とはあまり関わりのない病院でした。
そうしたときに、高知の近森病院にスカウトされてそちらへ移ることになります。1986年のことです。
当時の近森病院は、救急は頑張っているものの、全館付き添い看護で寝たきりの患者ばかりベッドに寝ていて、「寝たきり製造機」のような病院でした。ベッドが足りないとベッドを増やすか、患者をよそへ転院させるかで、一生懸命よくして家に帰そうなんて雰囲気はほとんどなかったんです。
でも、そういう病院だから仕事になるわけです。既に完成されたところへ行ったって面白くないですよね。
行った当初はもうめちゃくちゃ、四面楚歌でした。付き添い看護を撤廃しようとしたんですが、誰も賛成する人はいませんでした。そこで、虎の門病院から看護師さんを6人ぐらい引き抜いて、その人たちと協力しながら少しずつ取り組んでいきました。みなさん「リハビリ」というと、今でもPT、OT、STがやるものだと思っているかもしれませんが、要になるのは看護なんです。
少しずつ結果が出はじめると、徐々に周りの反応も変わってきて、3年半後には基準看護とチームアプローチの近森リハビリテーション病院を開設しました。この病院のやり方が厚生労働省に注目されて、回復期リハビリテーション病棟の制度ができたんです。
近森病院を変えていくのはとても大変でしたけど、今になって考えると楽しかったですね。
またその頃には、当時の厚生省に何回も足を運び、日本のリハビリテーション医療がいかに未熟で、危機的な状態にあるかを、データを示して訴え続けました。経済的にも、人員的にも、さらなるバックアップが必要だと説いて、診療報酬の向上を目指したんです。非採算部門のままでは、改革なんてできませんから。
現在では、リハビリテーションに関する診療報酬が以前とは比べものにならないぐらいアップしました。ただその分、今は質が厳しく問われる時代になっています。
東京でのリハビリテーション病院設立
高知で近森リハビリテーション病院が軌道に乗ったあと、1996年には在宅総合ケアセンターを作り、翌年には近森病院本院に急性期リハを整備しました。これにより、急性期、回復期、維持期の三つのリハが揃いました。ただ、すべてが整ってしまうと、私のやることがなくなってしまったんです。そのままいてもよかったんですが、つまんなくなっちゃったんですね。
そこで、出身地である東京に目を向けてみたところ、リハ提供体制が1980年代からあまり進展していなかった。「これは東京でもう一仕事できるな」と思って、東京に戻ったんです。
東京に戻るにあたりお金もなく、スタッフも大勢いるわけではなかったので、台東区にたいとう診療所を立ち上げて、まず在宅から細々とやり始めました。
そうしたら、どんどん仕事が増えていったんです。在宅に取り組むほどに、東京にはまともなリハビリテーション病院がないことが分かってきました。「それじゃあ、まともなリハ病院を東京のど真ん中に作ろう」と考えて、2002年にできたのが初台リハビリテーション病院です。近森でやっていたことをバーションアップしたものを東京でやり始めたわけですが、キャピタルコストが全然違いますからね。東京ではなかなか大変でした。
2002年には初台リハビリテーション病院(写真上)を、2008年には千葉県船橋市の要望を受け船橋市立リハビリテーション病院(写真下)を開院した。
在宅の包括的なケア体制の普遍化を目指して
地域包括ケアの整備の中で、在宅の包括的なケア体制をどのように確立していくかというテーマがあるとお話ししました。輝生会では今、元浅草と成城、そして船橋の3つの拠点で、このテーマに取り組んでいます。
元浅草のケアセンターは、今、8床しかありませんが、在宅の診療で常勤医が5人、スタッフ数は常勤で100人います。100人いれば病院を作れますが、その人数で在宅患者を診ているわけです。私は在宅診療にはこれだけの体制が必要な時代だと思っています。こうしたケアセンターが各地域に1カ所ずつあれば、その地域で寝たきりの人がいないという状態を実現できると確信しています。
こうしたケアセンターのやり方を普遍化する、経営的にももっと研ぎすまして地域にも受け入れてもらえるようにして、全国展開というか、全国で真似してもらうことで普及させたい。それが今の私の仕事ですね。
リハビリテーション医を目指す医師に向けて
日本は少子高齢化まっしぐらで、将来は高齢化率40%の時代が来そうな状況です。そんな中で、医療や介護に対する要望も非常に厳しいものがあり、従来のやり方をしているだけではうまくいきません。
医療スタッフをチームとしてまとめて医療や介護のサービスを作っていくのは、苦労が多いかもしれませんが、大変やりがいのある仕事です。リハビリテーション医は「人がその人らしく生きること」をサポートできる仕事であり、人間が好きな人に向いています。そして、ただ単に“よくする”のではなく、リハビリを通し、その人の人生を前向きに変えられる医療でもあるのです。
ぜひ、この魅力的な仕事に一生懸命に取り組んでもらえればと思います。
(聞き手・エピロギ編集部)
【関連記事】
メスを置き、リハ医として生きる 前編
医師の目から見た「働きやすい病院」とは 前編
医療ニーズの変化と医師の生涯学習
「医者」として正しい専門医へ
企業と人の狭間で <前編>

- 石川誠(いしかわ・まこと
- 医療法人輝生会理事長。回復期リハビリテーション病棟協会常任理事(元会長)、日本リハビリテーション病院・施設協会顧問(元副会長)、日本訪問リハビリテーション協会初代会長。日本リハビリテーション医学会専門医・代議員・理事。
1973年に群馬大学医学部を卒業後、同年5月より同大学医学部脳神経外科研修医。1975年に佐久総合病院脳神経外科医員、1978年に虎の門病院の脳神経外科医員となる。1986年4月より医療法人社団近森会近森病院リハビリテーション科長、1989年12月より近森リハビリテーション病院院長に就任。2000年4月より医療法人新誠会理事長を務める。2004年4月より現職。





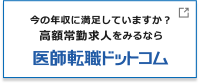
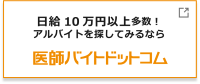


















コメントを投稿する