【第4回】レナードの朝~医師患者関係を徹底して追求した感動作
石原 藤樹 氏(北品川藤クリニック 院長)
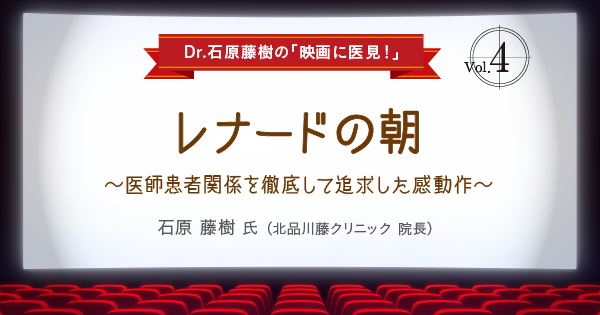
医療という題材は、今や映画を語るうえで欠かせないひとつのカテゴリー(ジャンル)として浸透しています。医療従事者でも納得できる設定や描写をもつ素晴らしい作品がある一方、「こんなのあり得ない」と感じてしまうような詰めの甘い作品があるのもまた事実。
シリーズ「Dr.石原藤樹の『映画に医見!』」は、医師が医師のために作品の魅力を紹介し、作品にツッコミを入れる連載企画。執筆いただくのは、自身のブログで100本を超える映画レビューを書いてきた、北品川藤クリニック院長の石原藤樹氏です。
第3回の『ディア・ドクター』に続き、今回は『レナードの朝』をご紹介いただきます。
現役医師だからこそ書ける、愛あるツッコミの数々をお楽しみください(皆さまからのツッコミも、「コメント欄」でお待ちしております!)。
映画『レナードの朝』の概要
今日ご紹介するのは、1990年製作のアメリカ映画『レナードの朝』です。1969年アメリカ、ブロンクスの神経内科病院に赴任した、それまで臨床経験のほとんどなかったマルコム・セイヤー医師(ロビン・ウィリアムス)は、嗜眠性脳炎の後遺症と思われる重症の神経障害の患者に対して、当時臨床応用が始まったばかりのL-ドーパ製剤を実験的に使用し、それまで眠っていた患者が次々と目覚めるという、劇的な治療効果を得ます。
その治療により最初に目覚めたのが、少年の時から症状を発症していたレナード・ロウ(ロバート・デ・ニーロ)という患者でした。第二の人生を謳歌するレナードでしたが、薬の安定した効果は長くは続かず、新たな症状と苦しみが彼を襲います。レナードとセイヤー医師はどのような決断をするのでしょうか。感動のドラマが待っています。
見どころは名優2人の見事な演技と人間ドラマ
この作品の見どころは、何と言っても主役2人の見事な演技にあります。ちょっと奥手で発達障害的な医師を、人間味たっぷりに演じたロビン・ウィリアムスもさすがですし、緻密な演技プランで、パーキンソン症候群に苦しむ患者をリアルに表現したデ・ニーロも見事な出来映えです。特にレナードが、一度は普通の恋愛を夢見ながら、絶望して身を引くところなど、涙なしでは見られません。
それ以上に感動的なのは、医師と患者の関係を超えた2人の友情で、前半でレナードの動かない体に生命のきらめきを探し、徹底してその復活を追い求めるセイヤー医師の情熱も凄いですし、後半では、今度は副作用や病状の悪化に苦しみながら、その記録を主治医に残させようとするレナードの執念に心を打たれます。
原作と映画との違い
この作品はオリヴァー・サックス医師による同題(原題、訳題とも)の症例報告スタイルのドキュメントを原作としています。つまり、事実を元にしています。ただ、翻訳もされている原作と映画とでは、かなりの違いがあります。
原作には20例の症例が1つずつ紹介されていて、レナードの事例はそのうちの1つに過ぎません。原作のレナードは、体は動かないものの、治療前にも医師との意志疎通自体はできていて、インテリジェンスのある対話も可能でした。L-ドーパを使用することで体は動くようになったものの、幻覚やジスキネジアなどの副作用が強く出現したため、本人も同意の上でL-ドーパを中止し、その後にもアマンタジンなど、複数の投薬を本人とも相談の上で試しています。
映画では内容をドラマチックにするために、レナードを意思疎通が全くできない状態にしていて、投薬により普通の人と変わらないまでに回復する、という設定にしています。そこまではまだ良いのですが、後半では病院の中で病人が人権を奪われ、迫害されていると訴えるような場面を作っているのは、いささかやり過ぎだと思います。そんな描写は原作には全くありません。『カッコーの巣の上で』(※)の影響でしょうか? かなり違和感がありました。原作とは多くの点が異なり、主人公の医師の名前も違っているのに、事実に基づいている、とクレジットされるのも、いささかフェアではない、という気がします。
ご興味のある方は原作も是非お読み下さい。映画より数段リアルな内容で、映画に違和感を覚えた方も納得されると思います。
※『カッコーの巣の上で』
1963年9月のある日、オレゴン州立精神病院に一人の男が連れられてきた。ランドル・P・マクマーフィ。彼は刑務所の強制労働を逃れるために狂人を装っていた。しかし精神病院はもっと悲惨な状況にあった。絶対権限を持って君臨する婦長によって運営され、患者たちは無気力な人間にされていたのだ。さまざまな手段で病院側に反抗しようとするマクマーフィに、患者たちも心を少しずつ取り戻し始めた。そんな彼の行動に脅威を感じた病院は、電気ショック療法を開始するが、マクマーフィも脱走を計画し始める…。ケン・キージー原作のベストセラーを映像化。感動のラストシーンが印象的。
引用元:ワーナー・ブラザース公式サイト
演技するには無理のある表現も
この作品は要するに、まだL-ドーパの長期使用時の副作用が知られていなかった時代に、1日5000ミリグラムといった高用量を投与した場合の、医療の悲喜劇を描いたドラマです。そう思ってみれば納得がいくのですが、治療継続時の症状の悪化の原因をあまり明確に描かず、人間の尊厳や人権のドラマにしてしまっているので、どうも医療者としては違和感があります。
デ・ニーロの演技も、映画の演技としては素晴らしいのですが、患者の症状の記録として見ると、前半の無動の演技はまあリアルに見えるものの、後半のチックやジスキネジアなどの表現は、あまりリアルには見えませんでした。不随意運動を映像加工せずに演技で表現するというのは、基本的に無理があるように思います。人間というのは、意図のある動きしか、演技としてはできないもののようですね。
医療者が学ぶべきは「医師と患者の関係」
この作品には医者の目線から見るとおかしな点も多いのですが、医師患者関係という点からは、多くの学ぶべき点のある映画です。主人公のセイヤー医師は、ほとんど臨床経験がなく、実験しかしてこなかった経歴ですが、そのために熟練の臨床医とは別の目で、治る見込みがないと判断されている患者の病状の中に、回復の兆しを発見することができたのです。臨床医は日々の患者対応の中で、そうした誤った判断や、ステレオタイプの診断をしがちではないでしょうか?
また信頼関係のある患者への治療により、新たな問題が生じて病状が悪化した時に、セイヤー医師のように、その事実を患者に隠すことなく向き合い、不本意な結果でも認めるべきものは認めて、最後まで科学的で客観的な見方を失わずに、治療に取り組むことはできるでしょうか?
患者から信頼され求められる医師になるために、最も大切なことがこの映画では描かれているように思えるのです。
【関連記事】
・「Dr.石原藤樹の『映画に医見!』第3回|ディア・ドクター~日本映画史上最も有名な「偽医者」の物語」
・「“医”の道を切り拓く~世界の女性医師たち~|第5回 近代ホスピスの母 シシリー・ソンダース」
・「妊産婦の命を守りたい~“手洗い”の創始者 産科医イグナーツ・センメルヴァイスの生涯」
・「アメリカの『ベッドサイドマナー』に学ぶ、患者コミュニケーション」山室真澄氏(North East Alabama Regional Medical Center in Anniston 心臓血管外科医)
・<PR>神経内科の医師募集情報

- 『レナードの朝』
- 発売中
Blu-ray 2,381円(税別)/DVD 1,410円(税別)
発売元・販売元:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
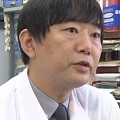
- 石原 藤樹(いしはら・ふじき)
- 1963年東京都渋谷区生まれ。信州大学医学部医学科大学院卒業。医学博士。信州大学医学部老年内科助手を経て、心療内科、小児科を研修後、1998年より六号通り診療所所長。2015年より北品川藤クリニック院長。診療の傍ら、医療系ブログ「北品川藤クリニック院長のブログ」をほぼ毎日更新。医療相談にも幅広く対応している。大学時代は映画と演劇漬け。



 公式SNS
公式SNS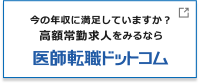
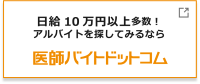




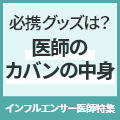
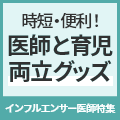


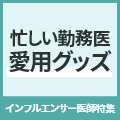











コメントを投稿する