「診察室に来る前」の患者に今、起きていること 医療者にできるアプローチとは〜 佐渡島庸平氏(編集者)×病理医ヤンデル先生
佐渡島庸平氏(編集者)× 病理医ヤンデル先生[市原真氏](病理専門医)
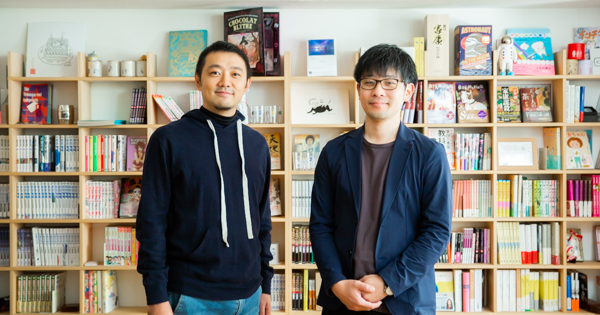
従来、診察室に来るまで生まれにくかった患者と医療の接点。インターネットが発達・普及し、人々の生活が一変した現在、それは「情報」という形で無数に増えている。検索サービスGoogleの日本における利用者数は約6,600万人。人気SNSのアクティブユーザー数は、Facebookが2,600万人、Twitterが4,500万人、Instagramが3,300万人。そして、これらプラットフォームのすべてで、医療情報はその発信者が専門家か非専門家かによらず、活発に発信されている。
このような状況がもたらすのは、当然、恩恵だけではない。例えばアメリカでは、近年の麻疹の再流行の背景に、FacebookなどのSNSにおける「反ワクチン」情報発信の強まり、それによるワクチン接種率の低下があったとされる。日本でも、科学的根拠のないがんの「治療」がネットで宣伝され、患者や家族がそれを信じ込んでしまう、といった問題が提起されている。一方、「診察室に来る前」の患者へのアプローチは、ほぼ手つかずなのが現状ではないか。
そこでエピロギでは、『ドラゴン桜』『働きマン』『宇宙兄弟』(いずれも講談社)などのマンガの担当編集を歴任、現在はクリエイターのエージェント会社・コルク代表の編集者・佐渡島庸平氏と、Twitterで10万人以上のフォロワーを擁し、書籍などネット外での情報発信にも積極的に取り組む病理医・ヤンデル先生の対談を実施。2019年夏、ネット上で行われた医療情報発信に関する「往復ブログ」をベースに、医療者に望まれるアクションを話し合った。
いかに患者の「自分ごと化」を起こすか
――ヤンデル先生は最近、医療情報発信の支援にかなり熱心な印象です。佐渡島さんとのネット上の往復ブログでは、“「『適切な医療』を多くの人々に届けようという(情報発信の)試み」が停滞している恐怖”がある、としていました。つまり、医療と患者をつなぐ情報発信に課題がある、ということでしょうか。
▼メディアプラットフォーム noteにて行われた、佐渡島氏とヤンデル氏の往復書簡
(ヤンデル先生→佐渡島氏)
(佐渡島氏→ヤンデル先生)
(ヤンデル先生→佐渡島氏)
ヤンデル:まず、私は「実際に全く医療情報が届いていない」と思っているわけではありません。医療者として現場の例をいくつか振り返っても、昔より医療情報にアクセスしやすくなり、患者から見ても医療のハードルが下がり、早めに必要な情報にたどり着けるようになっている。SNS普及以前に比べ、今の方がはるかに適切な医療が患者に届きやすい状況と言っていいと思います。
問題意識を過剰に持つあまり、ありもしない問題を生み出してしまうのは危険です。話題書『FACTFULNESS 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣』(日経BP)にもあるように、医療情報に限らず、基本的に社会にまつわるあれこれは、昔よりも少しずつましになってきている。それが前提です。
ヤンデル:一方で、SNSには感情的な言葉をさらに強調する効果がありますよね。それはポジティブよりもネガティブな面についてより顕著なため、日頃から医療にまつわる多くの不満・不安を見かけるようになりました。これらは、今まで医療者たちが診察室の中で拾いきれなかった、診察室の外にある患者側のナラティブ(物語)です。その結果、私の体感では医療者と患者の間に、今まで気づけなかったタイプの齟齬が生まれているのではないかと思います。その是正を図ることには、社会的な意義があるでしょう。
現状、特に私が問題視しているのは、メディアをおそらくは使いこなせていないまま医療情報を発信している、われわれ医療者の方です。つまりは「自戒」が根本にあります。
例えば、エビデンスとナラティブのバランス。エビデンスで固めた「正しい」医療情報が本質的に伝わりにくいものだとする向きもありますが、だから届かなくてもしょうがないんだ、と開き直るのは少々無責任すぎると思います。医療という「専門の盾」で情報を囲んでしまっているが故に、届けるべき情報を上手く伝えられていないのだとしたら、まずいのではないか。
このような思いが、現状、医療情報発信の試みが停滞しているのではないかという恐怖につながっています。もし、情報発信のプロの力を借りれば、同じように正確な情報であってももっと上手く伝えられるかもしれません。
――医学論文のような情報はたしかに一般の生活者には伝わりづらいと思う一方、プロのコンテンツ制作者の手にかかれば、『コウノドリ』(鈴ノ木ユウ/講談社)や『フラジャイル 病理医岸京一郎の所見』(恵三朗・草水敏/講談社)といった人気マンガのように、専門的な知識を含みつつも、秀逸なストーリーによって滞りなく読ませ、ドラマ化などで社会現象になる例もある、ということですね。
ヤンデル:はい。名だたる人気作品を送り出してきた、著名な編集者である佐渡島さんにnoteで質問をしたのは、それが理由です。佐渡島さんは以前、noteの記事で「商品、サービス、プロジェクト、会社が世の中に浸透するには、ステークホルダーを増やすことが重要で、コンテンツを世に届けるという行為は、様々なビジネス的な行為と結局は一緒なのだ」「コンテンツが溢れてしまって、ますます他人にとってどうでもよくなっている時代だからこそ、編集者はコンテンツに対して各自がステークホルダーになれる仕組みを散りばめることが必要」とおっしゃっていました。これを拝読し、われわれは医療情報をどう発信していくべきか、佐渡島さんに教わりたいと思ったんです。
――医療情報について佐渡島さんのコンテンツ論を当てはめたとき、各自がステークホルダーになるというのは、その情報を「自分ごと化」してもらうことだとも言えそうです。一方で、現在、健康な人に将来の病気のことを自分ごと化してもらうのは難しいし、病気になり、まだそれを受容できない人に自分ごと化を求めることもやはり難しい。どのようなアプローチがあり得ると思いますか。
佐渡島:まず、医療者と患者では、医療情報にアクセスするときの視点が全く違うことを意識するべきでしょう。
先程エビデンスという言葉が出ましたが、多くの人が知りたいのは「正しい知識」ではない。そもそも何が「正しい」かは、コミュニティによって変わってしまうものです。科学において「正しい」ことと、社会において「正しい」ことは、乖離してしまうことがあるんですね。
例えば、病気に関する「正しい知識」を手に入れても、患者や家族にとってはどうしようもないこともある。例えば患者ががんについて知りたいことは、「がんとは細胞が突然変異を起こして……」といったメカニズムではなく、「自分のがんは治るのか」「生きていられるのか」ということでしょう。もっと言うと、正しいことを知りたいのではなく、安心したいんです。
佐渡島:一方で、医療情報が難しいのは、その患者が欲している安心が存在しない場合も多いということ。5年生存率は〇〇%です、という正しい情報を理解するというのは、裏を返せば、一定の割合で5年後に死ぬ可能性があることを認めなければいけないということですから。
また、正しい情報を手に入れても、患者が「正しく」選べるのかという問題もある。単純化した例を挙げますが、医師が「治療Aは治る確率が60%だけど、副作用の可能性は70%くらい」「治療Bは治る確率が40%だけど、副作用の可能性は30%です」と言ったとします。それは医学的には正しい情報だし、選ぶのが患者だという姿勢も正しいのでしょう。しかし、「さて、どうしますか」と聞かれたところで、Aを選ぶべきかBを選ぶべきか、患者にはなかなか選べません。例えるなら、乗り心地や、そもそも目的地のこともよく知らない状態で、移動手段はどれにするかと聞かれても、選びようがない。
このような理解や選択を助ける、患者に寄り添うような情報というのが、まだまだ少ないと感じます。まずは医療者と患者のこの大きな差を埋めなければ、「自分ごと化」は起きません。
もう一つ、伝え方の例として、あえて「ニセモノの情報」を扱っている人もいます。いわゆる「ニセ医学」のような情報を発信する人たちですね。彼らは、自分たちの情報がニセモノであることをよくわかっています。だから、情報を伝えることではなく、感情に寄り添うことを主軸に発信する。その結果、患者の中で情報の「自分ごと化」が起きて、その人たちの情報の方が、科学的に正確な人の情報よりも患者には届いてしまう。
ニセ医学の情報発信者は、実際にはそうではないにもかかわらず、「胸襟を開いている」印象があるのも特徴的です。「がんが消えた」「抗がん剤は使わなくていい」など、正しくなければいくらでも言い切れるからでしょう。
長年、コンテンツ制作を生業にしているからこそ思うことですが、信頼の積み上げというのはなかなか難しいものです。特に、科学的に正しい情報を伝えるとき、言いにくいことは言わずに「察してほしい」という、ためらいのようなものを僕は感じることがある。そんな奥歯に物が挟まったような情報発信では、ニセモノの情報発信と勝負にならない、ということに、向き合うタイミングが来ているのかもしれません。
医療が「生き物」なら、そこに脳はいない
――佐渡島さんは近年、横浜市医療局とタッグを組んだ『医療マンガ大賞』など、医療領域での活動にも注力されています。医療への関心がおありなのでしょうか。
佐渡島:僕は文系に進みましたが、もともと母校の灘高校には医学部志望の同級生が多く、友人にも医師がたくさんいます。とにかく議論が好きな人たちなので、一緒にゴルフに行ったら例えば「日本の医療制度の問題点」をずっとディスカッションしているんですね。医師になった後輩の一人は『ドラゴン桜』の勉強法をいくつか考案したり、『宇宙兄弟』の医療パートの一部を監修してくれたりと、仕事を一緒にすることもあって。他にも『「病院」がトヨタを超える日』(北原茂実/講談社プラスアルファ新書)という書籍を担当したり、医療ビジネスに取り組む企業のコンサルをするなど、ずっと医療には強い関心を持っていました。
――ヤンデル先生とネット上で往復ブログをされていましたが、実は今日が初対面なんですよね。
佐渡島:ですね。でも、1〜2年前くらいからTwitterでフォローしていました。友人の医師からTwitterに注力したいという相談を受けたのですが、そのときに医師のインフルエンサーとして教えてもらって。SNSの使い方が上手な方だな、と。だから、往復書簡としてnoteで質問をいただいたときは驚きましたが、やりとりするのが毎回楽しみでした。
ヤンデル先生との議論であらためて感じたことですが、日本では医療だけではなく、いろいろな分野で制度疲労が発生しています。それなのに、制度自体を刷新するような仕組みがない。それが何よりの問題だと思うのですが。
ヤンデル:「刷新」というのは、実際に変化を起こした経験がある人でないと、そもそも思いつかないことなんですよね。医療についてそれが難しい理由に、医療を一つの生き物として見たとき、「脳」にあたる人や組織がないということがあると思います。今あるのは「手足」ばかりなんじゃないかと。
ヤンデル:「AIに医師が取って代わられる」「いやそんなことはない」という議論が白熱するのも、自分が手足であるという潜在的な危惧がどこかにあって、敏感になっているからなのかもしれません。
佐渡島:政府や厚生労働省、日本医師会といった組織はあっても、それが意思決定の「器官」として機能していないということですよね。取れる手段が診療報酬を変える程度しかないこともありますが、それに加えて医師が病院ごとに分断していて、大勢が連携して何かを起こす仕組みもない。医療制度が崩壊したら国民全員が困るのに、実はそれに責任を持つのが誰なのか、よくわからないという。
ヤンデル:それらの組織は、脳にはなりきれていなくて、脊髄くらいなのかもしれないですね。手足からしてみると、そもそも、医療という生き物の全身像を把握する必要がない。専門化した最先端部分で仕事をしているだけで、普通のビジネスパーソンよりはちょっといい給料がもらえる。そこで満足してしまうので、何かを変えようというモチベーションが起きにくいのだと思うんです。そんな私たちだけでは医療全体を刷新しようという発想はできないし、できたとしても実際にどうすれば変えられるか、イメージのしようがない、というのが、実際に現場で働いている私の本音でもあります。
より現実的には、「このままではいけない」と思っても、仕事量の都合で普段の仕事以上のことなんてする余裕がない、という理由もあります。医療業界では「76日間で今の医療知識が倍になる」とよく言われるのですが、専門の先端部にいたら、知識の伸長を追いかけるだけで精一杯です。医療の制度全体を俯瞰して、「自分の守備範囲はこれくらい」というのをマッピングして、あるべき理想の制度まで道筋をつけて……なんてことまでは到底できない。現場の医師だけでは荷が重いように感じます。
このような構造をすべて把握して、ここに「手足」がない、ここに「神経」が必要だ、と言っている「脳」はまだほとんどいないと思います。
佐渡島:でも、今はヤンデル先生のように、医療業界の内から外に出て発信をする方が増えてきましたよね。
ヤンデル:うーん、できていればいいのですが。今後もっとそういう人が増えてほしいですし、上手なやり方をどんどん模索していかなければいけません。
情報社会を脳に例えるやり方があります。SNSというネットワークが発達した社会を人間の脳神経に例えると、インターネット以前の社会は、哺乳類にすらなっていなかった。最初は、その場その場で外界からの刺激に応じて、局所で反射的に動く、細菌とかクラゲのような存在だったと思います。マスメディアの手助けを借りることで、ようやく爬虫類レベルの脳まで進化した。そして、ソーシャルメディアによって、外の世界を認識しようとする「目」が一気に進化して、高度な情報処理をできるようになってきました。まさに生物の進化を模倣するかのように情報社会は発展していきます。
でも、今はあちこちに「小さな脳」ができてしまって、全体としての最適化が進んでいないのかもしれません。部分最適に留まると、脳ができたところの手足と、そうでないところの手足の間の給料や働き方に大きな差ができてしまう。
全体最適化は急務で、私はこの5年くらいが勝負だと思っています。というのも、時間がかかりすぎると、もしちゃんと脳ができたとしても、すでに手足の関節が痛み、まともに動けないという状況があり得るからです。だから、すでに脳になっている人の知見が必要。そこで、佐渡島さんにいろいろおうかがいしたいなと思いました。
佐渡島:ヤンデル先生のおっしゃる、生物の進化とインターネットによる知性の進化の相似形、特に目が重要というところ、僕はすごくしっくり来ているんです。
僕のいとこが防犯カメラ・監視カメラのクラウドサービスを運営しています。すでに飲食店やジム、動物病院などへの導入が進んでいるのですが、その事例を聞いて医療にも応用できると思いました。病室にカメラを設置し、映像を録画、データをクラウドに保存していく。そのデータをさらに複数の病院で共有し、病状と行動の関連、他にもサーモグラフィーで体温データを測ったり、その他の医学的なデータと統合したり……としていくと、かなりの精度で異常やその予兆を発見することができる。巡回などにかかる人的なリソースも大幅に削減できるようになるはずです。2020年に5G通信がスタートして大量のデータのやりとりがしやすくなれば、もっと進化するでしょう。
佐渡島:現場には一定数の手足がある。より足りないのは目なんですよね。目から見た情報を積み重ねて、脳を作っていく。ミクロでもマクロでも、とにかく今は目を増やす段階なのかもしれません。
ヤンデル:その進化を阻んでしまうのは、もしかすると医療者自身なのかもしれません。私たちは目を導入することに対して、なかなか積極的になれない。なぜかと言うと、多くの医療者が自分たちのことを脳だと思っているところがあるから。でも、脳になる訓練をしておけば、さっきの佐渡島さんのカメラのくだりのような発想により、すでに医療はテクノロジーで大幅に改革されているはずなんですよ。
しかし現実はそうじゃなくて、専門化という流れの中で手足として進化してしまった結果、今の現実がある。現場の人間としてのプライドは大事で、私にもあります。一方で、生き物全体としては手足であるという自覚を持って、一部の人を優秀な目へと育成しなければ、未来がないとも感じます。
「覚悟を決める」で思考を停止しないために
佐渡島:ここまで話を聞いて思ったのは、ヤンデル先生の課題感というのは、医療者が医療業界の内から外に出て、オーディエンスを取り込み、医療業界を拡張するという方向性ですよね。
ヤンデル:たしかに、おっしゃるとおりですね。
佐渡島:でも、医療業界って本来、拡張しなくてもビジネス的にはとても大きい市場じゃないですか。
――2019年に出された経済産業省の資料によると、国内ヘルスケア市場規模は2016年で25兆円、2030年には33兆円にまで拡大するとされています。
佐渡島:対して、出版業界の市場規模は約1.5兆円。桁が違うんです。その点、医療の市場そのものを積極的に取りにいく医療分野のコングロマリットのような企業も影響力を持っていますよね。医師を対象としたポータルサイトを軸に、医薬品マーケティング支援、キャリア支援、病院のシステム構築、ゲノムビジネス、そしてその仕組みを海外にも横展開しようとしている。
もちろんビジネスと情報発信でジャンルは違いますが、目のつけどころが良く、脳がちゃんと働けば、大きな市場で存在感を放つこともできる。ビジネス的に力を持った会社は、実際に医療制度を改革し得るのではないでしょうか。こういう発想の転換も必要だと思います。
ヤンデル:なるほど……。佐渡島さんと対談するまで、私は脳不在の環境下で、いかに全体を最適化するかを考えていたように思います。ビジネスのように全く違うパラダイムで、一気に業界を改革してしまうという発想はありませんでした。
ヤンデル:医療者は「覚悟を決める」ということを正義として掲げてしまっています。医療がいろいろと批判されているのはわかる。現場は多くの矛盾を抱えている。でも、やるしかないじゃん。その覚悟を、良くも悪くも決めてしまっている。逆に言えば、そこで改めて矛盾を直視し、モヤモヤを持ち続ける余裕、度量がないのかもしれません。ハッとしました。佐渡島さんの言葉に殴られた、という感覚です。
――ここで疑問なのですが、医療者が大変な環境の現場で手足を動かしながらも、目を遠くに向けることは可能なのでしょうか。
ヤンデル:自分が医療という生き物全体の中のどこにいるのか、まずはマッピングしてみることでしょうか。その上で、各自がそれぞれの手足で触れた一次情報を世の中にストックしていく。これは従来から病院や学会でおこなわれてきた医学の営みそのものですが、時代に合わせて手法をアップデートすることはできる。情報発信に向いている人がストック情報をSNSのようなソーシャルメディアでやさしく発信したり、マスコミに説明したりする役割を担うのが、これからの時代では今まで以上に必要になるでしょう。
そして、発信を分業することも大事かもしれません。情報をストックすること、流通させること、情報を入手するための方法のサポート、それらに関わる人たちの広報、関わる人たちの仲間意識の醸成、医療に関心のあるコミュニティを多様にそろえること、などです。各人は、できればそのうち1つのことだけするのではなく、2つ以上担当することで、医療者や患者、メディアなど、さまざまなステークホルダーと複数の関わりを持って、ネットワークを作るように意識する。そうすれば、視野を広く維持することができるかもしれない、というのが、現時点での仮説です。
――こうした準備により、患者を診察室に迎え入れることができるようになるわけですよね。では、診察室の中ではどうでしょう。この時代に、診察室で医療者が患者にするべきこと、できることは変化していますか。
ヤンデル:「チームで医療を提供する」という原則がよりはっきりしてくる……かもしれません。そもそも患者のナラティブを共有することは、医師よりも看護師や介護士、ケアマネージャーたちが得意としてきた分野です。SNSによって医療のネガティブな点が強調されやすくなり、患者の不満がフォーカスされやすくなった時代、チームで患者さんと医療を共有するムードをより高めていく。そうすれば、医療者と患者の間の齟齬も減るかもしれません……が、これはまだわかりません。実際にそうなってみないと。
あとは、逆説的になってしまいますけれど、ネットで1対nのコミュニケーションが容易になったことで、診察室という場ではより一層、1対1のコミュニケーションを堪能するべきなのかもしれません。複数相手のコミュニケーションは、ネットワーク上で代替することができる。だったら診察室ではそこでしかできないコミュニケーションをする。それは、雑談だっていいかもしれません。
ただし、診察室で医者と患者が雑談をする余裕を生み出すためにも、結局は並行して目や脳の形成を急がなくてはならないでしょうけれどね。
佐渡島:患者の視点で言えば、やはり、もっと個人に寄り添ってほしいと思いますね。例えば医師が僕に「大丈夫」と言ったとして、人の健康値を100としたときに90の「大丈夫」なのか、60なのか、30なのか。「死にはしない」というレベルの「大丈夫」なのか。わからないわけです。面倒なことかもしれませんが、患者の不安のもとはそんなところにあったりします。
佐渡島:もしそれが医療以外の相談ごとであれば、怒っている人と冷静な人が話し合っているときに、冷静な人が淡々と事実を指摘しても、事態が改善しないという状況があるのはわかるはずですよね。患者は怒っているわけではないけれど、不安で、少なくとも冷静ではない。そこでコミュニケーションエラーが発生しているような気がして、とてももったいないと思います。
正確であろうとするのが医療者のプロフェッショナリズムというのはよくわかります。一方、患者とのコミュニケーションにおいて、正確であることはその体験を改善しないことがあるというのは、念頭に置くべきことかもしれません。「正しい」ということは専門家同士のコミュニケーションの作法であり、それを医師と患者との作法に持ち込んでも、必ずしも機能するわけではない。単一のコミュニティーにしかいない人は、よりそのような傾向があることを警戒するべきではないでしょうか。
ヤンデル:要するに、Twitterをすればいいってことですね(笑)。冗談ではなく、TwitterのようなSNSを活用して、医療クラスタ外とつながることは、医療業界の外の視点を持つために効果的だと思います。
(聞き手・文=朽木誠一郎+ノオト/撮影=栃久保誠)
※2020年2月3日 表記の誤りについてご指摘がありましたので訂正いたしました。
【関連記事】
・「アメリカの『ベッドサイドマナー』に学ぶ、患者コミュニケーション」
・「GoogleクラウドとAIを駆使した遠隔画像診断システムで、医療を変える~目指すのは、患者が医療情報を管理する『医療の民主化』」北村直幸氏(放射線科医/㈱エムネス代表取締役)
・「『医者は僕にとってのヒーローなんです』現役医師の疑問を『コウノドリ』作者・鈴ノ木ユウ先生に聞いてみた」
・「『外科医』という仕事の魅力」山本健人氏[けいゆう先生]
・「医師不足地域になぜ医師は集まらないのか?―転職データとアンケートから読み解く、医師の偏在の背景と対処法―」[医師転職研究所]
・「医師不足の負のスパイラルに拍車をかける?医師不足地域での残業時間の上限緩和案」[医師転職研究所]

- 佐渡島 庸平氏(さどしま・ようへい)
- 2002年講談社入社。週刊モーニング編集部にて、『ドラゴン桜』(三田紀房)、『働きマン』(安野モヨコ)、『宇宙兄弟』(小山宙哉)などの編集を担当する。2012年講談社退社後、クリエイターのエージェント会社、コルクを創業。著名作家陣とエージェント契約を結び、作品編集、著作権管理、ファンコミュニティ形成・運営などを行う。従来の出版流通の形の先にあるインターネット時代のエンターテイメントのモデル構築を目指している。著書に『WE ARE LONELY,BUT NOT ALONE. ~現代の孤独と持続可能な経済圏としてのコミュニティ~』など。
https://corkagency.com/

- 病理医ヤンデル先生[本名:市原 真氏(いちはら・しん)]
- 1978年生まれ。2003年北海道大学医学部卒、国立がんセンター中央病院(現国立がん研究センター中央病院)研修後、札幌厚生病院病理診断科。医学博士。病理専門医・研修指導医、臨床検査管理医、細胞診専門医。日本病理学会学術評議員。著書に『どこからが病気なの?』『病理医ヤンデルのおおまじめなひとりごと~常識をくつがえす“病院・医者・医療”のリアルな話』『Dr. ヤンデルの病院選び 〜ヤムリエの作法〜』『いち病理医の「リアル」』『症状を知り、病気を探る 病理医ヤンデル先生が「わかりやすく」語る』など。





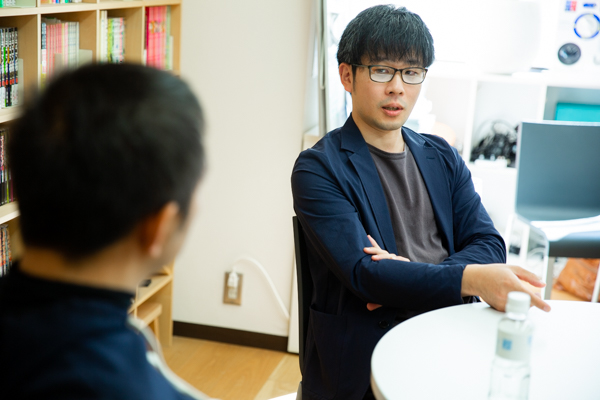



 公式SNS
公式SNS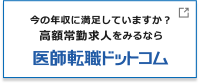
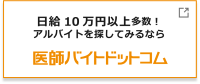















コメントを投稿する
コメント一覧(3件)
3. このコメントは承認待ちです。
2. このコメントは承認待ちです。
1. このコメントは承認待ちです。