日常診療における対話(ダイアローグ)の重要性
孫 大輔 氏(家庭医/鳥取大学医学部 地域医療学講座/日野病院組合日野病院 総合診療科)

診察室で感じる「患者とのコミュニケーションの限界」。当然ながら診察となると、患者と話せる時間は限られています。こうした中で、患者は医師に本音を話せているのだろうかと、医師と患者の関係性に意識を向けた家庭医がいます。
孫大輔先生は高校生のころ、突然発生する原因不明のかゆみに悩まされ、ある病院を受診。医師の話に納得がいかなかったこと、自身の話を十分に聞いてもらえなかったことから、医師に対して不満を抱いたといいます。しかし、その後に行った漢方クリニックの医師は症状を丁寧に聞いてくれ、納得感と大きな満足感を得たそうです。
生物医学的な視点から病気を説明する医師。一方で、症状や苦痛、その症状の自分なりの解釈といった主観的な経験を理解してほしい患者。両者の間には、「まなざし」の違いがあるのではないか。「白衣を着た医師」と「専門知識に差がある患者」という力の不均衡が納得できない診察につながっているのではないか。
そう考えた孫先生は、医師と患者が対等に近い関係性で言葉をつむぎ合う方法として「対話」を学び、市民と医療者の対話の場「みんくるカフェ」や、地域コミュニティに根差したプロジェクト「谷根千まちばの健康プロジェクト(通称:まちけん)」を始めました。
今回は、患者との双方向の対話を大切にする孫先生に、対話の重要性や対話の原則、対話による治療的アプローチを解説いただきます。
- 目次
-
- 1.対話はなぜ必要か
- 2.対話(ダイアローグ)の原則
- 3.臨床における対話実践
対話はなぜ必要か
さまざまな考え方や価値観が登場し、多様性が顕在化した現代において、他者同士がコミュニケーションをとることはますます難しくなっている。自分と異なる背景を持つ者とのコミュニケーションは誤解や対立を生みやすく、円滑な言葉のやりとりを行うのは簡単ではない。むろん、医療現場における患者と医療者のコミュニケーションも同様である。こうした状況下で、対話の重要性がますます増している。
私は対話とは「一期一会」のコミュニケーションだと考えている。対話は英語で「Dialogue」であるが、ギリシャ語の「Dialogos」に由来しており、「Logos」(言葉)と「dia」(~を通して)に分けられる。つまり、言葉を通して意味をやりとりするという意味である。これは複数の人の間に一種の「意味の流れ」が生じ、そこから何か新たな理解が生まれてくる、ということである。
私が対話を行うときは、常に他者は自分が想像できる以上の世界を持っているという「他者尊重」の意識を持つようにしている。極端に言えば、相手の語りを一言一句聞き漏らすまいという姿勢で臨む。また言葉を発するときは、「~と私は感じますが、どうでしょうか」と、あくまで自分の考えとして述べ、それが正しいかどうかは保留した形とする。常に「自分の考えは正しくないかもしれない」という考えが前提になり、相手の世界観を自分が正しく理解できたかどうかを相手に確認しながら言葉を発する。何にも邪魔されずに、相手の言葉と存在を受け止め、また自分がその場で感じたことを、お盆にコップをそっと載せるように声にするというやりとりなのである。
みなさんは、最近こうした対話を、誰かと15分や20分でも行ったであろうか。もし行ったとしたら、それは非常に充実した、豊かな時間となる。
対話は、日常でも、医療・福祉の世界でも、まちづくりや政治においても、あらゆる分野で行われている。
医療・福祉の現場においては、患者と家族、複数の医療従事者で「話し合い」が行われることがあるが、これを相手の思いを丁寧に汲み取りながら、真摯な態度で行えば、それは対話的コミュニケーションとなる。ただ残念ながら、現実には日本でこのような対話的コミュニケーションを実践しているところは少ない。一方、フィンランドでは1980年代から、精神医療や福祉の現場で「対話」が治療的あるいは予防的なアプローチとして実践されてきた。オープンダイアローグ(Open Dialogue)や、未来語りのダイアローグ(Anticipation Dialogues)と呼ばれるものがそれである。オープンダイアローグの実際については後述する。
対話(ダイアローグ)の原則
対話するときにはどのような心構えが重要であるのか。オープンダイアローグにも7つの原則などが紹介されているが、ここでは、先述した対話の哲学の考えを基礎に置きつつ、私自身が重要と考える原則を5つ提示する。
これらは、医師と患者の一対一の場面よりむしろ、医師・他職種と患者・家族が話し合うような複数での対話場面で応用しやすい。もちろん、診察室で行う医師・患者間のコミュニケーションにも取り入れると、患者中心のコミュニケーションに近づいていくと考えられる。
(1)「話す」と「聞く」を分ける
これは、話す人と聞く人を分けるという原則である。誰かが話し手のときは、他の人は聞き手になるというシンプルなことである。人の話を遮って話す、あるいは話し終わらないうちに話し始めるのは御法度である。
あるいは、話す時間と聞く時間を分けるという言い方もできる。時間を分ければ、同じ人でも話し手から聞き手になる。
オープンダイアローグでは、途中で「リフレクティング」という時間を入れることもある。リフレクティングとは、話の聞き手同士で感想を話し合っている様子を話し手だった人が観察する手法である。これにより話し手は自分の噂話を目の前で聞くような体験をする。このとき、話す人(たち)と聞く人たちを交代させるような形となる。これも、この原則に則っている。
(2)応答する
語られたことに対して応答するという原則である。「応答」は、何も言葉である必要はなく、うなずきやあいづち、表情、ちょっとした動きといった態度で表してもよい。言葉にするときは、相手への敬意を忘れずに声にする。用意された言葉ではなく、その場で生まれる自然な反応を返す形でよい。その言葉の応答のネットワークによって、その場に安心できる空間が生まれる。
(3)「今、ここ」を大事にする
対話では、その場で感じたことや考えたことを言葉にして返していくというやりとりが重要となる。なぜなら、もともと持っていた意見を相手にぶつけるだけでは、それは「議論」になってしまう。対話は勝ち負けのないやりとりであり、お互いが相手の世界観を汲み取ろうとする共同行為であり、論理よりむしろ感情や気持ちを大切にする。
対話の中では、自分が「今、ここ」で感じたことや考えたことを、ぽつりぽつりとその場に出していく。対話のときの話し方は早口ではなく、ゆっくりとした語りとなり、ときには言いよどんだり、沈黙をはさみながら語る。
(4)不確実性に寛容になる
対話の際には早急に答えや解決を求めてはいけない。なぜなら、相手の話を聞きながら「なるほど、○○さんの話はこういうことだな」とか「○○さんは△△という状態に陥っていて、××という対処をとった方がよい」などと考えてしまうと、途端に相手にアドバイスをしたくなってしまうためだ。人というのは困っている人の話を聞くと、アドバイスをしたくなるものである。しかし、こうした早期のラベリングは、相手が体験している非常に深くて多様な世界観や、その経験の総体を捉えそこなうことになる。
対話の際、相手の話を聞いているときは、自分が理解しているのはその一部に過ぎないだろうという姿勢で聞き続ける。そして、不確実性にとどまりながら、早急に解決を求めず、お互いにつむいでいく言葉のネットワークを意識すると、自然に新しい地点(意味)に到達できる。
(5)ポリフォニー(多声性)
「ポリフォニー(多声性)」とは、対話の場に参加するすべての人の「声」が発せられ、そのどれもが主役でも脇役でもなく、お互い対等な立場で、すべての言葉が尊重される状態を指す。よって、ここでは参加する者同士は、肩書や身分がどうであろうと「対等性(水平性)」が保たれることとなる。
「議論」の場合は、どの意見がより合理的かといったことで優劣が決まる。一方で「対話」の場合は、優れた意見が出てほしいということではなく、すべての人の多彩な考えが場に出る方がよいと考える。どんなに小さな「声」であっても、大きな「声」と同じくらい重要と考えること。その「声」が発せられるということ自体が重要であること。そうした「ポリフォニー」の状態を目指すことで、対話は続くのである。
臨床における対話実践
オープンダイアローグは、精神科領域にとどまらず、プライマリケア領域でも活用できる。例えば、終末期について患者・家族と話し合うACP(アドバンス・ケア・プラニング)の場や、社会的要因が複雑に絡むケースについて患者と関係者を含めて話し合う場である。医療従事者が主導するのではなく、患者や家族の語りから気持ちなどを十分に汲み取りながら、答えのない問題について対話を行いたいときに、オープンダイアローグは有効な方法となりえるであろう。
また、「ダイアローグ」は方法論というよりは哲学・原則に近いものである。今回紹介した5つの原則などを普段の診療場面でも活用することは、医師・患者との一対一のコミュニケーションにおいても十分に資するものであると考えている。
<参考文献>
・オープンダイアローグ・ネットワーク・ジャパン (ODNJP)「オープンダイアローグ 対話実践のガイドライン(第1版)」(2018)
・ヤーコ・セイックラ,トム・エーリク・アーンキル『オープンダイアローグ』 (2016)高木俊介・岡田愛訳, 日本評論社
・日本プライマリ・ケア連合学会誌「不確実性に耐える: オープンダイアローグがプライマリ・ケアにもたらす新たな可能性」41(3): 129-132 (2018) 孫大輔・塚原美穂子
【関連記事】
・「アメリカの『ベッドサイドマナー』に学ぶ、患者コミュニケーション」
・「治す医療から治し支える医療へ これからの地域で求められる、在宅医療での患者との関わり方」
・「医師のあなたに知ってほしい。医療現場でのLGBT」
・「弁護士が教える医師のためのトラブル回避術【第9回】モンスター患者対応の心得」
・「『診察室に来る前』の患者に今、起きていること 医療者にできるアプローチとは〜佐渡島庸平氏(編集者)×病理医ヤンデル先生」
・「医師に試してほしいお薦め最新アプリ【第1回】コミュニケーションに役立つアプリ」

- 孫 大輔(そん・だいすけ)
- 1976年、佐賀県に生まれる。2000年、東京大学医学部を卒業。腎臓内科医として働いた後、患者さん目線に近い医療がしたいと家庭医に転向する。鳥取大学医学部 地域医療学講座、日野病院組合日野病院 総合診療科勤務。日本プライマリ・ケア連合学会認定家庭医療専門医。一般社団法人みんくるプロデュース代表理事、谷根千まちばの健康プロジェクト(まちけん)代表。大学では臨床教育、コミュニケーション教育、研究などに従事。著書に『対話する医療 ―人間全体を診て癒すために』(単著、さくら舎)、『人材開発研究大全』(分担執筆、東京大学出版会)、『「ラーニングフルエイジング」とは何か――超高齢社会における学びの可能性』(分担執筆、ミネルヴァ書房)。




 公式SNS
公式SNS
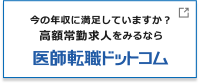
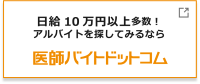



















コメントを投稿する