実はこの人も医者だった!?
医師からキャリアチェンジした偉人達 Part2

「民衆の立場から革命を率いた」ジャン=ポール・マラー(フランス・18世紀)
ジャン=ポール・マラーはフランス革命の主導者として名高い人物です。ブルボン王朝が倒れ国民による政府が建てられたフランス革命は、現代の民主主義の土台ともなりました。
マラーはスイスの中流市民の家に生まれました。幼い頃より病弱で室内に引きこもることが多く、運動よりも勉強を好む少年でした。母親を10代のうちに亡くした彼は、自身の見聞を広げるべく西欧諸国を巡ります。もともと好奇心が強くさまざまなことに興味を持っていましたが、最終的には医師になる道を選び、ロンドンで開業医となります。
その後はパリに移住し、ルイ16世(かの有名なマリー・アントワネットの夫)の弟であるアルトワ伯の元で侍医として働きました。中流市民の身でありながら勉学を重ね、宮廷に仕える医師となったのです。マラーはこの際に自分専用の実験室を作らせ、自然科学の論文を執筆する傍ら、刑罰制度の改革を論じた著作なども発表しています。自然科学については電気の特性に深い関心を持ち、ライデン瓶と摩擦起電機を用いた静電気療法を行いっていたとも伝えられています。ちなみにライデン瓶と摩擦起電機とは、現在でいう電位治療器のようなものです。
1789年、フランス革命が勃発。王政が崩壊し国民によるフランス政府が建てられました。このとき政権を握ったのがジャコバン・クラブと呼ばれる政治グループで、彼らは王侯貴族などの富裕層を激しく非難する思想を持っていました。侍医として仕える中で宮廷の腐敗を目の当たりにしていたマラーは、王政のことをあまり良く思っておらず、ジャコバン派の考えに賛同。新聞『人民の友』を発行し、王政を鋭く批判して民衆の支持を得ました。さらに国民公会議員に選出されてジャコバン派の指導者の一人となります。ジャコバン派の考えに背く者をすべて断頭台送りにするその政治は、「恐怖政治」と呼ばれ恐れられました。
ある日のこと、シャルロット・コルデーという若く美しい女性が彼を訪ねてきました。彼女は「裏切り者の名前を教えに来た」といいます。マラーは当時、持病の皮膚病が悪化していたため、一日中浴槽に浸かる生活を送っていました。温泉療法のようなもので、お湯に硫黄や薬草を溶かしていたそうです。そこでマラーは湯船に浸かったまま面会を行うことにします。密告しようとシャルロットはマラーの湯船に近づきます。その瞬間、彼女は隠し持っていたナイフを振り上げ、マラーの胸を一突きにしました。実は彼女、ジャコバン派に虐げられていた貧しい貴族の娘であり、恐怖政治を行うマラーを憎んで暗殺に来たのです。彼は心臓そばの血管を刺され、ほぼ即死だったといいます。マラーは死後、革命の殉教者として民主から崇拝を受けました。
その暗殺の様子は、彼の同志であった画家のダヴィッドの手により「マラーの死」としてドラマチックに描かれ、現代も語り継がれています。
「村医師から軍神となった」大村益次郎(日本・19世紀)
大村益次郎(村田蔵六)は幕末期の兵学者で、戊辰戦争の指揮をとり長州藩を勝利へ導いた人物です。戊辰戦争とは王政復古を経て明治政府を立ち上げた新政府軍と、徳川幕府を支持する旧幕府軍との戦いです。
大村益次郎は1824年、長州藩(現・山口県)の村医者の家に生まれました。10代のうちから医学や蘭学を学び、大阪に出てからは緒方洪庵の経営する適塾で蘭学を学びました。ちなみに適塾はのちの大阪大学医学部で、かの福沢諭吉や橋本左内も学んだ場所です。大村は蘭学を熱心に研究し、塾頭にまで上り詰めました。とても頭がよく、何事も論理的に考える性格だったと伝えられています。その後は長州で開業し村医者として活動しましたが、理詰めで考える性格ゆえに無愛想であり、また治療の手技も上手ではなく、あまり医者には向いていなかったといわれています。
大村益次郎の人柄については、以下のようなエピソードが伝えられています。
益次郎の父親もまた医師で、彼は患者の気持ちを思いやる性格でした。患者の身体に異常が認められなくとも、「気分が悪いんです」と訴えられればとりあえず葛根湯を処方し、「これを飲めば良くなる」と言って返したそうです。患者に対するプラシーボ効果を期待していたのでしょうか。それに対して大村益次郎は大変な理論家であったために、身体に異常が認められないときは頑として薬を処方しませんでした。「どこも悪いところはない、帰って寝なさい」と患者を家に突き返してしまうのです。もちろん体に悪いところはないので、薬を処方してもしなくても同じなのですが……。その頑固さが仇となり、村人からは「あいつは薬も出してくれない、患者に冷たいヤブ医者だ」と噂されていたそうです。
そんな彼に転機が訪れたのは、黒船が来航し幕藩体制が揺らぎ始めた頃のことでした。蘭学の必要性が唱えられる時代になり、大村は宇和島藩に呼ばれて洋書の翻訳や蘭学の講義をすることになりました。この仕事ぶりに目をつけたのが、長州藩の桂小太郎です。「大村の優れた頭脳と蘭学の才能はきっと倒幕に役立つ」と踏んだ桂は、大村を長州藩の藩士としてスカウトします。こうして医師から藩士となった大村は、長州藩の軍政改革を任されました。
蘭学に秀でた大村は、近代兵器と西洋の兵法を備えた中央集権的な軍隊を整備しました。最新の武器を備えた新政府軍は、旧幕府軍を圧倒していきます。大村は戦略・戦術にも大変優れており、どんな戦況でも冷静に的確な判断を下す知将でした。彼の考案する作戦は、理論を重んじるあまり、ときに「冷徹」と評されることもありましたが、確実に戦果を上げていきます。まさに軍神ともいうべき大村の秀でた才能と優れた指揮により、倒幕は達成。明治維新の隠れた立役者だったのです。
「祖国の危機を救う『国医』を目指した」孫文(中国・20世紀)
中国の政治家である孫文は中国革命の象徴であり、中華民国(台湾)では現在も国父として敬愛され続ける人物です。
孫文は1866年に広東の農家に生まれました。ハワイにいた兄を頼って14歳で渡米し、ハワイの学校で教育を受けます。そこで西洋の思想やアメリカの民主主義に触れて、19歳で広東に戻りました。その後は香港で西洋医学を学び、澳門(マカオ)の広州にある病院に眼科医として勤めます。当時のマカオは中国医学が中心でしたが、孫文の勤め先では治療に西洋医学を採用することとなり、孫文が招かれたのです。勤務医として勤めてすぐに、孫文は開業医に転じます。その頃、マカオはポルトガルの植民地であり、ポルトガル人医師が幅を利かせていました。孫文は中国人という「よそ者」であるためにあまり歓迎されませんでしたが、めげずに医師としての使命を全うします。その一生懸命さから患者からの評判はよく、分院を出すほどになりました。しかし病院が発展する一方で、彼は医療によって人を救うことへの限界を感じていました。
当時の中国は清王朝が300年以上も支配を続けており、その腐敗した政治体制のもと、民衆は苦しい生活を強いられていました。この堕落した清王朝を倒さないかぎり、祖国である中国に未来はない。医術は目の前の人を救うことはできるけれど、自分の手の届かないところにいる人を救うことはできない。それならば自分は個人を救う医師よりも、「国を救う医師」でありたいと、孫文は考えたのです。そして彼は、医師の職を捨てて政治家への道を歩みます。
まずは革命を目指して興中会を組織し広州で挙兵しましたが、この計画は失敗に終わりました。しかし彼は一度の失敗でめげるような人物ではありません。日本へ亡命して革命の準備を整えます。日本で力を蓄えながら、革命の機会をじっくりと窺っていたのです。
1911年、孫文を中心とした革命組織は辛亥革命を起こし、ついに清朝を倒します。ここにアジア史上初の共和制国家である中華民国が誕生し、孫文は臨時大総統の座に就きました。彼はその後すぐに大総統の座を降りることとなりますが、祖国をより良い国にするため、懸命な政治活動を続けました。
1925年、孫文はがんによって亡くなります。遺言では「革命尚未成功、同志仍須努力 (革命なおいまだ成功せず、同士よってすべからく努力すべし)」と述べ、臨終の瞬間まで愛する祖国の未来を心配していました。
*
現代の民主主義の土台ともなるフランス革命を率いたマラー。
新政府軍を勝利に導くことで、新たな日本の礎を築いた大村益次郎。
国医として、最期まで愛する祖国を思い続けた孫文。
3人のキャリアチェンジがなければ、世界のありようは現在とはだいぶ違ったものになっていたかもしれません。
(文・エピロギ編集部)
【関連記事】
医師からキャリアチェンジした偉人達 Part1
時代を越える金言 ~医師や医学者の名言集~
いばらの道を駆け抜けた女性医師たち|第1回 与えられなかった女医と、与えられた女医
医局の歴史|第1回 医局の成立と大学への医師の集中





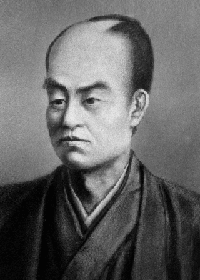

 公式SNS
公式SNS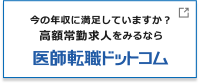
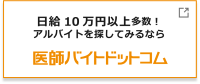















コメントを投稿する