第5回 近代ホスピスの母 シシリー・ソンダース

厚生労働省が発表した「平成28年(2016年)医師・歯科医師・薬剤師調査の概況」によれば、医師数319,480人のうち、女性は67,493人(総数の21.1%)。若い年代ほどその割合は高く、29歳以下では34.6%と3割を超えるなど、日本における女性医師の割合は年々増加を続けています。
しかし、かつての日本には、男尊女卑の慣習から女性が医師になることすら許されなかった時代がありました。この事実は、国外に目を向けても同じことがいえます。
女性に対してのみ閉ざされていた医学教育の扉。それをこじ開けるように、時代の流れに逆らうことで医師となった女性たちが、世界各地に存在していたのです。
日本の女医を紹介するシリーズ「いばらの道を駆け抜けた女性医師たち」を承継し、舞台を世界に再設定した本企画。第5回の主人公は、“近代ホスピスの母”と呼ばれ、その偉業から爵位の称号を与えられた英国の女性医師「シシリー・ソンダース」です。
シシリー・ソンダース ホスピス運動の先駆けとなった女性
聡明で議論好きだった少女
1918年、イギリス・ロンドン北部に暮らす裕福な家庭で、シシリー・ソンダースは生まれました。父はやり手の不動産業者で、一家は高級住宅街バーネット区に屋敷を構え、召使いを雇っていました。父は社交的で明るく、母は完璧主義な性格の持ち主。シシリーは両親それぞれの性格を受け継いで育ちます。
シシリーには2人の弟がいました。3姉弟は幼い頃から成績優秀で、シシリーは特に父と議論をするのが好きでした。朝食の時間に論戦に熱中するあまり、たびたび父の出社を遅らせていたそう。父は同僚に「シシリーとまたやってきたのかい?」とからかわていたといいます。
政治家秘書から看護師へ
シシリーは中等教育を終えた後、ソサエティ・オブ・ホーム・スチューデンツ(現在のオックスフォード大学 聖アン・カレッジ)に入学します。もともと看護師に憧れていた彼女ですが、両親に反対され、大学では政治家秘書を目指して政治学・哲学・経済学を学んでいました。
ところが1939年、シシリーが21歳のときに第二次世界大戦が勃発。学業を一時中断して戦時看護師になることを決意します。戦時下で「勉強どころではない」という雰囲気が学校に漂っており、また世間は確実に看護師を必要としていました。このチャンスに乗るしかない。そう感じた彼女はその後すぐにナイチンゲール看護学校に「看護師の訓練を受けさせてほしい」と手紙を送り、返事を待ちました。
閉ざされた看護師の夢
22歳のとき、シシリーは念願叶ってナイチンゲール看護学校に入学します。戦時下での看護実習は生易しいものではありませんでした。ネコの餌のような粗末な食事をとり、そこらじゅうに虫がわく劣悪な環境の中で夜通し働いたシシリー。しかし彼女はその状況を苦とせず、むしろ看護師を天職と感じていました。見習い看護師のリーダーを務め、皆に頼られ、強いやりがいを感じていたのです。
ところが、シシリーの看護師としてのキャリアはわずか3年で終わりを告げます。日々の激務により生まれつきの背中の持病が悪化したのです。外科医からの忠告により看護師の仕事を離れることになったシシリーは、深い挫折を味わいます。
アルモナー時代
「患者のそばにいられる仕事がしたい」と考えていたシシリーは、聖アン・ソサエティ(ソサエティ・オブ・ホーム・スチューデンツより1942年に変更)に復学し、アルモナー(現在の医療ソーシャルワーカー)を目指して勉強を始めます。看護師の仕事に未練がなかったわけではありません。勉強していると、厳しくも充実していた看護師時代の生活が恋しくなることもあったようです。しかし、何でも完璧にやらないと気が済まない母譲りの気性を持つシシリー。看護師時代も仲間内でトップの成績でしたが、聖アン・ソサエティでも2年かかる勉強を1年で終わらせ、政治学と公衆社会管理学の2教科で最優秀の成績を修めて卒業しました。
末期の患者デヴィッドとの出会い
29歳になったシシリーは、聖トーマス病院にアルモナーとして就職します。ここで出会った一人の患者が、その後の彼女の運命を大きく変えることになりました。患者の名はデヴィッド・タスマ。戦争で国を逃れてきたポーランド系ユダヤ人です。二人は惹かれ合い、やがて恋に落ちます。しかし、そのときすでにデヴィッドの体は末期がんに侵されていました。
シシリーはデヴィッドが最期を迎えるその瞬間まで、彼のそばに寄り添い続けました。二人が会った回数はわずか25回でしたが、1回1回の時間を大切に過ごしました。二人の関係が深かったことを表す、こんな話が残っています。
――クリスチャンであるシシリーは、デヴィッドを慰めるため聖書をよく読み聞かせていました。ある日、シシリーがいつものように聖書の一節を読み上げると、デヴィッドは彼女が詩を読み続けるのを止めて、こう言いました。「ダメだよ。僕は君の頭と心の中にあるものだけが聞きたいんだ」。
デヴィッドは死の直前、「やっと安らぎを感じるようになった」と病棟看護師に話したそうです。彼はシシリーの心の内側から生まれてくる優しさを求め、心のこもらない形だけの“慰み”を受け入れませんでした。死にゆく人に寄り添うには、表面的なケアではなく心からのケアが必要なのだ。シシリーはそう気づかされ、以来これが彼女の生き方の根幹となり、ホスピスの理念を形づくっていったのでした。
聖ルークスでの発見
デヴィッドの死後、「死にゆく人のために仕事をしたい」という思いを強めたシシリーは、聖トーマス病院を辞め、死期が迫った貧困層の人々のための福祉施設、聖ルークスで夜間看護師のボランティアとして働き始めます。
ここで彼女はあることに驚きました。聖ルークスでは、鎮痛剤として麻薬が定期的に投与され、それにより患者は心も体も安定した状態を保っていたのです。
当時は、治癒の見込みがない患者は手荒に治療されていた時代。医師は患者が苦しみ始めてからようやく薬を投与していました。死期が近い患者の苦しみを少しでも取り除くには、このシンプルな方法が使えるかもしれない。デヴィッドのような末期患者を苦しみから救いたいと思っていたシシリーは、それを具体的に実践するためのヒントを得たのです。
看護師から医師へ
ボランティアとして短時間働いていたシシリーは、次第に仕事に対して物足りなさを感じるようになりました。死にゆく患者にもっと多くの時間寄り添いたい、という思いを捨てきれなかったのです。彼女は以前アルモナーとして働いていた聖トーマス病院のバレット教授に「夜勤看護師として働きたい」と相談しました。
バレット教授は、彼女にこうアドバイスしたといいます。「看護師という身分では相手にされず苦労する可能性があるし、疼痛コントロールの専門知識を学ぶ上でも医師になるのが賢明だ」。そしてもう一言、「末期患者を見捨てているのは、医者なんだ」と。このときすでに30代だったシシリー。医師になるには遅いスタートでしたが、医師になることを決断します。
痛みをコントロールする先駆的な研究
内科学、外科学、小児科学、免疫学、法医学……。現代と同じように、当時の医学生が学ぶ内容も多岐にわたっていました。看護や福祉の知識があったとはいえ、これらの広範な医学知識を30歳を過ぎて身に付けるには相当の努力が必要だったことでしょう。それでもシシリーは、末期患者の苦痛を和らげる方法を見出すという目的のため寸暇を惜しんで勉学に励み、38歳で医師免許を取得します。
1958年には、聖メアリー病院で研究員として奨学金をもらいながら末期患者の研究を開始。さらに研究のかたわら週3回、聖ジョゼフ・ホスピスに医師として勤め、末期患者のケア方法の改善にあたりました。同ホスピスでは聖ルークスで学んだ投薬方法を導入し、使う麻薬(モルヒネやヘロインなど)の種類や投与のタイミングを試行錯誤しながら、1,000人以上の末期患者の経過を観察。また、投与方法の工夫により、患者の痛みを和らげようと尽力しました。
当時医師の間では、麻薬の定期的な投与は(薬に対する抵抗力がついて)薬の効き目を下げたり、薬物依存につながったりするとされていました。しかし、研究データをもとにシシリーは「そうした事態が起こる可能性はまれで、定期的な投薬によって末期患者の痛みを和らげることができる」と論文で発表します。この研究結果は先駆的だとして高い評価を受け、彼女の名は医療の世界に知れ渡っていきました。ホスピスの見学者たちは「ここの患者は落ち着いていて、痛みがあるように見えない」と口を揃えて評したといいます。医者になって3年目、41歳の時のことでした。
聖ジョゼフ・ホスピスでの研究に確かな手ごたえを感じたシシリー。自分のホスピスを建てたいと思い始めていた彼女は、その構想を実行に移します。
聖クリストファー・ホスピスの設立とホスピス運動の広まり
1967年、シシリーが49歳のとき、聖クリストファー・ホスピスを開設します。設立にあたって資金面での困難にも見舞われましたが、彼女の理念に共感する人々の支援を受けたほか、父親譲りの天性のビジネスセンスを発揮し、その窮地を切り抜けました。
聖クリストファー・ホスピスは、研究・教育・在宅ケアの3つの機能を持った施設です。死にゆく人々のケアに関する研究を促進する、医療従事者の教育・育成の役割を担う、ホスピスだけでなく患者の自宅でもケアを行う。この3つを主軸として運営され、やがて“ホスピスの聖地”と称されるまでに発展を遂げました。彼女が世界中を飛び回って講演をしたかいもあって、各国から医療従事者が訪れ、自国に知識を持ち帰ることでホスピスがさらに広範囲に普及しました。
1980年、シシリーは62歳で英国女王から爵位の称号(国家功労者に贈られる称号)を授与され、翌年には宗教界のノーベル賞にあたるテンプルトン賞を受賞しました。聖クリストファー・ホスピスはキリスト教を背景に持つため、宗教の発展にも貢献したとして評価されたのです。また、1990年にWHO(世界保健機関)が『がんの痛みからの解放とパリアティブ・ケア』を刊行したことも、ホスピスの概念がさらに世界に広まるきっかけとなりました。
聖クリストファー・ホスピスの哲学
シシリーは常に患者と同じ目線に立ち、技術だけでなく心からの思いやりを与えることも大切にしました。例えば、ホスピスの患者に「自分はいつ死ぬのか?」と聞かれた際に、「顔を合わせるなりそれを知りたがるのはどうして?」と尋ね、患者が信頼するシシリーから事実を知りたがっていることが分かると、簡潔かつ明確に「良くはならないわ」と伝えたという話が残っています。
その場で“優しい嘘”をついたりストレートに死を宣告したりするのではなく、必要としていれば真実を伝える。彼女はまず患者の気持ちに寄り添うことを念頭に置き、選択権を常に患者に持たせるように配慮しました。患者との平等な目線を大切にしたシシリーは、“Be there”(共にある)という言葉を大事にしていたそうです。この言葉の中に、聖クリストファー・ホスピスの哲学が集約されていると言えるかもしれません。
また、シシリーは聖クリストファー・ホスピスを、命の終わりと始まりが日常として存在する“1つの村”に例えたといいます。ホスピスには患者が生活する病棟のほかに、ボランティアスタッフが居間や寝床として利用するドレイパー棟や、職員の子どもが過ごす保育室があり、インコや魚などの小動物も一緒に暮らしていたそうです。気軽に患者の家族が訪れて、スタッフと親戚が一堂に会して和やかな雰囲気の中、バースデーパーティーが行われることもあったといいます。互いを世話し世話されるという相互性が、このホスピスで過ごす患者とスタッフが互いに尊重し合う姿勢を持つことにつながっていたのでしょう。
「死の顔を変えた」シシリー・ソンダース
今や“近代ホスピスの母”と呼ばれるシシリー・ソンダース。彼女の功績は「定期的な投薬による痛みの緩和の発見」だけではありません。死が迫った患者に何ができるかを徹底的に追求し、死ぬまで生きる手伝いをする“ポジティブなケア・アプローチ”の実践により、死を敗北と捉えていた当時の医師に、死は敗北ではなく達成点なのだと気づかせました。
患者に回復の見込みがないと分かった途端、諦めたり哀れみの態度で接したりするのは患者から距離を置いて差別することと変わりない。患者に死が近づいているときに医師がすべきなのは、より良い最期を迎えるために患者の心に寄り添うことではないかと示したのです。
「死の顔を変えた」「医療に人間性を取り戻した」。ホスピス運動が広まるきっかけをつくったシシリーは、現在も世界中から高く評価されています。多くの苦難にさらされながらも、患者のそばに寄り添い続けたシシリー・ソンダース。その精神はホスピスを学ぶ者たちに脈々と受け継がれています。
「あなたはあなただから大切なのであり、あなたの最期のときまで大切です。あなたが心安らかに死を迎えられるだけでなく、死ぬまで生きられるようにできる限りのことをいたします」――シシリー・ソンダース
(文・エピロギ編集部)
<参考>
シャーリー・ドゥブレイ、マリアン・ランキン著 若林一美 監訳『近代ホスピス運動の創始者 シシリー・ソンダース 増補新装版』(日本看護協会出版会、2016)
シシリー・ソンダース 著 小森康永 編訳『ナースのためのシシリー・ソンダース: ターミナルケア 死にゆく人に寄り添うということ』(北大路書房、2017)
宮下光令『ナーシング・グラフィカ成人看護学⑥』緩和ケア(メディカ出版、2016)
編集部のページby日本看護協会出版会「近代ホスピス運動の創始者 シシリー・ソンダースの生涯」
(http://jnapcdc.com/archives/13865)
ふじ内科クリニック「シシリー・ソンダースとホスピス」
(http://www.naito-izumi.net/archives/60.html)
日本緩和医療学会 理事長 恒藤暁「患者のいのちを見出す医療を目指して『緩和医療における“Total Pain”の考え方』」(市民のためのがん治療の会)
(http://www.com-info.org/ima/ima_20120215_tunetou.html)
【関連記事】
・「いばらの道を駆け抜けた女性医師たち|第1回 与えられなかった女医と、与えられた女医」
・越川病院 越川貴史氏インタビュー「生き抜く生命と歩む『緩和医療』〜『より良い状態』への選択肢をひとつでも多く手渡すために〜」
・<PR>緩和ケアの医師求人&ニーズ動向情報




 公式SNS
公式SNS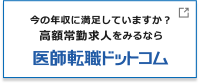
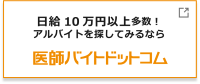


















コメントを投稿する